2期連続の最高益更新のセブン&アイの弱点とは!?
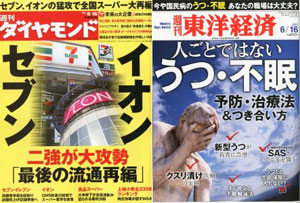 (左)「週刊ダイヤモンド 6/1号」
(左)「週刊ダイヤモンド 6/1号」
(右)「週刊東洋経済 6/16号」
まず、イオンは2011年、年商約3000億円の規模を持つ四国の有力スーパー、マルナカとその関連会社を買収。セブン&アイは近畿日本鉄道子会社のスーパー、近商ストアに30%出資するなど、攻めの戦略を展開している。この再編機運は大きな動きになっていて、背景には、市場が縮小しているなかでの各スーパーの生き残り策、西友の立て直しに一定のメドがついてきたアメリカ・ウォルマートの国内での事業拡大としてのM&A攻勢といった動きがある。
13年3月には、債務返済を猶予する中小企業金融円滑化法が期限切れとなり、経営危機に陥る地方のスーパーが出てくる。これをきっかけに、業界再編の大きな動きになっていくのではないかというのだ。
「業界再編は今後も進む。日本の市場サイズから見れば(年商)2~3兆円規模の食品スーパーが複数あってもおかしくない」と、イオンの岡田元也社長はスーパーの事業拡大に積極的だ。
イオンの年商(売上高)は5兆円。営業利益のうち、スーパーで4割、商業施設開発で2割、店舗清掃・警備やクレジットカードなどで2割といった内訳だ。コンビニはミニストップ(売上高641億円、営業利益70億円)を抱えている。
一方のセブン&アイの年商(売上高)は4兆7000億円。営業利益のうち、コンビニ事業(セブン-イレブン)とそれに付随する金融事業が8割を占めている。スーパーはイトーヨーカ堂(売上高1兆3610億円、営業利益105億円)を抱えている(『Part1 セブン、イオン最高益の実相』)。イオンのほうが業績は好調だ。
ただし、時価総額(株価×発行済み株式数)で見ると、イオンとセブン&アイの立場は逆転する。セブン&アイの時価総額は2兆1478億円。イオンの時価総額は8357億円だ。この総額の差は、両社のコンビニ事業への株式市場の評価の差だという。つまり、セブン-イレブンは市場で高く評価され、イオンのミニストップはそれほどの評価がないということだ。このため、今後、コンビニ業界での再編はイオンのミニストップが起爆剤になって、スリーエフやローソンとの提携に動くのではないかという(『Part4 株式市場が促す流通再編』)。
セブン&アイが圧倒的優位に立つコンビニ事業はどうか。セブン-イレブンとそのほかの大手コンビニとの一日の店舗当たり平均販売額の差は、約12~13万と広がっている。この好調の要因は、プライベートブランド(PB)「セブンプレミアム」の売上だ。他社の追随を許さないPB「セブンプレミアム」の好調の理由は、セブン&アイグループで共通のPBとしたことだ。商品開発はセブン-イレブンだけでなく、イトーヨーカ堂、ヨークベニマルなどのバイヤー(社員)が、一つのチームとなって開発をすることになる。しかも、その製品はPB専用工場を有しており、比率は93%(他のコンビニは20~30%)。共通のPBなので、どのグループでも販売できるために在庫リスク、在庫ロスがないのだ。
「業態ごとに取り扱う商品や価格が異なるから難しい」とPB共通化に難色を示したグループ各社に「どの店に行っても顧客が喜んでくれる商品を開発すればいいのではないか」と説得した鈴木敏文会長の戦略が的中した。セブン-イレブンは、高齢者などの全国で600万人とされる買い物弱者を狙った宅配サービス「セブンミール」を始めるなど、今後にも注目が集まる。
ただ、同社の唯一ともいえる懸念材料は、鈴木会長の後継人事だ。鈴木会長は79歳。今号のダイヤモンドのインタビューに鈴木会長は「リーダーの条件は先見性とリーダーシップを持つ人物」としたものの、「具体的に誰ということではない。だが後継者には、私とは異なる発想を持った人のほうがよいのかもしれない」と語っている。企業モノが得意なダイヤモンドらしい大特集になっている。
入社4~5年目の社員が「新型うつ」を発症する!?
「週刊東洋経済 6/16号」の大特集は『人ごとではない うつ・不眠 ~予防・治療法&つき合い方』だ。厚生労働省は11年に、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の4大疾病に精神疾患を加え5大疾病とする方針を決めた。なかでも、うつ病は96年の20.7万人から08年には70.4万人に急増。なんらかの治療を受けているのは20%程度とされ、未治療者・未診断者を加えた患者数はもっと膨れ上がるという。
人間関係や過重労働による疲労、ストレスが蓄積しているために、従業員のメンタルヘルス対策は、重要な経営課題になりつつある。さらに「新型うつ」といった症状も話題になっている。こうした、メンタルヘルス問題の現状に迫った好企画だ。
うつの主な症状は「眠れない、食欲がない、一日中気分が落ち込んでいる。何をしても楽しめない状態が続く、これらが2週間に以上にわたる」場合はうつの可能性が高いという。この原因は景気後退による経済的な不安や、職場、家庭、人間関係などのストレスと長時間労働による過労が原因とされていて、精神疾患を原因とする労災の請求件数を見ると、98年には42件しかなかった申請が10年には1181件にまで増えて過去最高に。11年度も高水準の請求件数が見込まれており、3年連続で過去最高を更新する勢いだという。
記事によれば、この急増の背景には、うつ病の診断基準の解釈が広がってきていることがあるという。10年前ならばノイローゼや自律神経失調症といわれた症状も、現在はうつ病と診断されるようになった。またうつ病についての認識が広がり、病院で受診する機会が増えていることもある(『うつ 急増しているのはなぜ』)。
一方、最近、話題になってきた「新型うつ」は、勤務中だけうつ状態に入り、仕事を離れると普通の生活に戻ることができるという症状で、周囲からは怠け病としか思えない状況が続くが、精神科でうつ病との診断を受けるのだ。
話題の「新型うつ」は不安感が強いタイプ、気を使いすぎるタイプに多く、ゆとり教育世代や親からあまり怒られたことのない若者がなりやすい。ある中堅企業では、従来型の精神疾患を発症させた社員は減ってきているが、「新型うつ」の症状の若手が急増中、とくにリーマンショック前に入社した4~5年目の社員が発症させているという。入社後の長時間労働が原因なのか、因果関係が不明で対策がとりにくいのが現状だ。
「新型うつ」についても、「精神医学的に厳密な定義はない」のだという。このため、「新型うつ」というよりも人格が成長する過程において何かが欠落して止まっている未熟状態である「未熟型うつ」ではないか、自立しにくい社会環境の中で育ち、自立しようともがいている「病的自立症候群」と呼ぶべきではないかといった専門家の異論を掲載している(『問題視される新型うつ 治癒しにくいのが難点』)。
うつ病で深刻なのは、強いストレスにさらされる海外駐在員と家族たちだ。海外赴任といえば、かつては成功者のイメージだったが、現在は赤字の海外拠点はが削減されたりして、1人で何役もこなさざるを得なくなる。さらに中国などでは接待などで飲酒量が増える。中国人の部下に対しても。タフな交渉が必要になってくる。こうしたストレスから、さらに飲酒量が増えて、健康までも害してしまうのだ。専門家によれば、「海外だとストレス3倍、うつ病発症率は3倍以上」だというのだ。
とくに中国では、80年代生まれ、90年代生まれの若い世代は、中国人にとっても対応が難しいとされている。こうした世代を部下に持つことで、海外駐在員は大きなストレスにさらされるのだ。メンタルヘルス対策が万全の企業でも海外駐在員までサポートが回りきらない。
また、うつになった場合に治療薬の問題にも注意しておきたい。医師がよかれと思って処方した治療薬が、手の震えや、足腰の筋力低下、食欲の不振といった副作用を引き起こしてしまうことがあるのだという。医師の知識が十分でなく、症状のひとつひとつに異なった薬を処方し、多剤になり、副作用を引き起こしてしまう大量処方問題もある。
不適切な服薬を避けるための対策としては、病院と利害関係の深い”門前薬局”でなく、かかりつけの薬剤師を持ち、日ごろの服薬についてのアドバイスをもらうという薬のセカンドオピニオンが必要だという(『患者本位が求められる治療 第一選択の薬物治療で不適切な処方が問題に』)。
社会の変化に対して後手に回る医療……といった構図で、やはり、まずは自分で身を守っていくしかなさそうだ。社会問題が得意の東洋経済らしい好企画だ。
(文=松井克明/CFP)





















