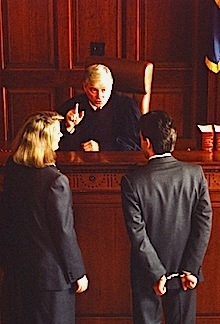 「Thinkstock」より
「Thinkstock」より前回も表向きは法律事務所だが、実際には弁護士は出勤もしていない違法な非弁提携事務所「B弁護士法人」と「C弁護士法人」。だが、法律に詳しくない依頼人には、そうした事情はわからず、かなり繁盛していたという。前回も証言してくれた元事務員A氏が語る。
「私が『B弁護士法人』や『C弁護士法人』の事務所にいた時の受任件数は、毎月100件とか150件が当たり前でした。その前に勤務していた大手の法律事務所では弁護士が12〜13人もいて、ひと月に200件程度でした。『B弁護士法人』の弁護士は2人、『C弁護士法人』の弁護士は1人ですから、明らかに過剰受任ですよね。私たち事務員も毎日、膨大な仕事に追われました」
松永弁護士も「無茶苦茶な数字。1人の弁護士だったら、1カ月30件の受任が限界。月に100件も依頼人が来たら、面談もこなせません」と言う。
過大な受任件数からは雑な仕事ぶりが想像できるが、問題はそれだけではない。「そもそも、通常の方法では、それだけ多くの依頼人を集めることは不可能」(同)なのだ。
では、「B弁護士法人」と「C弁護士法人」は、どうやって依頼人を集めているのか。
「お客さんを多く集められるのは、地方で行う無料相談会です。1日に十数人、借金問題の相談をする人がやってきて、ほぼ全員から受任を取り付けられるのです。弁護士も同席しますが、形式的なものに過ぎません」(A氏)
不可解なのは、全国津々浦々を回るのではなく、岐阜、仙台、長野など特定の箇所を巡回すること。そして、相談者のほとんどが借金を完済済みで、過払金を消費者金融から取り戻せるという、法律事務所にとって旨味の大きい同じ属性である。
消費者金融会社が顧客リストを流出?
実はA氏が回っていた巡業先は、大手消費者金融であるX社の「特大店」と呼ばれる大型店舗がある場所だった。そして、依頼人が同じ属性であることからは、同消費者金融の顧客リストの存在もうかがえる。
松永弁護士が解説する。
「法律事務所に依頼人を斡旋する『紹介屋』という人たちがいますが、弁護士法上、紹介屋も弁護士も罰せられる違法行為です。また、消費者金融側の人間が顧客リストを流出させているとしたら、業務上横領罪などに問われる可能性もあるでしょう」
「B弁護士法人」と「C弁護士法人」の事務所が行う無料相談会に訪れる依頼人は、皆、「チラシを見て来た」と口を揃えるという。通常、法律事務所はチラシなどの広告は広告代理店に出稿するものだが、「B弁護士法人」と「C弁護士法人」は、D社という広告代理店と関わりが深かった。
「私は『C弁護士法人』に移籍した後、同事務所の幹部から『オーナーサイドと懇親会がある』と言われて、D社のK社長と会い、接待をしたことがあります」(A氏)
実は、松永弁護士も、かつてそのD社に広告を出稿していたが、D社側から違法な非弁提携を持ちかけられた経緯があった。松永弁護士はその誘いを断ったが、その後、発注額の5倍という不当に過大な広告料金を請求され、松永弁護士がこれを突っぱねたために、D社から訴訟を起こされていた。
紹介者組織の陰
訴訟ではD社が非弁行為を行っているかどうかも争点となった。松永弁護士は証拠となるD社の内部資料を法廷に提出したが、一審、控訴審で松永弁護士が敗訴。現在、上告の準備をしているという。
同弁護士が言う。
「私がかつてD社に広告を依頼していたときのことを思い出すと、依頼人が『ポストにチラシが入っていたので、先生のところに連絡をしました』と、聞いてもいないのに妙なストーリーを話し始めたりするんです。また、D社にチラシ配布を依頼していない地域からの依頼人が来たこともありました。さらに、依頼人の内縁の夫を名乗る人物から電話がかかってきて、『赤坂の紹介屋から、おたくを紹介してもらったが、過払金を取り返せると言われたのに、武富士が倒産して戻ってこなくなった。弁償をしてほしい』と言うのです。私は『赤坂の紹介屋』なんて知りません。『誰ですか?』と私が聞くと、その人は『迷惑がかかるから、言えない』と言い、それで電話が切られてしまいました」
D社はテレビCMを流したり、海外に支店を持つほどの広告代理店だ。だが、それは表向きの姿に過ぎず、実態は広告代理店の体裁を借りた紹介屋組織なのではないか、という疑惑が浮上する。
D社にはE社という子会社がある。E社は弁護士、司法書士事務所の人材派遣、開業支援を業務としているが、かつてD社がE社を設立する前にD社自身が開業支援に関与した、Fという弁護士の法律事務所の「収支明細書」がある。それによれば、平成20年度、F弁護士が債務整理事件を受任して得た、毎月の成功報酬の総額は1億1700万円余りとなっているが、それと同額がそっくりそのまま「外注費」として差し引かれていた。
また、E社が開業支援した弁護士法人の収益モデルを示した別の内部資料では、弁護士法人の収益のうちE社が業績連動として20%を得ることになっていた。仮にこうした事実があったとしたら、弁護士法違反の非弁行為ということになるが、松永弁護士との訴訟では、D社側は、これらの証拠が示す事実に対して、「途中で計画は中止になった」と説明しているという。
弁護士会は不正行為に優しい
こうした疑惑以上に心配なのは、D社と関係の深い法律事務所が、消費者金融から取り戻した過払金や依頼人からの預かり金を適正に処理しているかどうか、ということだ。
過去、非弁提携事務所が事件化したケースでは、多くの場合、整理屋が依頼人のお金に手を付けていて、返還されずに、弁護士が破産している。
A氏によれば、「事務所にお金が入ると、すぐに事務長が代表を務めるコンサルティング会社に資金が移動されていました」という。一体、どういう経理をしているのであろうか。
「B弁護士法人」と「C弁護士法人」の双方の事務長、事務局長を務める人物は、「依頼人と会ったり、消費者金融と交渉をする際、偽名を名乗っていた」(A氏)という。まともなことをしているとは到底思えないのである。
弁護士の問題というのは、暴力団が関わっているぐらいの悪質な業務をでなければ、行政が介入することはまれで、通常、弁護士会の自治に委ねられている。弁護士会は非行弁護士に対して懲戒をすることもできるが、非弁提携には及び腰だ。
A氏が言う。
「弁護士会というのは、優しいんです。弁護士が依頼人に一切面談していないような不正行為に対しても、1〜2人が懲戒請求をしたところで戒告止まり。数十人が一斉に懲戒請求するぐらいでなければ、業務停止命令までは出ません」
松永弁護士も「D社の問題については、弁護士会にすでに報告していますが、いくら待っても何の音沙汰もありません」と言う。
非行弁護士、整理屋が放置され続けた結果、問題は深刻化の度合いを深めているようだ。
「弁護士会の雑誌などには、100や200は非弁提携事務所があるなどと書かれています。私も債務整理を扱う前は、何割かの法律事務所はおかしなところもあるだろうと思っていました。しかし、今の私の実感では、非弁提携事務所は1000ぐらいあってもおかしくないなというのが正直なところです。広告を出しているところの9割はおかしなところ、本当にまともな事務所は数パーセントに過ぎないのではないかとさえ思うのです」(松永弁護士)
D社と関係が深いとされる法律事務所は10以上あるとされ、規模はかなり大きい。D社、そして関係する法律事務所で、一体、何が起きているのだろうか。実態解明が待たれる。
(文=星野陽平)





















