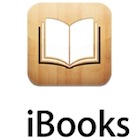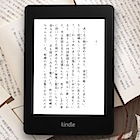koboの戦略について語る三木谷・楽天社長。(8月5日付日経新聞より)
koboの戦略について語る三木谷・楽天社長。(8月5日付日経新聞より)さまざまなテレビ番組や雑誌などでもお馴染みの購買/調達コンサルタント・坂口孝則。いま、大手中小問わず企業から引く手あまたのコスト削減のプロが、アイドル、牛丼から最新の企業動向まで、硬軟問わずあの「儲けのカラクリ」を暴露! そこにはある共通点が見えてくる!?
電子書籍の実力
これまで21冊の本を出した。そのうち何冊かを出版社のサイトから電子書籍にして発売した。
『1円家電のカラクリ 0円・iPhoneの正体」(幻冬舎新書)を出したとき、「ラインナップの中で、1カ月で最も売れた」と言われた。その数、90ダウンロードだった。約1万円が私に振り込まれた。
私は正直、「やはり、こんなもんか」と思った。つい数カ月前のことだ。
私は幻冬舎の販売力に問題があったとはまったく思わない。むしろ、よく売れたほうだと思う。紙の書籍は初版1万2000部を刷っていた。そのころ電子書籍がすべてを変えるといわれていた。しかし、実際のところ、書き手からすると、それほど世の中を変えそうに思えない。
もちろん、電子書籍で多数のダウンロードを誇るものもある。電子書籍の話題になるとき、例外的に売れたものばかりが注目される。ただ、その他大勢はどうなのか。売れた本は常に語られ、売れなかった本は常に語られない。そして、幻想だけが流布していく。
電子書籍化のコストはさまざまだ。
電子書籍を販売している出版社をヒアリングすると、おおむね200~300冊を損益分岐点(赤字と黒字の境界)と設定しているところが多い。ということは、1年程度をかけてゆるやかに損益分岐点を突破すればよいのだろう。それにしてもこの数字、ほんとうに世の中を変えるモンスターなのか、私にはわからない。
考えてみるに、デバイスが増えたからといって、読者人口が増えるわけではない。もしかすると、ためしに面白がって電子書籍を購入する新読者層もいるかもしれないけれど、彼らが継続して電子書籍を購入するかどうかは怪しい。電車に乗ったとき、みんなが見ているのは、文庫本・新書・スマホ(Facebook)・スマホ(メールチェック)・スマホ(Twitter)だろう。電子書籍を読んでいる例を私はほとんど知らない。
マンガ家の井上雄彦さんが語るように、マンガであれば電子タブレットに特有の新表現がありうるのかもしれない。動きや音を使い、そしてネットワークとつながれば、新たなマンガが登場しうる可能性は想像に難くない。しかし、いわゆる活字本については、図が少し動くくらいで、電子でなければいけない優位性を見つけるに至っていない。
電子リーダーあれこれ
という私も、電子リーダーは多くを購入してきた。電子書籍が読めるものとして、PCは当然として、iPhone、iPad、Kindle(アメリカで買った)……。そして、先日はkoboも購入してみた。説明するまでもなく、koboとは楽天が肝いりで発売した電子リーダーだ。
私は、「活字本については、図が少し動くくらいで、電子でなければいけない優位性を見つけるに至っていない」と書いたものの、一つの可能性はあると考えてきた。
それは、重さからの解放だ。
職業柄、さまざまな雑誌を読むけれど、女性誌は一つの文化批評として楽しんできた。ただ、女性誌は重すぎる。「VOGUE JAPAN」は眺めるだけで刺激的だけれど、腕が折れそうになる。「Mart」は女性一人ひとりがクリエイティブなことを知らしめる革命誌だけれど、しばらく持つと手がしびれる。その他、あれほど重い女性ファッション誌を軽々と持ち上げる女性たちに、私は勝てないと思った。
なるほど、女性の社会進出とパワーは、なでしこジャパンの活躍を見るまでもなく、女性誌の重さが証明していたのである(ちなみに、相当数の年配女性は、女性ファッション誌が重すぎて持ち帰るのを躊躇し、購入に至らないのではないかと思うけれど、もしかすると重さによって一つのハードルを課しているのかもしれない)。
まあ、それはいい。
物理的な重さから解放されれば、少なくとも私は電子リーダーで女性ファッション誌を読む。事実、iPadのアプリで海外の女性ファッション誌を読んでいる。Kindleでも多くの雑誌が買える。
そしてkoboの登場だ。講談社と蜜月であるkoboちゃんならば、きっと多くの雑誌が購入できるはずだ!
と思ったら、雑誌は買えないでやんの。
調べなかった私も悪いけれど、koboちゃんは「定期購読」できると聞いていたのであれこれ操作したけれど、どうやってもわからない。書籍も、ベストセラーのものは並んでいるけれど、とりたてて買いたいものもない。
重たい専門書も買えないとは…
重さ、という意味では、ぶ厚い専門書をいくつか調べたけれど、そのほとんどが売っていなかった。なんなのだろう。
ちなみに私は電子書籍の可能性として
・電子ゆえの新たな表現を志向しているもの、あるいは電子オリジナルのコンテンツ(マンガ等での新表現、または電子上のみで読める作家の新刊)
・重さから解放してくれるもの(ファッション誌、専門書)
を挙げた。
特に2点目の専門書は、もう一つの利点もある。専門書類を読んでいるとき、用語で検索するときがある。これまでは巻末の索引に頼っていたけれど、これが電子ゆえに一瞬で検索できることは大きい(なぜ、専門書出版社は、この利点を強調しないのだろう)。学習者や研究者の時間は大幅に浮くはずだ。
残念ながらkoboちゃんはいまのところ、「紙で読めるコンテンツの一部を電子でも読めますよ」程度にとどまっている。
とはいえ、7980円という低価格から思うに、koboちゃんはそれほど批判するにあたらない。書籍を読めないことはないし、日々コンテンツが増えているのも事実。おもちゃとして愉しむことができる。日本発の電子リーダーとして今後の展開に期待したい。
Kindleの日本上陸?
楽天がkoboちゃんの発売を急いだのは、AmazonのKindleの日本上陸以前に先手を打ちたかったからだろう。しかし、AmazonはKindleをまもなく発売するとしながら、数カ月のあいだ手間取っている。日本では、著者が著作権を持ち、出版社に書籍として複製する許可を与えている。電子書籍として電子データを読者に送信する権利は著者にあり続けているから、出版社の意思だけでAmazonと契約することができない。
Amazonが著者一人ひとりと契約を結ぶことは考えにくい。不可能ではないけれど、現実的には数十万人いるとされる著者たちと契約を結ぶよりも、出版社を抱き込む形でKindleサービスを開始せざるをえない。もっともそれは各社とも同じ。楽天koboちゃんは、出版社経由で著者に確認をする手間を重ねているから、楽天の目標としていたラインナップ数6万冊を揃えるまで相当な時間がかかるだろう。
koboちゃんは、先行者利益を確保することができるのだろうか?
本家のように30年愛されるかどうか。
わざとらしいけれど、楽天とkoboちゃんの検討を祈る。