楽天、三木谷一極集中の死角~不当表示問題、疲弊する出店者、収益の柱は金融に
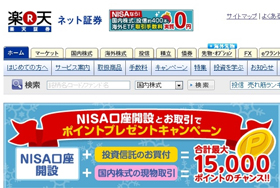 楽天証券 HPより
楽天証券 HPより
特集記事『ネット通販 楽天市場に変調』では、二重価格問題を取り上げる。保有する球団・東北楽天ゴールデンイーグルスがパリーグ優勝、日本一となり、それぞれのタイミングで緊急セールを開催。今年9月の流通総額(商品取扱高)は前年同月比42%増の1426億円を記録した。しかし、11月の「星野監督の背番号77にちなんだ、通常価格から77%引き」の楽天日本一セールは、後味の悪い結果となった。
景品表示法では、過去8週間以内に4週間以上販売した実績がないと通常販売価格と打ち出せない。しかし、日本一セールで初めて商品を出品した業者が「通常販売価格1万2000円の77%引き」と掲げながら、実際には1万2000円で販売した実績はなく、不当な二重価格表示だとされた問題だ。
「そもそも77%オフが無理な設定だった。うちでもサンプル商品か廃番商品でないと出品できなかった」(6年前からスポーツ衣料品店を出店する社長・同記事)
今の楽天にとって、定期的なセールは流通総額拡大にとって欠かせない戦術となっているが、出店者からは「やりすぎ」や疲労感を訴える声が上がる。
楽天の2012年の年間流通総額は1兆4460億円とヤフーのヤフーショッピングの約5倍、アマゾンジャパンの約2倍(売上高基準)の規模を誇る。過去12年間で約28倍の成長を遂げたが、その背後には出店者の大きな負担があるのだ。
●三木谷会長に一極集中のピラミッド構成
特集記事『三木谷王国の全貌』では、グループ1万人を背負う、三木谷浩史代表取締役会長兼社長を頂点とした経営陣を解説している。
「手掛けるサービスが多岐にわたるためか取締役は15名と、競合のヤフー(5名)、LINE(3名)に比べ多い。各取締役の出身母体は三木谷氏と同じ銀行に加え、トヨタ自動車やリクルート、NTTなどが目立つ。運営体制は三木谷氏への一極集中で典型的なトップダウン型だ」(同記事)
特集記事『ヤフー決死の反撃!』では、「出店初期費用、月額費用、売上高手数料はいっさいもらいません」と10月7日にヤフーが発表したネット通販事業・ヤフーショッピングの無料化戦略の狙いを解説している。
「手数料収入をゼロにすると言ったヤフーだが、儲けないとは言っていない。売り手の数と集客力を引き上げることに集中。人の集うところに広告が出る、広告が販売を伸ばし売り手がさらに増える、という循環を形成し、中心にいるヤフーは広告料でしっかり稼ぐという算段だ」(同記事)
●金融事業にシフトしつつ多角化
今回、知っておきたいのは、楽天とヤフーショッピングのビジネスモデルの違いだ。ヤフーのビジネスモデルは広告等であるのに対し、楽天の収益の中心は楽天市場ではなく、カードや銀行、証券といった金融事業が前年比で2倍に増えており、最新業績(2013年7~9月期)ではグループ営業利益の4割強をたたき出した。楽天証券は株高の恩恵を受けて、証券手数料収入が急伸中だ。ネット証券ではSBI証券の35%に続く15.3%で第2位のシェア占有率を占めている。11月からは、ついに住宅ローンの自行融資も始めるなど、金融事業を中心とした企業になりつつあるのだ(特集記事『多角化する楽天の金融』)。
ライバル誌の「週刊ダイヤモンド」(ダイヤモンド社/12月7日号)も、特集『激烈! 流通最終決戦』の記事『楽天、アマゾンへ切り札投入 ヤフーEC革命の正体』において、楽天とヤフーのビジネスモデルの違いに迫っている。ダイヤモンドの特集記事では「楽天はヤフーの無料化策に打撃を受けていない」という。楽天は店舗と密着した体制を組んでいるからだ。
「楽天の強みは何といっても、全国15拠点にECコンサルタント約500人がいることである。『店舗の流通総額を上げる』というミッションを負い、店舗と知恵を出し合い互いに成長しようという応援団がいるのだ」(同記事)
「地方支社を増やし、実際に店舗の人と会う『面着率』を高めている。外資系の戦略コンサルタントのような人材を擁する集団にしたい」(楽天の執行役員・同記事)
広告で儲けるヤフーと、インターネット金融で稼ぐ楽天、物流・ITシステムへの投資に余念がないアマゾン。競合3社にまだまだ成長余地があるが、その分、リアル店舗の市場が落ち込んでいく一方なのかもしれない。
(文=松井克明/CFP)















