年収78億円、なぜDJに高額報酬が払われる?今も未来も「編集の時代」である
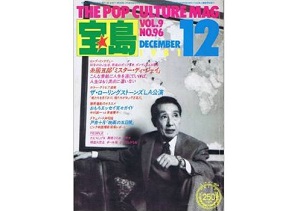 糸居五郎(「宝島」<宝島社/1981年12月号>より)
糸居五郎(「宝島」<宝島社/1981年12月号>より)糸居五郎のDJ時代
唐突な質問ですが、世界トップクラスのDJの年収をご存じでしょうか? そう、ディージェイ、ディスクジョッキーの年収です。「知ってるよ」とおっしゃる方は、前半は飛ばして後半からお読みくださっても結構です。知らないという方は、彼らの年収を知る前にここ数十年のDJの歴史をたどることにしましょう。DJの年収と歴史を考えることで、ちょっとした未来のヒントが見えてきます。
DJとは、専用の機材を使ってさまざまな楽曲や音源を組み合わせ、客層や雰囲気に合わせて選んだ曲を流しながら来場客を楽しませる職業です。東京なら渋谷近辺、地方なら中核都市にあるクラブや屋外レイブ(DJによる屋外でのダンスイベント)に行けば、彼らのプレイに接することができます。
 『無印良品の「あれ」は決して安くないのに なぜ飛ぶように売れるのか?』(江上隆夫/SBクリエイティブ)
『無印良品の「あれ」は決して安くないのに なぜ飛ぶように売れるのか?』(江上隆夫/SBクリエイティブ)50代以上であれば、DJというと1960~70年代にかけて深夜のラジオ番組で最新の楽曲を紹介していた糸居五郎さんや亀渕昭信さん(お二人ともニッポン放送の番組『オールナイトニッポン』のアナウンサーでした)、あるいは当時いたる所にあった「ロック喫茶」のレコード用ブースで選曲をする人を思い出すかもしれません。
音楽系出版社ロッキング・オン創業者、渋谷陽一さんも売れない評論家時代に、新宿でDJのアルバイトをやっていました。筆者の印象では、この時代のDJとは「選曲者」にほかなりません。
選曲者からプレイヤーへ
しかし、80~90年代にかけて「DJ=選曲者」の印象が大きく変わっていきます。70年代にヒップホップDJが出現し、スクラッチ(アナログレコードの特定部分を反復したり、回転を変えたりする技法)や2台のターンテーブルを使って観客を楽しませる音楽手法が生まれたからです。
彼らはほかのアーティストが創った音楽をただの音素材とし、ターンテーブルの使い方を変えることで別の音楽を奏でたのです。「音楽を再生するデバイスを楽器にしてしまい」さらに「他人が創った音楽から別の音楽を引き出す」というコペルニクス的転回を起こしたのです。いま思えば、現代美術のマルセル・デュシャンに負けず劣らずの、ポピュラーミュージックの革命でした。
これ以降、裏方だったはずのDJが、さまざまなコンサートに「プレイヤー」としてメインの出演者とともに出てくるようになります。彼らのDJプレイは音楽としても新しく、今までにない新鮮な響きを持っていました。
今の20~30代の方には当たり前かもしれませんが、12歳くらいから洋楽(今はこんな言葉もあまり使わなくなりました)を聴き続けてきた筆者にとって、「他人がつくった音源や曲を流して」「そこに変化を加える」ことが「オリジナルの音楽行為」として認知されていくことは本当に衝撃でした。他人の曲にタダ乗りじゃないか、オリジナル性はどこにあるんだ、と。ただ、いろいろな音楽をプレイと称して「編集」しているだけではないかと。しかし、時代は彼らにGOサインを出します。
世界的DJの驚異的年収
そのGOサインは「年収=世の中から求められている量」に明確に現れています。米経済誌「フォーブス」が14年8月19日に「Electronic Cash Kings 2014」として世界的DJの年収ランキングを公開しています(http://www.forbes.com/electronic-cash-kings/)。
1位は31歳の英国人カルビン・ハリス。額は6600万ドルで約78億円(以下、すべて1ドル119円換算)です。2015年3月時点における国内上場企業役員報酬の最高額は12億9千万円であり、5倍以上の開きがあります。2位は47歳のフランス人デヴィッド・ゲッタの3000万ドル(約35億円)。10位のデッドマウスでも1600万ドル(約19億円)です。
ポピュラーミュージックの歴史は、1920年代から始まる蓄音器普及の歴史と重なります。ポピュラーであるためには、みんなに共有されるための「デバイス」が必要だったからです。みんなに共有され、とことん味わいつくされて初めてポピュラーたり得ます。それゆえポピュラーミュージックは、先行した音楽のすぐれた部分を反復、拡大再生産しながら、もしくは批評的に変えていくことで発展してきました。ほとんどの音楽家が例外なく、好きな曲をコピーし、真似るところから自分のキャリアを始めることからも、そのことがわかります。ポピュラーミュージックの核心には「既存のものの組み合わせ」原理があります。
その歴史もそろそろ100年。無数のメロディ、ハーモニー、リズムが溶けあって新しい音楽として現れてはいますが、人間が快適に聴けるメロディなどは、この100年である程度出つくした感があります。この状況の延長線上にDJたちが存在する、と考えると現在の状況がよくわかります。
続く「編集の時代」
では、世界はなぜこの高額の報酬を彼らに与えているのでしょうか? ひとことで言い表すなら、今も未来も、しばらくは「編集の時代」だからです。毎年、世界中で数限りない新曲と新人歌手が現れますが、結局はメロディ、ハーモニー、リズム、歌詞、服装、演出の組み合わせ、つまり「編集のセンス」によってヒットするかどうかが決まっています。DJとは音楽における「編集のセンス」の代名詞なのです。
勘のいい人はもうお気づきでしょうが、この「編集の時代」は何も音楽に限ったことではありません。米アップル創業者のスティーブ・ジョブズも、日常的な製品における「編集の王」でした。iPhoneが、既存技術の徹底的な洗練された組み合わせによって造られていることは周知の事実です。ウェブビジネスはそれこそ何と何を組み合わせるかの「編集」センス如何によって、成功するかどうかが決まります。
あなたが「編集」すべき対象は何でしょうか?
一度、身のまわりを「編集」の視点で丁寧に見てみてください。ビジネスの種や未来のヒントが転がっているはずです。
ちなみに、今年のポール・マッカートニー『OUT THERE JAPAN TOUR 2015』のオープニングアクトは、DJによるビートルズやウィングスナンバーのプレイでした。
(文=江上隆夫/ブランド戦略ディレクター





















