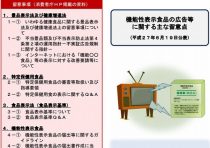病気がイヤなら医療を疑え!飛躍的に医療進歩でもなぜ、がん・糖尿病・脳梗塞患者は激増?
 「Thinkstock」より
「Thinkstock」より日本の医療が混迷を深めている。毎年、40兆円もの医療費を費消しながらも、病気にかかる人の数は一向に減る気配がない。ちなみに40兆円という金額は、今年経済破綻の危機に見舞われたギリシャの政府債務に匹敵する。また、1兆円というお金は、わかりやすくいえば、縄文時代から毎日(毎年ではない!)100万円ずつ約3000年間使い続けてやっと達成できる数字である。まさに天文学的な金額である。
1975年のがん死者数は約13万人、医師数も約13万人であった。その後の40年間で、医師数は約31万人と2倍以上に増え、がんに対する研究や治療法が格段に進歩したとされるのに、昨年のがん死者数は36万人を超えている。また、官民あげてがん対策に取り組んでいるのに、今や2人に1人ががんにかかり、3人に1人ががんで死亡するという惨状である。
一般の人も潜在意識下に西洋医学や医療に対する不信を抱いているのか、「がんは何も治療しないのが一番長生きする」と主張する元慶応義塾大学講師の近藤誠医師が著した『医者に殺されない47の心得』(アスコム)という、度胆を抜くようなタイトルの本が、120万部ものベストセラーになっている。
医療の常識は正しいのか?
糖尿病に対しては、「糖質制限」「ローカーボ(低炭水化物)ダイエット」「米は食べるな」「小麦は食べるな」「炭水化物が人類を滅ぼす」などと謳う本が多数出版され、糖質や炭水化物(多糖類)の摂取を極力しない食事法がブームになっている。
しかし、戦後約60年前に比べて、炭水化物である米の摂取量は約2分の1に、芋の摂取量は10分の1に激減しているのに、糖尿病患者(予備軍も含めて)は約2200万人に激増している。ちなみに約60年前のそれはたった数百人だったとされる。
1950年頃の日本人の塩分摂取量は、鹿児島で1人1日平均14g、北に行くほど多くなり、秋田や青森では同28gであった。当時、秋田や青森の人々は高血圧の疾患や脳出血で死亡する人が多かったので、その後、東北地方から始まり日本全国に減塩運動が展開され、現在では一日の食塩量は10g未満にするように厚生労働省より指導されている。
にもかかわらず、高血圧の患者数は一向に減る気配はなく、6000万人ほどいると推計されている。
心筋梗塞や脳梗塞などの血栓症予防のために、血液をサラサラにするべく、「水をこまめにとれ」「1日2l(リットル)以上の水分をとるように」などと指導されるようになったのは、ここ20年くらいである。それまで、「水を飲め」などという健康法は日本にはほとんどなく、我々の少年時代は、炎天下で草野球やサッカーの試合をしている途中で喉が乾いて水を飲もうとすると、「試合中は水を飲むな! 力が出なくなる」などと監督から叱られたものだ。
血液をサラサラにするために水を多く飲むように指導され始めてから今日までの約20年間で、脳梗塞(脳出血ではない)や心筋梗塞などの血栓症は、減るどころか着実に増加している。
こうしたいくつかの事象を鑑みても、どうも医療常識には疑う点が多々あることが推測できる。
毎年40兆円以上の医療費が費やされているにもかかわらず、国民の健康が改善している気配はない。年間数百万人が受ける人間ドックで、まったく「異常なし」の人は7%しかいないというのだから、この数字こそ「異常」である。
このままいくと、日本人と日本は、病気と医療費で衰退する。
こうした点をふまえて今後本連載では、「病気にならないための生き方」について述べていきたいと思う。よろしくお願いします。
(文=石原結實/イシハラクリニック院長、医学博士)