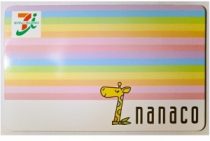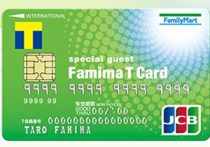ストレイトスカード「ストレイトス 公式サイト」より
ストレイトスカード「ストレイトス 公式サイト」より不思議なことに50年、100年スパンで見ると未来への大きな流れは変わりません。しかし、その流れの過程では、小さく渦巻いたり、突然支流が生じたり、停滞したり、一筋縄ではいきません。広告やブランドという常に半歩先、一歩先を見る仕事を長年続け、コンセプト関連の著作もあるブランド戦略ディレクターの江上隆夫氏が、自身のアンテナに引っかかってくる未来の種を「短期、長期の本質的な視点」を織り交ぜながら解説します。
お金が持つ3つの機能とは?
人がつくる制度は、年月を経て少しずつ変わっていくものです。例えば政治を見ると、日本は江戸時代の中央集権的な幕藩体制から、明治時代の立憲体制、参政権の拡大を経て、昭和に入ると第二次世界大戦後の民主主義体制へと変貌を遂げました。
制度のひとつであるお金も、同様に大きく変化してきました。お金は、ある意味で私たちが最も頻繁に活用する制度といえるでしょう。そのため、私たちは変化によって大きな影響を受けます。
お金の専門家でもなく、ただの生活者である私が、お金の未来に以前から関心を寄せてきたのはなぜでしょうか。それは「お金の変化は、政治や世界情勢の変化以上に大きなインパクトを社会にもたらす」と、心のどこかで確信しているからです。
お金という制度がどう変わるかを見る前に、お金にはどのような働き、つまり機能があるのかを考えてみましょう。お金の基本的な機能には、以下の3つがあります。
 『無印良品の「あれ」は決して安くないのに なぜ飛ぶように売れるのか?』(江上隆夫/SBクリエイティブ)
『無印良品の「あれ」は決して安くないのに なぜ飛ぶように売れるのか?』(江上隆夫/SBクリエイティブ)ひとつ目は「価値交換のための手段」、つまり「支払うための手段」ということです。
欲しいモノやサービスを受け取るために、その価値にふさわしい量のお金を差し出す必要があります。物々交換もないわけではありませんが、今の時代は世界中のほとんどのモノやサービスはお金と交換され、人から人へ所有者が移っていきます。
2つ目は、「価値を測る」機能です。
つまり、すべてのモノやサービスの価値を、単一の尺度として測ることができるということです。土地、飛行機、ビルからミネラルウォーター、クリップ、消しゴム、あるいは大根やお米まで、すべてがお金によって相対的に価値を測ることができます。
世界中のあらゆるモノやサービスの価値が比較可能という点において、お金は唯一の尺度といってもいいでしょう。
そして、3つ目が「価値を保存する」機能です。
簡単にいえば、貯蓄です。銀行にお金を預けるという行為は、あなたが働いたりして得た価値を保存するということにほかなりません(銀行預金の利子については、ここでは不問とします)。
逆に考えると、価値の「交換」「測定」「保存」の機能があれば、お金の代替品となり得るわけです。
ポイントは「企業内地域通貨」である
一口に「お金」といっても、今は実に多様なかたちで存在しています。
例えば、航空会社にマイレージポイントがあります。ほぼ全世界の大手航空会社が採用しているサービスです。私も出張が多いため、ある航空会社のマイレージがかなり貯まっています。
このマイレージは、一種のお金と呼んでも差し支えないと思います。なぜなら、完全ではありませんが、前述した3つの機能を持っているからです。
まず、会社によって規定はありますが、マイレージは関連した商品やサービスと交換、つまり買うことができます。そして各商品・サービスに定められたマイレージの数によって(かなり限定された範囲ではありますが)価値の測定も可能です。
さらに、交換期限の有無もそれぞれですが、マイレージを使用しないということで、価値の保存もできます。
これは、航空会社という企業内における地域通貨といってもいいでしょう。そのため、顧客が保有するマイレージは、航空会社にとっていわば負債に当たるわけです。銀行の取り付け騒ぎのように、顧客が一斉にマイレージを商品やサービスの交換に充てようとしたら、航空会社はかなり慌てるのではないでしょうか。
今は、多くの人がさまざまなカードを持ち、それに付随するポイントを持っていると思います。それぞれの価値は小さくても、そこにはお金が循環するような経済圏が生まれているのです。
たくさんの電子マネーも、ネットワーク社会の中でお金の変化を促しています。
例えば、交通系の電子マネーがあります。首都圏なら「PASMO」や「Suica」、関西圏なら「ICOCA」や「PiTaPa」などです。一部で使えない路線もありますが、相互に利用可能なケースが多いため、1枚持っていればほぼ全国で利用できます。
また、「楽天Edy」やNTTドコモの「iD」、セブン-イレブンの「nanaco」など、商業系の電子マネーも普及しています。使用できる店舗に限りはありますが、レジでカードをタッチするだけで支払いが済み、ポイントもつきます。そのため、コンビニエンスストアなどでは、あまり現金で買い物をしないという人も少なくないでしょう。「お金=カード」になりつつあります。
サービスと利便性という両面で、お金は姿を変えています。
カードすらいらない未来のショッピング
では、お金の進化はどこを目指しているのでしょうか。
私が考えるひとつのシーンは、「カードのない未来」です。ただ、その前に「1枚のカードにすべてをまとめる」時代がやってくるとは思いますが……。
あなたは、財布の中のカードの多さにうんざりしたことはありませんか? 正直、私は面倒で仕方がありません。
今、自分の財布の中にあるカードを調べてみると、銀行のキャッシュカード2枚、クレジットカード5枚、会員カード2枚、鉄道系カード2枚の計11枚がありました。
このほか、いつも携帯している手帳には、9枚のカードが入っています。こちらはキャッシュカード3枚、クレジットカード1枚、会員カード3枚、健康保険証1枚、診察券1枚でした。
つまり、20枚のカードをほぼ常時携帯していることになります。そのうち半分ぐらいは仕事上持たざるを得ないもので、可能であれば大幅に減らしたいのが正直なところです。
日本クレジット協会によると、2014年3月1日時点での国内265社の発行枚数合計は2億6722万枚です。20歳以上の総人口1億475万人で割ると、成人1人当たり2.55枚のクレジットカードを持っていることになります。
いずれにしても、会員証や保険証などを入れると、少なくても6~7枚のカードを所有している人がほとんどではないでしょうか。
今、こうしたカードを1枚にまとめるサービスが始まっています。5月にサービスを開始したのが、アメリカのカード型ウォレット「ストレイトス」です。
ストレイトスが便利なのは、磁気ストライプのあるカードなら、クレジットや銀行のカードだけでなく、会員証やドアキーまで、すべてカードリーダーで読み込んでまとめることができる点です。
同じようにクレジットカードを8枚まで読み込んで自由に使える「Coin」というサービスもあります。しかし、こちらはまだ開発中であり、ストレイトスが大きくリードしているといっていいでしょう。
よく考えると、カードはお金をやり取りする際の本人認証の手段でしかありません。本人認証さえできれば、カードでなくても問題はないわけです。
そう考えると、いずれは高度化した生体認証がカードに取って代わる時代が来ることが予想できます。指紋、声、静脈、虹彩などを本人の認証に使うことができれば、カードは不要になります。
これには、生体情報の扱いやプライバシー保護の問題、膨大なインフラやセキュリティの問題があります。しかし、何も持たずにショッピングできる時代が、そう遠くない未来にやってくるのではないでしょうか。
指を差し出し、目を見開けば、モノが買えてサービスが受けられる時代。これが素晴らしい未来なのかどうかは、わかりません。ある意味、すべてが管理され監視されている、ジョージ・オーウェルの描くディストピアのようなにおいもするからです。
さまざまなカードは、お金の「価値を『交換』する機能」を外部化したものです。いわば、お金の出先機関や支社のようなものです。もともと、クレジットカードは現金がない時の代替手段として、小切手の後に登場したものですが、いずれにしても、お金がデータ化され処理される流れは、これからも変わりません。
物体としてのお金は、次第に我々の身の回りから姿を消していくでしょう。お金は、モノとしては「透明化」の道をたどっているからです。
(文=江上隆夫/ブランド戦略ディレクター)