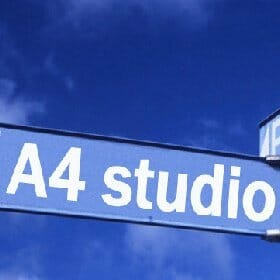ポケモンGOとコカ・コーラは、なぜ「異例」?レーシック手術とたまごっち、なぜ衰退?
 アトランタのワールド・オブ・コカ・コーラ(「Wikipedia」より/Melizabethi123)
アトランタのワールド・オブ・コカ・コーラ(「Wikipedia」より/Melizabethi123)本連載では前回、前々回とマーケティングにおける「Product」(製品)について解説してきたが、今回はそれら製品の「ライフサイクル」について、立教大学経営学部教授の有馬賢治氏が解説する。
「製品ライフサイクル」は人間の一生に似ている
――せっかく生み出した製品でも、気がついたら市場からなくなっていることはよくあります。これはなぜでしょうか。
有馬賢治氏(以下、有馬) 各製品にはそれぞれ、マーケティング理論でいうところの「製品ライフサイクル」というものがあります。その製品が市場に売り出されて、販売実績を伸ばし、やがて廃れていく様子を生物の一生に当てはめた理論です。この前提には、製品の売上は時間とともに増減し、製品の寿命は限られている、という考え方があります。
――製品ライフサイクルは、どのような段階を経て進んでいきますか。
有馬 製品が市場に導入されて販売が開始された時点から徐々に販売数が伸びていく期間を「導入期」、製品が市場に受け入れられて定着に向かっていく期間を「成長期」、製品が市場の潜在的購入者の多くに浸透する期間を「成熟期」、徐々に市場からなくなっていく期間を「衰退期」と呼び、この4段階に分類されています。人間でいうところの「幼児期」「青年期」「壮年期」「老年期」の分類に似ていますね。
――その段階によって利益幅も変化していくということですね。
有馬 はい。「導入期」はそれまでの開発費や市場導入にあたっての広告費など多額の費用が発生するため、利益が出ないことも多いです。今でいうところのVR(仮想現実)端末などですね。火を使わない次世代タバコ「IQOS(アイコス)」などのように、世間から認知されて急速に普及しはじめると「成長期」に入ったといえます。この期間は大幅な利益が期待できます。現在のスマートフォン(スマホ)や多くの家電のように「成熟期」となると、他社との競争が激化して値引きの必要性にも迫られてくるので、利益はある程度頭打ちとなります。そして、従来型電話、いわゆるガラケーのように製品の売上と利益がともに減少していく「衰退期」へと向かいます。
“忘れられる”ことを防ぐ
――製品寿命があることが前提とのことですが、コカ・コーラなどのように世界中で一向に「衰退期」が見えない製品もあります。
有馬 長期間売れ続ける製品をつくるのは難しいですが、製品ライフサイクルをできる限り引き延ばすことは可能です。例えば、自動車でしたらマイナーチェンジを行い製品自体に魅力を付与します。コカ・コーラであればリマインダー広告を打ち続けて、メッセージを世間へ出し続けることで“忘れられる”ことを防いでいます。日本マクドナルドも一時期衰退期に向かっていましたが、全国2900店舗を「ポケモンGO」の「ポケストップ」にした効果もあって、衰退期に入ることから逃れることができた印象です。
――そのポケモンGOのように、導入期もなく、いきなり大ブームとなるケースも頻繁にあります。
有馬 発売前からメディアで多く取り上げられれば、導入初期の認知度の高さが売上を急激に伸ばすことがあります。同じような例でいいますと、初期の米アップル「iPhone」や米マイクロソフト「Windows95」もそうですね。これらの製品は、一ブランドだけで考えれば必ずしも導入期ではないのですが、「スマホ」や「PC」といった製品カテゴリで考えると、導入期に該当していました。つまり、ポケモンGOもAR(拡張現実)とGPS機能を活用した「位置情報ゲーム」というシーンでは、導入期と考えられます。
製品・サービスの「廃れ方」
――「たまごっち」も一時爆発的に売れ、類似品もたくさん生み出しましたが、今ではまったく見る影がありませんね。
有馬 好調に売れる期間の代表的パターンは「スタイル」と「ファッド」の2パターンがあります。スタイルとは住宅、衣服、芸術などの分野にみられるあまり流行に左右されない基本的要素を含む場合のパターンです。時間と利益の相関関係はゆるやかな曲線を描き、多少の流行と廃りを繰り返しながらも、長ければ何世代にもわたって続いていくパターンを指します。ファッドは急速に販売が伸びて、すぐにピークに達し、その後、急速に販売が落ちる曲線を描きます。このパターンは製品だけでなく、アイドルなどのサービス財にもある程度当てはまります。
――廃り方にも種類はありますか?
有馬 たまごっちなどのように単純に時代遅れとなって市場から消えるケースもありますし、オープンリールからカセットテープ、MD、CD、mp3といった音楽メディアのように技術革新によってより利便性の高い製品に取って代わられる場合もあります。
もうひとつのケースとして、薬品などは規制などによって衰退期を待たずに強制終了を迎えることもあります。サービスでいえば、「レーシック手術」は一時期持てはやされていましたが、手術後に感染症になるなどの事故が相次いでいるとニュースで報じられたために、すっかり患者数が減っているそうです。タレントが不祥事を起こして、売り出し中にもかかわらず芸能界から強制的に排除されたという出来事が最近ありましたが、サービス財というのは、不祥事の影響を一番受けやすい製品なのかもしれませんね。
――ありがとうございました。
(解説=有馬賢治/立教大学経営学部教授、構成=A4studio)