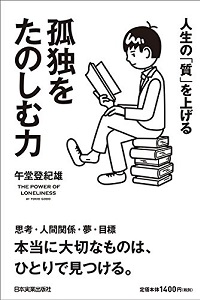常に他人の目を気にして「窮屈な人生」を送るキミへ…「孤独を楽しむ力」で解放!
 「Thinkstock」より
「Thinkstock」より昨今は、LINEやFacebook、InstagramといったSNS、そしてそれらが使えるスマートフォンの普及によって、常に誰かとつながっている「常時接続」の時代になっています。こうしたSNSは、人間の承認欲求を満たすには格好のツールで、若い人のなかには自分の見られ方を非常に気にし、「いいね」欲しさに写真映えを工夫する人も少なくありません。
しかし一方で、皆が自分を見せ、そして見てもらうという状態は、ある意味「監視社会」を生み出し、日本人の常識や道徳観に合わない言動をする人をいっせいに叩く「炎上」を頻繁に生み出す結果となっています。
そんなふうに強い同調圧力が世間を覆えば、価値観が均質化されやすくなり、人は周囲の反応を過剰に気にするようになります。「生きづらい世の中」「窮屈な社会」といわれるのもそのためです。
そんな重圧から抜け出すひとつの能力が、「孤独を楽しむ力」です。多くの人は「孤独」や「ぼっち」という言葉にネガティブな印象を持っていると思います。実際に日本人のなかには、人との絆やつながりこそ重要であり、「孤独はよくないことだ」という常識があります。「人間はひとりでは生きていけない」という言葉に、「それは違う」と言える人は多くないと思います。
入学・進学した子どもが帰ってきて親が一番にかける言葉が「お友達はできた?」であるように、友達や一緒にいる人が少ない人、つまり孤独な人は、人間として失格であるかのような価値観を強いています。テレビや週刊誌でときどき「孤独死」という言葉が出てきますが、これもやはり孤独をネガティブにとらえている人々が多いということでしょう。
そのため多くの人は孤独を避けようとし、ひとりでいるところを見られまい、知られまいと振る舞います。実際には、孤独がみじめなのではなく、「孤独はみじめだ」と思い込んでいる自分の固定観念が原因です。
たとえば、「ランチメイト症候群(ランチに一緒に行く友達・同僚がいないことが強いストレスとなり、会社や学校に行けない)」や「便所飯(トイレの個室の中で弁当を食べる)」といわれる現象も、ひとりでいるところを見られて「あいつは友達もいない寂しいヤツだ」と思われるのを極度に恐れるからです。
そうした思い込みは、ひとりにならないよう、寂しい人間だと思われないように、自分とは合わない人とでも無理に付き合う、合わないグループに自分を抑えてでも所属する、という行動を生み出します。
しかしそれは、本当の自分を出しているわけではなく、我慢して周囲に合わせて生きているので、いずれ精神的につらくなります。そうやって人間関係に疲弊し、行き詰っている人は少なくありません。
孤独力とは「能力」であり、高められる「スキル」である
そんな時代環境だからこそ獲得したいのが「孤独力」です。
孤独力とは、他人との接触を避け、物理的な孤独の状態そのものを愛するような、自閉的な意味ではありません。社会のなかで人とかかわりあいながらも、常に自分の意思を主軸に置いて、自己責任で生きるという姿勢のことです。この姿勢があれば、誰かと一緒でも楽しめるし、ひとりでも楽しめます。物理的に孤独になったとしても、寂しさを感じることはありません。
そうした感覚を強く持つためには、自分との対話、つまり内省という習慣を手に入れることです。内省とは、自分の価値観を振り返り、それをベースに経験を振り返って分析し、自分の思考体系とそれに起因する行動体系を軌道修正し、自らを成長させていく、高度に知的な作業です。
精神医学・心理学者のアンソニー・ストーがかつて、「ひとりでいられる能力は、自己発見と自己実現に結びついていき、自分の最も深いところにある要求や感情、衝動の自覚と結びついていく」と述べたとおり、孤独のなかで自分の本心を的確にとらえ、それを生き方に反映させていくことでもあります。
そうやって自分で自分の心を錬磨していく。たとえばAI(人工知能)がディープラーニング(深層学習)によって自己進化していくように、孤独による内省とは、自分で自分の精神を進化させるセルフ・ディープラーニングともいえます。
孤独は生きる強さの証
そして、孤独な人間だけが持てる力に「人生の構想力」があります。人は大人になる過程で、世間というモノサシで自分を見て、あるいは他人と相対することによって、自分がどういう人間であるかを解釈しようとします。たとえば他人と比べて運動や勉強ができるかどうか、容姿はどうだとか。つまり「世間のモノサシ」から自分という存在の価値を認識するわけです。
もちろん、これはこれで必要であり不可欠なプロセスなのですが、孤独を恐れる人は、世間のモノサシを重視しすぎて、社会の常識やモラルに合わせようと、自分で自分を縛ってしまいます。そうやって他人に合わせて他人流で生きようとするため、息苦しくなるのです。
また、孤独を恐れる人は、絶えず他人に光を発し、反射されて返ってくる光のみでしか自分を認識できません。他人がいなければ自分の存在が確認できないうえ、他人の動きによって乱反射する光に惑わされたり揺らいだりします。
だから彼らは「ロールモデル」を欲します。「好きにしていいよ」と言われてまっさらな空間に放り出されても、手本となる生き方がないと、自分は何をしたいか、何をすればいいかわからない。周囲からどう思われるか不安で、自分で生き方を決めることができません。それは結局、世間並みの発想、世間並みの生き方になるわけで、いわゆる「その他大勢」といわれる人々です。
しかし、孤独のなかで内省によって自分の本心と向き合うことで、世間のモノサシから自分独自のモノサシへと比重を移すことができるようになります。「自分はこれでいいと思う」「自分はこれが幸せにつながると思う」「他人はそう言うけれど、自分はこう考える」などという価値判断基準であり、自己肯定感であり、自律心です。
自分で自分の能力を生かせる
それが育つと、過剰に他人の目を気にして行動するとか、人からどう思われるか気になって本音が出せないとかといったことが少なくなります。そして、無理に自分を抑えてでも誰かと一緒にいなければならないとか、友達がいない人間は価値が低い、などという強迫観念もなくなります。
誰にも依存せず、すべてを自分で決められる(決める)という意志がある。すべてを自分で解決できる(する)という覚悟がある。他人のネガティブな影響を受けず、ポジティブな影響だけを自らの判断で選んで受け止めることができる。外的な要求や圧力に屈することなく、自分の意思と信念で自分の行動を選別できます。
他人からの影響を理性で排除し、自分の頭で自分の人生の展開を考え、「こう生きよう」という道筋を導けるようになり、それを信じられるようになる。そんな姿勢はまさに、自己責任において、自分の人生をデザインできる「人生の構想力」にほかなりません。
ドイツの哲学者カントは、「自己を啓発するとは未熟さから抜け出すことであり、未熟さとは、他者からの指示を受けないと自分の能力を使えない状態」と言いました。孤独とは、自分の意志で自分の能力を生かすことでもあるということです。
孤独力とは孤高としての強さを持つこと
そこで今回、新刊『人生の「質」を上げる 孤独をたのしむ力』(日本実業出版社)を上梓しました。
詳細は本文で紹介しますが、孤独のなかで自分と向き合うことで、自分の感情を意のままに操れるようになれます。自分で自分を理解し、認めてあげることができれば、「わかってくれない」「評価してくれない」という不満が出ることはありません。
自分が全力を尽くして事に当たったなら、満足できる結果だろうとそうでなかろうと、自分の努力を認めることができます。そうやって不安や悩みも自己消化できるし、出来事への捉え方を変え、幸せを感じられます。そんな精神の強さを高めるには、必ず孤独の時間が必要なのです。
精神分析家のD・W・ニコットが論文で、「ひとりでいられる能力は高度に知的加工の加えられた洗練された現象で、情緒的成熟と密接に関連している」と述べたように、いざとなったら、ひとりでも平気と自信を持て、嫌われて孤立しても気にせず、「自分にとって本当に大切なのは、自分の人生を生きること」と思える強さは、大人としての成熟度といえるでしょう。
つまり本書で言うところの孤独とは、人との接点を自ら避けるとか、誰からも無視されて孤立することではなく、自分の信じる道を歩く「孤高」のほうが近い概念です。
みんなでいても楽しいけれど、ひとりでも楽しい。どちらの状態でも楽しむことができる。ひとりになることが怖くなければ、無理して周囲に合わせて人間関係を維持する必要もなく、自分らしく生きられるのです。
本書では、寂しさという意味でのネガティブな孤独ではなく、人間が精神的に成熟するための必須体験としてのポジティブな孤独を紹介します。そして、いかに孤独を使いこなし、心の成長を獲得していくか、その方法論も紹介しました。
もし孤独でつらい、寂しい、苦しいと感じている人が、孤独はむしろとても素晴らしいことであると感じていただけたら、著者として大変うれしく思います。
(文=午堂登紀雄/米国公認会計士、エデュビジョン代表取締役)