 「Gettyimages」より
「Gettyimages」より前回の記事で、アマチュアスポーツ界における組織上層部によるパワハラ問題や、独裁的な経営がされている組織などにおける不祥事など一連の騒動は、氷山の一角にすぎず、日本社会全体に“組織の金属疲労”が起きているのではないかと指摘しました。そして、そうした日本の組織で起きている事象は欧米のトップスクールで教えられているネットワーク分析の理論(以下、ネットワーク理論)とプラットフォーム戦略®を学ぶことでより深く理解できると指摘しました。
ここまでM・グラノヴェッターの「弱い紐帯の強さ(“The strength of weak ties”)」、シカゴ大学ビジネススクール教授のロナルド・S・バートの「構造的空隙の理論」「ネットワーク密度」「構造同値」「ランダムネットワーク」と「スケールフリーネットワーク」等についてご紹介してきました。今回は「ネットワークの中心性」と「ハブ」についてです。拙著『世界のトップスクールだけで教えられている 最強の人脈術』(KADOKAWA)からご紹介しましょう。
誰が中心か?4つのネットワーク中心性
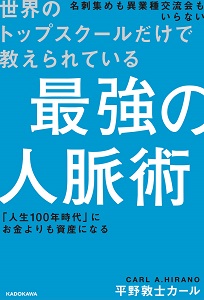 『世界のトップスクールだけで教えられている 最強の人脈術』(平野敦士カール/KADOKAWA)
『世界のトップスクールだけで教えられている 最強の人脈術』(平野敦士カール/KADOKAWA)ある組織において、最も影響力のある人物、あるいは重要な人物とは、どのような人でしょうか。会社であれば、社長や会長などが頭に浮かぶかもしれません。しかし、本当にその組織で重要な人物とは、じつは現場の工場長であったり、ミドルクラスの課長であったりするわけです。あなたが今いるポジションによっても、それは変化することでしょう。
みなさんが持っている人脈ネットワークにおいて、中心的な存在とは誰でしょうか。SNSなどで友だちの多い人や、ツイッターなどでフォロワーが多い人は、たしかに中心的な存在、あるいは目立つ人という印象があるかもしれません。しかし、必ずしもつながりの数が多い人が重要であるとはいえないことも明らかでしょう。
たとえば、今A社の社長に会いたいと思っている人にとっては、A社の社長と仲のよい人こそが重要な人物であり、その人がSNSでどれだけ人気者かどうかについては関係がありません。このように「中心性」にはさまざまな考え方があるわけです。
ネットワーク理論では、個人の資質や能力はいったん脇に置いて、その人の人間関係、すなわち人脈ネットワークでのポジションにこそ、その存在価値があると考えます。そして、「ネットワーク中心性」という考え方は、人脈ネットワーク内で最も中心的な存在は誰か、ということを測定するために開発された指標です。
社会学的にいえば、これはあるノード(点)がどのくらい重要な(中心の)位置にいるかを測定しようとするための指標のことで、カリフォルニア大学教授のリントン・C・フリーマンは、このネットワーク中心性について、以下の4つの分類を行いました。
(1)次数中心性
「次数中心性」とは、関係を維持している数、つまりノード(点)のもつエッジ(辺)の多さ、すなわち紐帯の多さによって中心性を測る考え方です。多数の人とつながっている人が中心であり、重要な人である、という考え方です。たとえばツイッターのフォロワー数やブログの読者数などが多い人が重要な人であるとするもので、感覚的にもわかりやすいでしょう。
(2)近接中心性
「近接中心性」とは、効率よく最大多数の人に接触できる人、すなわちノードとノードとの距離が短い人が中心である、という考え方です。具体的にはすべての他のノードとの距離の近さによって、中心性を測ります。より少ないリンクで他のノードにたどりつける、情報伝達効率がよい人となります。
(3)媒介中心性
「媒介中心性」とは、人と人とをつなぎ合わせる力、つまり「媒介性」がある人が中心である、という考え方です。
たとえば、A→B→C→Dという関係があった場合、AとDがつながるためには、BとCという存在が必要です。同様に、BとDがつながるためにはCという存在が必要です。この場合、CはBとD、さらにはAとDの関係を媒介しているといえます。こうして媒介している数のことを「媒介性」と呼びます。
この例では、CはBとD、さらにはAとDを媒介しているので媒介性は2となります。一方、AとDは誰のことも媒介していないので媒介性は0、BはAとC、AとDを媒介しているので媒介性は2と考えます。つまり、BとCの媒介性は2、AとDの媒介性は0です。
そこでネットワークの中心的な存在とは媒介中心性、つまり他の人との関係を媒介する力が強い人と見なした場合には、BとCがその中心ということになります。そこで、多くの人を媒介する人は「ハブ」と呼ばれます。国際空港などでも、多くの国に飛行機が飛んでいる空港を「ハブ空港」と呼びますが、それと同じです。この「ハブ」という考え方はプラットフォーム戦略®を考えていくうえでも非常に重要です。
(4)固有値ベクトル中心性
「固有値ベクトル中心性」とは、自分に対してエッジ(辺)を張っているノード(点)がどれだけの中心性をもっているか、ということによって、その中心を考えます。わかりやすくいえば、あなた自身がどれだけの次数(友人)をもっているかではなく、「多くの友人をもっている人」とつながっているかどうかによって、あなたを評価する、というものです。
世にいう黒幕と呼ばれる人などが、わかりやすい例でしょう。黒幕は最も重要な人物ですが、決して表には出てきません。彼らは決して多くの人とつながっているわけではなく、世間で知られた権力者や政治家などの有名な人のうちの、さらにごく一部の人たちとだけつながっています。固有値ベクトルで見れば、こうした黒幕が中心となります。
みなさんも馴染みのある例でいえば、検索エンジン最大手のグーグルが採用しているページランクという、検索エンジンに掲載する順位を決定するためのアルゴリズムも「固有値ベクトル中心性」に基づいたものです。
グーグルの検索エンジンでは、多数のページからリンクを貼られているページは人気があると見なし、その多数のリンクが貼られているページからリンクを貼られているページは、より人気があると見なすアルゴリズムになっています。つまり、人気のあるページからリンクを貼られているページは、人気のないページからリンクを貼られたページよりも検索エンジン上のスコアが高くなるといわれています。
これはもともと、「優れた論文は引用される数が多い論文である」という考え方に基づいているとされます。事実、ノーベル賞などの選考においても、引用された論文の数が多い人が有力な候補になるための条件とされています。もっとも、最近ではグーグルの検索エンジンのアルゴリズムもページランクだけでなく、そのサイトがどのくらい有益な情報を網羅しているか、あるいは情報の質やサイト運営者の信頼性など、200以上の指標をもとにしたアルゴリズムに変がされているようです。
本当に大切な人とのつながりが重要
以上、4つの中心性についてご紹介してきました。この4つの中心性のなかでどれが重要かは見方や文脈によって決定されるもので、一概にそれをいうことはできません。つまりSNSなどでむやみにフォロワー数を増やすことは目的によっては理論的に意味がないともいえるのです。あなたの目的に応じた本当に大切な人とのつながりこそが重要なのです。
一つ確かなことは、今世界で最も時価総額が高く成功しているGAFAなどの企業は、3つ目の「媒介中心性」のなかで登場した「ハブ」のポジションをとっている、ということなのです。そしてこの「ハブ」になる経営戦略論がプラットフォーム戦略®といえるのです。次回以降で詳しくご紹介していきましょう。
(文=平野敦士カール/株式会社ネットストラテジー代表取締役社長)


















