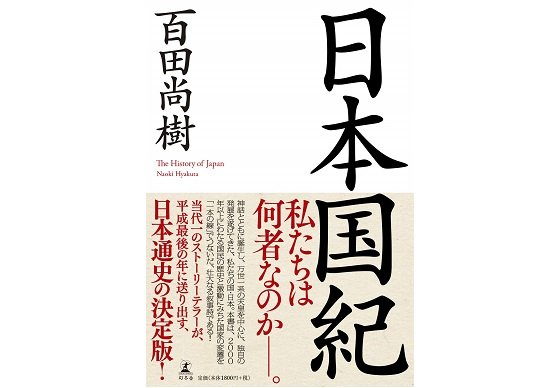「通史」、というのは、実に難しい専門家泣かせの分野です。多くの場合、各時代各分野の専門家に執筆を依頼し、だれか一人が編集者として全体にまとまりをもたせる、という手法が一般的。
しかし、わかりやすさや読みやすさ、という部分を重視するならば、ある程度、文学者や作家の手を借りることで、わかりやすく説明できるものであることは確かでしょう。その意味では、百田尚樹氏の『日本国紀』(幻冬舎)には期待するところもありました。
ただ、先にお断りしておくと、この本はCコードの0021ではなく0095に類する書であるという点です。つまり「日本史」の本ではなく、あくまでも「日本文学・評論・随筆・その他」の本です。本書の帯書きには「壮大なる叙事詩である」とあり、同時に「日本通史の決定版」と記されています。したがって、本書を読む場合は、この2つの側面をどうとらえて、どう評価するかということになりそうです。
とくに、筆者が文末表現で「推測にすぎない」「~を示す資料はない」など独自見解については明示されているので、その部分は評せず、「通史の決定版」としての側面での評を中心に進めたいと思います。
また、私自身は高等学校で歴史を教えているので、その立場・視点からの指摘もさせていただくことをご了承ください。
さて、「通史」は以下の(1)~(5)の手法・形式・留意点が必要であると私は思っています。
(1)歴史「を」説明することに軸足を置くか、歴史「で」説明することに軸足を置くのか。
(2)その説明を「断絶論」で説明するか、「連続論」で説明するか。
(3)その理由は、「テコ」で説明するか、「合力」で説明するか。
(4)一つで全体を説明しない。全体で一つをおろそかにしない。
(5)最近の研究と定説化は違う場合もある。紹介することと定説として示すことは別。
(1)歴史「を」説明することに軸足を置くか、歴史「で」説明することに軸足を置くのか
(1)について、『日本国紀』を要約し、筆者の主張をまとめると、
「日本は、すばらしい国で、素晴らしい人たちが活躍してきた歴史がある。しかし、GHQの占領政策、戦後の教育によってその歴史がゆがめられた」
ということになりそうです。歴史の出来事をアナロジーとして日本の素晴らしさ、日本人の素晴らしさを説明していく、という筆者の思いが込められていて、この点は「叙事詩」的な部分なのでしょう。
(2)その説明を「断絶論」で説明するか「連続論」で説明するか
(2)について、「断絶論」なのか「連続論」なのかというところですが、たとえば、邪馬台国が九州にあったか近畿にあったかは、九州説をとればヤマト政権とは断絶だし、近畿説をとれば連続となります。
国風文化も、遣唐使の廃止によって日本独自の文化が生まれたとしたら断絶論ですし、遣唐使は従来と同じく「停止」にすぎず、日本の風土や環境、慣習や伝統に順応して漸進的に生まれたとするならば連続です。
鎌倉文化は、それまでが貴族の文化で、鎌倉時代から武士や庶民の文化に変わったとしたら断絶で、貴族文化も鎌倉時代の貴族に受け継がれ、それと並行して新しく武士や庶民という担い手が加わったとしたら連続です。
また、江戸が「夜」で明治が「夜明け」ならば断絶ですし、幕末からすでに文明開化が始まっていたとするならば連続となります。
筆者は、江戸時代は別として、上記の「邪馬台国」や九州王朝説、「国風文化」「鎌倉文化」など、ことごとく断絶の立場から筆をとっておられます。この部分は教科書的説明や定説などとは著しく異なる部分ですので、なぜ定説とは違うか、教科書とは違うか、もう少し丁寧な説明をしていただきたかったところです。
(3)その理由は、「テコ」で説明するか、「合力」で説明するか
(3)について、人物や特定の事件を「テコ」として歴史を説明するか、政治はもちろん、社会・経済・外交、当時の文化などとの「合力」で説明するか、というところですが、総じてこの作品が歴史書ではなく、「叙事詩」であるということから、つまり作家として筆者の顔がどうしても出てくるようで、また(1)の側面から、人物や特定の事件で通史を書き進めていく姿勢がみられます。もちろん、この部分が「物語」としてのおもしろさでもあるのですが……。
「薩長連合」における坂本龍馬、幕末での勝海舟などの活躍はもちろん、「日英同盟」における柴五郎の扱いなどにそのことがよく表れているといえます。古代・中世の歴史上の人物の場合は、少し史実を逸脱した表現でも、『平家物語』や『太平記』のように、詩的な説明は魅力やおもしろみを引き出してくれますが、近現代の人物は、関係者も存命である場合もあるので、筆者はもちろん監修、編集段階のファクト・チェックは徹底しておかないと他の記述の信憑性も疑われてしまいます。
たくさんありますが、二例ほどあげておきますと、コラムでユダヤ人を救った日本人として杉原千畝を取り上げていますが、彼は「ゴールデンブック」には掲げられておらず、三井物産の古崎博の誤りかと思います。
また、サイパン陥落時、岸信介は商工大臣ではなく無任所の国務大臣でした。記載されているような発言をしたとすれば軍需次官だったからではないでしょうか。
また、人物の言動を示した資料も正確に引用しないとその人物の魅力が誤って読者に伝わってしまいます。そのような一例としては、
「この国の人々は、これまで私たちが発見した国民の中で最高の人々であり、日本人より優れている人々は、異教徒の中では見つけられないでしょう」
という来日した宣教師の言葉があげられます。これはルイス=フロイスの書簡ではなく、フランシスコ=ザビエルの書簡からの引用で、教科書にもよく取り上げられているものです。
(4)一つで全体を説明しない。全体で一つをおろそかにしない
(4)について、「一つで全体を語らない」「全体で一つをおろそかにしない」ということですが、これもいくつか例をあげておきますと、水戸家の特殊性を説明するにあたり、「参勤交代」の実状に誤解をあたえかねない部分がありました。参勤交代で江戸定府は実は水戸家だけではありません。御三家の中で、あるいは主だった大名の中では、と説明すべきだったと思います。また、参勤交代は「諸藩が力を蓄えられないようにする(幕府に歯向かうことのないようにする)」ためと説明されていますが、幕府がそのような意図で参勤交代を始めたことを示す史料はなく、いわゆるこれは俗説で、教科書から消えてかなり久しくなっています。
また、本書は日本史の物語、「叙事詩」ではありますが、世界史との関連を説明した箇所では、筆者がやや雑に説明してしまっていて、ここでも誤解を受けかねません。むしろ専門外・対象外であるからこそ、丁寧に正確に、そして慎重に著述すべきであったと思います。
「江戸はロンドンやパリ以上に歴史のある町で…」(P167)
日本の素晴らしさを伝統や歴史から伝えようとするあまりの勇み足だとは思いますが、ロンドンもパリも、古代ローマから存在する歴史のある町で、江戸よりもはるかに歴史が古い都市です。
「ヨーロッパ諸国はすべて君主制だったので、フランスの市民革命が自国に広がるのを抑えようと、革命政府をつぶしにかかったが、ナポレオン=ボナパルト率いるフランス軍がそれらの国を打ち破った」(P212)
当時、ヨーロッパのすべてが君主制であったわけではありません。
「経済学者のマルクスが唱えた共産主義を信奉するレーニンが武装蜂起し、政権を奪って皇帝一族を皆殺しにしたのだ。人類史上の一党独裁による共産主義国家ソヴィエト社会主義共和国連邦(ソ連)の誕生である。ソ連はドイツとの戦争をやめ…」
ソ連が成立するのは1922年で、それまではロシア=ソヴィエトと説明されている場合が多く、1917年から22年までの内戦を通じて、赤軍が旧ロシア帝国領内のザカフカース・ベラルーシ・ウクライナを統合、22年にソヴィエト社会主義共和国連邦を成立させました。ドイツと単独講和を結んだブレスト=リトフスク条約は1918年に結ばれたもので、ソ連と結んだものではありません。
「ヒトラーが率いる政党ナチス(国家社会主義ドイツ労働者党)も、ムッソリーニのファシスタ党も、正当な選挙で政権を取ったということである」(P363)
ムッソリーニが政権を獲得したのは選挙ではなく、クーデターともいうべき「ローマ進軍」と国王の任命によるもので、正当な選挙によるものではありません。ちなみにナチス、NSDAPの訳語は国家社会主義ドイツ労働者党ではなく、「国民社会主義ドイツ労働者党」とかなり前から教科書などでも表記が改められていて、ドイツ近現代史の専門家で「国家社会主義」という訳語を使う人はかなり以前からいなくなっています。
(5)最近の研究と定説化は違う場合もある。紹介することと定説として示すことは別。
(5)について、最近の研究と定説化は違う場合もある。紹介することと定説として示すことは別、ということですが、学説、また新しい研究というのは「振り子」のようなもので、一方に振り切ってもまた研究が進んで逆の方向に振ったりするものです。いくつかあげられますが、一例としては、室町幕府の足利義満についての説明です。いわゆる皇位の簒奪、自分の子を天皇にすることによって自らは上皇になろうとした、という話が述べられています。一時期、この王権簒奪説は取り上げられましたが、現在では否定されている説です。
「叙事詩」というか物語としてはおもしろいものですが、むしろコラムとして「紹介する」にとどめ、足利義満の権力獲得過程、明徳の乱や応永の乱にページを割かれたほうが「通史」としての厚みが出たように思います。
さて、最初に本書の要約は、
「日本は、すばらしい国で、素晴らしい人たちが活躍してきた歴史がある。しかし、GHQの占領政策、戦後の教育によってその歴史がゆがめられた」
というものである、と説明しました。500ページをこえる本書のうち、P282以降が明治以降の説明となっていますが、とくに第9章以降の要約は、以下のようにも説明できます。
「侵略ではなく自衛」であった戦争が、
「GHQ・戦後の教育」によって
「自衛ではなく侵略」として説明されてしまった。
しかし、「通史」であるとするならば、また自説を主張するような場合でも、「その理由は『合力』で説明し、一つで全体を説明しない。全体で一つをおろそかにしない。最近の研究と定説化は違う場合もある。紹介することと定説として示すことは別」という立場で、説明したほうが説得力はあったように思います。
最後に
「定説」というのは、氷山と同じで、見えている部分はほんの少しです。何もないように見えても多くの研究者の、たくさんの議論と検証、傍証と追加資料で積み重ねられたものです。
本書はあくまでもC0095で、「文学・評論・随筆」です。読者諸氏は、これらの定説や多くの研究者の説明を覆すようなものではない、と考えてほしいと思います。
(文=浮世博史/私立西大和学園中学高校教諭)