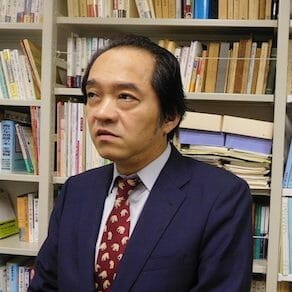“強姦冤罪事件”国家賠償請求を棄却、なぜ「公務員のミス」は許されてしまうのか?
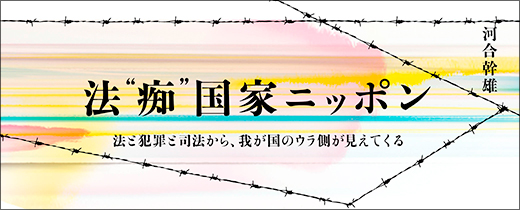 法社会学者・河合幹雄の「法“痴”国家ニッポン」
法社会学者・河合幹雄の「法“痴”国家ニッポン」第10回 2019年1月、強姦冤罪事件はなぜ「国家賠償」されないか? 国が「過ちを認めない」不可思議なシステム
2019年1月8日、大阪地裁で開かれた国家賠償請求訴訟。14歳の少女を強姦したなどとして懲役12年の実刑判決が確定したものの、冤罪であったことが服役中に明らかとなり、2015年の再審で無罪となった男性(75)とその妻が起こしたものです。
逮捕から6年以上身柄を拘束された男性は、逮捕・勾留・服役 1日当たり上限1万2500円の補償金の支払いを定めた刑事補償法に基づき、すでに約2800万円の補償を受けています。ただし、それはあくまで不当な拘束に対する補償として支払われたのであって、国が捜査や裁判の誤りを認めて謝罪したわけではない。そこで男性は、冤罪によって受けた精神的苦痛に対する国と大阪府の責任を追及すべく、今回の国家賠償請求訴訟に至ったわけです。
ところが大阪地裁は、「起訴や判決が違法だったとは認められない」として、男性側の請求をすべて棄却しました。本連載前回記事『強姦冤罪事件を生み出した“プロ失格”の検察と裁判所が“14歳の少女”のウソを見抜けず』において、そもそもこの冤罪事件を生むに至った2008年の裁判がどれほど杜撰なものであったかを詳しく解説しましたが、ひとことでいってこの冤罪は、検察と裁判所の完全なミス。それによって男性は長期間刑務所に入れられ、物心両面で多大な損害を被ったのですから、国が賠償責任を負うのは当然、というのが一般的な感覚でしょう。
 大阪地裁のほか、大阪高裁、大阪簡裁などが入る、大阪市北区西天満の合同庁舎(写真:上田 安彦/アフロ)
大阪地裁のほか、大阪高裁、大阪簡裁などが入る、大阪市北区西天満の合同庁舎(写真:上田 安彦/アフロ)死刑冤罪の場合、数億円の“補償金”も
ただ、わが国の司法の現状を知る者からすると、請求棄却というこの結果は、決して意外なものではありません。というのも、実はこのような冤罪事件において、国家賠償が認められた例はほぼ皆無といっていいからです。それは、死刑冤罪でさえ例外ではありません。
もっとも、身柄拘束の期間が数十年単位におよぶこともある死刑冤罪の場合、先に述べた刑事補償金で一応“こと足りてしまう”という側面もないではない。冤罪が判明して無罪になると、国家賠償が認められるかどうかにかかわらず、拘束期間の長さによって刑事補償金の総額は数千万円から数億円に達します。もちろん被害者からすれば到底納得いかないでしょうが、その金額でよしとして、勝てる見込みのほとんどない国家賠償請求をあきらめてしまうケースも少なくないわけです。
では、そもそもこの「国家賠償」というのはいかなる制度で、どういう場合に認められるものなのか。また、それを踏まえて、今回のケースで国家賠償が認められなかったことをどう評価すべきか。今回はそのあたりについて考えてみたいと思います。
“悪意ある違法行為”でなければ認められない国家賠償
まず、国家賠償の定義ですが、これは国家賠償法第1条において、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」と規定されています。
平たくいうと、公務員が、わざとであろうとミスであろうと、業務上誰かに対して違法に損害を与えたとき、その公務員個人に代わって国や自治体が賠償しますよ、という法律です。ですから当然、今回のように捜査や裁判におけるミスで冤罪が発生した場合にも適用され得るわけです。
ただ、ここで問題になるのが、「違法に損害を加えたとき」という文言をどうとらえるか、ということ。最高裁の判例では、
「違法行為があったとして国の損害賠償責任が認められるためには、裁判官が違法または不当な目的をもって裁判をしたなど、付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情がある場合でなければならない」
「各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があったときは、検察官の公訴の堤起および追行は違法行為に当たらない」
とされている。
要するに、「検察官や裁判官が、悪いことをしようという明確な意図のもとに行ったことでなければ、国家が賠償する必要のある違法行為には当たらない」という判断なわけです。国家賠償法の条文からすれば、「過失によって違法に他人に損害を加えたとき」も賠償の対象となるようにも思われますが、実際の判例から判断すれば、事実上「過失による違法行為」は、国家賠償の対象としてはほぼ認められていないのです。
これを今回のケースに当てはめると、大阪地裁が国家賠償請求を棄却した理由として挙げた、「検察が、職務上の注意義務を怠ったとは認められず、少女らの供述に基づいて男性に有罪と認められる嫌疑があると判断したことは不合理ではない」「裁判官が、違法または不当な目的をもって裁判をしたなどの特別の事情は存在しない」ということになります。
単なる「公務員のミス」では違法行為に当たらない
一般的な感覚からすると納得しがたい、こうした理屈がまかり通っているのは、もともと国家賠償法というのが、「公務員のミス」を想定して立法されたものでないことが原因といえます。この法律で想定されているのは、たとえば2010年の大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件のようなものです。当時厚生労働省の局長だった村木厚子さんが、大阪地検特捜部による証拠のフロッピーディスクの改ざんによって、障害者郵便制度悪用事件の犯人に仕立て上げられたあの冤罪事件のような、極端な国家の暴走があったときに備えてつくられています。そもそも、そういうコンセプトの法律なのです。
今回の強姦冤罪事件においては、担当の女性検察官が当時14歳の少女の被害証言を信じて疑わず、証拠を調べようとしなかった。それがいわゆる未必の故意、つまり、検察官がはじめから被疑者の男性を犯人と決めつけて故意に不利な証拠を排除したのならば、国家賠償の対象となる違法行為と認定される可能性はあるでしょう。しかし判例上、単なるミスや怠慢なら、国家賠償の規定する違法行為には当たらない、と解釈されてしまうわけです。
事件を担当した検察官・裁判官は糾弾されるべきか
国家賠償法というのが、たとえもともとそういう成り立ちのものであったとしても、今回の冤罪事件における検察・裁判所のミスは明らか。これを契機として、「過失によって違法に他人に損害を加えたとき」という法の条文に立ち返り、国の賠償責任を認めるべきだと私は思います。
ただ同時に、ネットなどでは事件を担当した検察官や裁判官の実名を挙げ糾弾するような声さえ高まっていますが、必要以上に個人を攻撃するのは、控えるべきだとも思います。検察官や裁判官とて人間であり、ミスをすることはある。もしそれが絶対に許されないということになれば、司法の場において検察官や裁判官がミスを恐れて萎縮し、犯人であると確信できないような怪しいケースをあえて追わずに見逃してしまう、というようなことも起きかねない。それは結局のところ、社会的損失として国民自身に跳ね返ってきます。
公務員に限らず、組織内のある個人が犯したミスについて、その個人を糾弾したくなる気持ちは、一般感覚としては大いにわかります。しかし、それをあまりにも追及してしまうと、結局のところ個人攻撃で終わったり、あるいはそのミスを生んだ背景にあるものを考える契機をなくしてしまいます。繰り返しますが、そのことは結果として、我々国民の不利益として跳ね返ってくる可能性もまた、はらんでしまうわけです。
それに、検察官や裁判官が、冤罪を生んでもなんら制裁を受けていない、と考えるのは誤りです。罪を着せられた者とは比較にならないとはいえ、検察官や裁判官にとっても、自分のせいで冤罪を引き起こしてしまうというのは精神的に大きな打撃であり、また出世という実利面においても消しがたい“黒星”となるからです。
今回の女性検察官の場合、2015年の再審で無罪が確定したのち、2017年に司法研修所の検察教官に就任したようです。司法研修所の教官は出世コースとみなされているため、一見不可思議な人事ではある。しかし、今回の冤罪事件を踏まえ、この検察官に対し、「現場向きではないが、人にものを教える専門の教師としては有能」といった人事上の判断が下された、とも解釈できます。
もちろん、それはただの推測にすぎません。しかし、ひとつ確かにいえること。それは、冤罪によって幸福を得る人間はひとりもいない、ということなのです。
(構成=松島 拡)