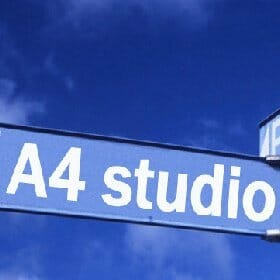「若者の免許離れ」「若者の車離れ」といわれるが、実際に警察庁の普通自動車免許に関する統計データでは、20代前半の免許の取得率は10年前に比べて約10%も減少しているとされる。だが、地方では自動車が主要な移動手段になっており、レンタカーやカーシェアリングを利用する人が増えていたりするため、一概に「車離れ」が進んでいるとはいえない面もある。
そこで今回は、自動車に関する問題やEV(電気自動車)の普及を考える市民団体、「日本EVクラブ」の副会長でもあり、日本カー・オブ・ザ・イヤーで1993年から選考委員を務める自動車評論家・御堀直嗣氏に話を伺った。
そもそも「若者の免許・車離れ」は実際に起きているのか?
「若者の車離れ」を考える上で、まずは押さえておくべき社会的背景があると御堀氏はいう。
「警察庁が発表した普通自動車免許の保有率に関するデータを見ると、20代前半はおよそ10年前の約80%に比べて約70%に下がっています。ですが、この現象も70%台で現在は横ばい状態。そしておもしろいことに、20代の後半から30代前半の免許保有率で見るとこれは90%台になるのです。つまり“20代前半までは免許を取らなかったけど就職してから必要になり取得した”というような背景が見えてくる。ここからわかるのは、“若者は免許を取得するのが後ろ倒しになってきている”という実情です」(御堀氏)
免許の取得は大学生の年代に当たる18~22歳頃に取る、というイメージがあるが現状はそうではないのだろうか。
「学生時代に免許を取る大きな理由は、時間があるので単純に免許が取りやすいからです。また、1970~80年代は車への憧れがあり“早く車を運転したい”という思いから早めの取得に到っていた背景があります。今はそうした車への思いもかなり変化し、たとえるならスマホ黎明期のブームから、徐々に効率的かつ必要なタイミングで購入するように意識が変わってきたのと同じだと思います。また1990年代、バブル崩壊後の就職氷河期には、普通自動車免許を持っているだけで就職で有利になり得ましたが、今はそうではないですからね」(同氏)
車を持たない選択をした約180万世帯、その背景に迫る
若者に限らずだが、普通自動車免許ではなく“車を持たない”選択が増えている通説についてはどうだろうか。
「今、日本で車が年間何台販売されているかを示す“自動車の販売台数“というデータを見ると、バブル期には約700万台もの数がありました。それが2012年頃までには、520万台ほどまで減少している。つまり“約180万世帯が車を持たない選択”をするようになったのです。一方で、カーシェアリングの会員数は今日本で160万人ほど。これは“車は持っていないけど利用はしている人”が約160万人(世帯)いるということで、先の“持たない選択をした約180万世帯”のうちの多数がこれに該当するとも考えられるわけです。これは経済的な理由が一番大きいでしょうね」(同氏)
だがこうした車の保有率は、地域差にも大きく影響されるという。
「年齢に関係なく47都道府県の免許保有率を見ると、東京や大阪といった都市部は保有率が少なく、地方都市は免許保有率が高い。これは公共交通機関の便利さに比例しています。都市部はJRや私鉄の路線が蜘蛛の巣のように張り巡らされており、利便性が高い。そして、“電車に乗るほうが安くつく”という声もありますが、電車の初乗り運賃が安いのは東京、大阪、名古屋の順となっており、利用客数が少なければ当然運賃も高くなるといった地域差が出ます。
ちなみに、とあるドイツの大手自動車メーカーの社員が東京に視察にきた際に、『こんなに電車やバスが充実しているのに、なぜ日本人が車を買うのかわからない』と困惑したというエピソードがあります。それくらい日本の都市部は利便性が高く、かつ日本の都市部と地方の利便性には地域差があるんです」(同氏)
では都市部の住民であれば、“車を持たないほうが得”ということになるのだろうか。
「免許を持つことは公共機関などでの証明書にもなりますし、カーシェアリングやレンタカーの運転ができるなどメリットも多いです。しかしズバリ言ってしまうと、車を所有することに関していえば、購入後に価値は下がる一方で、経済的な面からみるとデメリットのほうが多いでしょう。ただ、車を所有していれば生活面では当然行動範囲が広がりますし、自宅に駐車スペースがあればドアtoドアで移動できる快適さも得られます」(同氏)
カーブランドの戦略変遷、そして日本と欧米の車観の違い
トヨタの豊田章男社長が「メーカーが若者から離れてしまったのではないか。メーカーのほうから若者に歩み寄ろう」と発言しているが、メーカー側は時代に合わせどう舵取りを変化させてきたのだろうか。
「カーブランドの車業界に対するアプローチが変化してきたのは事実です。1960~70年代から日本の自動車メーカーは、アメリカへの輸出に力を入れてきました。しかし、日本に限らず1990年代からグローバルカーという名目で、特定の地域ではなく“世界で車を売る”というスタンスが浸透していきました。ただ、実際のところ、国によって合う車は千差万別で、車と土地のタイプが合わないねじれ現象が起きたんです。
さらに、製造面ではパーツごとの分業の加速、デザイン面ではコンピューターの演算機能の発達によって“一番燃費が良いフォルムのロールモデル”がはじき出され、各社に大きな違いが出づらくなってしまった。これによりメーカー側の開発意欲も昔とは違ってきている気はしますね」(同氏)
日本と欧米の運転免許保有率の違いも気になるところだ。
「アメリカとヨーロッパの免許の保有率は、日本より高いです。アメリカでは基本的に16歳から車の免許が取れるので、思春期の少年少女はその歳になるまで嫌々保護者に車で送り迎えされてきた鬱憤から、16歳で解放される喜びがある。ですから若者が積極的に免許を取って車を持ちたがるという文化的背景があります。ヨーロッパでは免許の取得は基本的に18歳からですが、F1やル・マンといったモータースポーツが日本より身近なので車への憧れは強いと思います」(同氏)
では最後に、日本の自動車業界は今後どうなっていくのだろうか。
「カーシェアリングが今後を大きく左右するでしょう。カーシェアリングは黄色い看板の『Times PLUS』が2010年頃から駐車場の空きを利用して全国で始めたことで、一気に広まった。これは完全に利便性と経済性の変化によるものです。加えて近年の高齢者の交通事故や免許返納、不景気による職業ドライバーの減少、自動運転の進化を鑑みると、ドアtoドアで目的地まで運んでくれる自動運転のカーシェアリングが、車業界が生き残っていく糸口になるのではないかと考えています。(同氏)
“自動運転のカーシェアリング”。一見すると未来が舞台のSF映画のようだが、利便性や効率性を重視して車と付き合っている現在の若者たちが、今後の車業界の中核を担っていくと考えると、夢物語ではない現実的な予想にも思えてくる。
(文=A4studio)