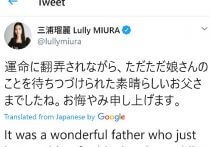5月上旬、米国で「新型コロナウイルス危機の結果、今後10年間で最大7万5000人がいわゆる『絶望死』する可能性がある」という衝撃的な予測が発表された。日本でも「今後自殺者が急増するのではないか」との警戒感が高まっているが、5月下旬に時宜にかなった著書が出版された。
タイトルは『新自殺論 自己イメージから自殺を読み解く社会学』(青弓社)である。 社会学の分野では1897年にエミール・デュルケムが当時の欧州の状況を詳細に分析して『自殺論』という有名な著作を発表している。『新自殺論』の著者たちも先進国の中で自殺率(人口当たりの自殺者数の比率)が高い日本の現状に鋭いメスを入れている。
日本で自殺問題が注目を集めるようになったのは1998年である。戦後最悪の金融危機に陥ったことから、自殺者数が初めて3万人を突破したからである。なかでも経済生活問題に起因するとされる自殺者数が前年比2502人増の6058人と急増し、特に中高年男性の自殺率が高かった。
自殺者数の高止まり(年間3万人以上)はその後も長く続いたが、減少に転じたのは意外なことに東日本大震災が起きた2011年だった。その年の自殺者数は前年比1039人減の3万651人となり、減少傾向は現在まで続いている(2019年の自殺者数は1万9959人<速報値>)。
「フェイス・ロス」
なぜ失業率が増加した2011年に自殺者数が減少に転じたのだろうか。
多くの日本人が職にあぶれていた第2次世界大戦直後の自殺率が現在よりはるかに低かったように、失業と自殺の関係は一筋縄ではいかない。デュルケムがかつて「自殺は不幸で説明できるほど単純なものではない」と述べたように、失業と自殺の関係は社会の状況によって異なる。隠れた要因があるからだ。
『新自殺論』のとりまとめ役を担った阪本俊生・南山大学教授は「自殺率を変化させている社会的要因は『フェイス・ロス』である」と主張しているが、どういうことだろうか。
フェイスとは大雑把に言えば「体面」や「面子」という自己イメージのことである。したがってフェイス・ロスとは「他人に合わせる顔がない」という状態のことを指していると考えることができる。
1998年当時の日本の「男らしさ」は、一家を養う稼ぎ手としての役割に直結していたことから、経済的苦境は中高年男性の面目を失墜させる結果を招いた。失業したり、自らが経営する会社が破綻してしまったことから、家族との関係で合わせる顔がなくなってしまった彼らは、恥の意識に苛まれ、その結果命を絶つという行為に走ってしまったのである。
中高年男性の自殺率はしばらく高止まりが続いたが、2003年をピークにその後は低下している。阪本氏はその要因を「女性の社会進出が徐々に進み、男女の役割分担に変化が起きていることがその背景にある。男女共同参画が進んで『イクメン』という言葉が普及したこともこの流れを後押しした」としている。男性が背負わされてきた「一家の大黒柱」という重荷が少しずつ軽くなってきているからだろう。
戦争時に自殺率は低下
自殺と社会の状況の関係については、戦争時に自殺率が低下するという傾向が世界各国で共通して見られるという興味深い事実がある。「倒すべき敵」が存在すれば、各人の意識は社会の連帯に向かい、日々の生活に張り合いが生まれるからとされている。
各国の指導者たちが現在の状況を「戦時」とたとえている。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的流行)が戦争や内乱などと同じような社会状況を醸し出しているとすれば、今後数年間、日本の自殺率を押し下げる要因となる可能性がある。
ちなみに今年4月の自殺者数(速報値)は前年比20%減の1455人となり、過去5年間で最少となっている。「外出自粛で職場や学校などに行く機会が減り、思い悩むことが少なくなった」ことがその要因の一つに挙げられているが、阪本氏は「『引きこもり』はフェイスが否定されることを避けるための自衛策になる」と指摘する。
確かに日本ではいまだに失業率と自殺率の相関関係が高い。生活保護受給者の自殺率は全体の2倍以上であることから、経済問題がもたらす生きづらさが自殺に関係しているが、自殺率を高めるのは物質的困窮よりも社会的な役割の剥奪である。阪本氏は「20~30代の自殺率は漸増傾向のままである。自殺率が低いからと言って幸福だとは限らない」とした上で、「大事なのは人としての尊厳を守りながら社会で生活が営めることである」と強調している。
失業者は、周りに多くの失業者がいて失業に対する公的支援があれば、あまり不幸を感じないことや、地域の首長が自殺対策に前向きな姿勢を見せるだけでその地域の自殺者の急激な減少が見られることも明らかになっている。「失業したのは自らの責任ではない。対策を受けることは当たり前の権利だ」という意識が浸透し、たとえ生活保護を受けていても積極的に社会参加できる環境になれば、「合わせる顔がなくなる」ことにはけっしてならない。
このように失業の増加は必ずしも自殺の増加とはならないのである。今後の日本の自殺者数の動向は要注意であるが、社会が失業をどのように受けとめるかが、その鍵を握っているのではないだろうか。
(文=藤和彦/経済産業研究所上席研究員)