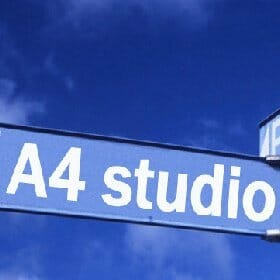「うちの夫はメンタルが安定している上に家事育児も高いレベルでできるとても良い夫なのですが、どのように育てられたかというと義母いわく、しっかりした幼稚園に通わせたわけでなく、熱心に家庭保育を施したこともなく、録画したアンパンマンをエンドレスで流して仕事してたそうです。励みになります」
今年の4月2日にあるTwitterユーザーが投稿したこのツイートが、7月10日現在までで1万リツイート、5.3万「いいね」を獲得するほど大きな反響を呼んでいる。しかし、幼少期にアニメ『アンパンマン』を観せることや、ほったらかし的教育をすることが安定したメンタルにつながるというのは、本当にありうることなのだろうか? 今回はそんな話題に関して、神奈川大学人間科学部教授で臨床心理士の杉山崇氏に話を聞いた。
不安の正体だという「社会的な排斥リスク」とは一体なんなのか?
ツイートにもあった「メンタルが安定している」という言い回し、近年は特によく使われているが、これは心理学的にはどういう状態を指すものなのだろう。
「心理学用語で言う『社会的な排斥リスク』を脳がモニタリングして、危険なしと判断している状態のことを指します。わかりやすく解説しますと、そもそも人間という生き物は、進化の過程で集団化・社会化を成し遂げていった存在であり、その社会にうまく順応しようと脳が自動的に指令を出します。そのひとつが『社会的な排斥リスクのモニタリング』なのです。
例えば、人間は罪を犯すなど、集団のルールから逸脱する行動をとると、大なり小なりの形で社会からはじき出されてしまいますよね。そういった状態にならないよう、脳は常に“この言動はリスキーじゃないか?”とチェックをし、危険と判断した場合はストレスとして知らせてくるのです。
『社会的な排斥リスク』をモニタリングする脳の器官は、幼少期に育まれる『愛情のモニタリング機能』と密接にリンクしています。1〜2歳の人間は、シナプスと呼ばれる脳の神経回路同士が盛んに食い合いをしている状態なのですが、この時期に自分を育ててくれる人間からどれだけ愛情を受けたかで、愛情を感じ取る『愛情のモニタリング機能』という回路の感度が変わってくるのです。
この『愛情のモニタリング機能』の高い人は、自分をよく愛してくれる人や集団を嗅ぎ分け、そこに身を置きやすくなる。すると、必然的に先に説明した『社会的な排斥リスク』を感じにくくなるわけですね。逆にこれが低い人は、自分を愛してくれない集団に期せずして身を置きがちで、メンタルが不安定になる場合も多いです」(杉山氏)
ただ、「愛情のモニタリング機能」の低い人が、必ずしも生きづらい人生を送ることになるわけではないという。
「ときに『愛情のモニタリング機能』の低い人同士で集団化することもありますが、このような環境では、お互い愛情がなくとも利害関係が一致してさえいれば、クールで過ごしやすい関係性を築くことができ、『社会的排斥リスク』を感じずに済むわけです」(杉山氏)
『アンパンマン』を観て育つと「社会的排斥リスク」を避けやすくなる?
メンタル安定の仕組みを理解したところで、本題である『アンパンマン』がメンタルに与える影響について聞いていこう。『アンパンマン』は育児、そしてその後の成長に伴うメンタルの形成に好影響を与えているのだろうか。
「好影響は確かにあるでしょう。理由としては、まず乳幼児の興味を引くビジュアルを持っていることです。『アンパンマン』は基本的に乳幼児が好む番組で、4歳から5歳を過ぎると興味がなくなりがちです。5歳未満の乳幼児は、人間の顔や丸っこい形状に大きな反応を見せたり安心感を覚えたりするので、アンパンマンのデザインは最適です。
次に特筆すべきは、人間は憧れの存在に自分を同一化し、人格を補強しようとする生き物なのですが、その性質と『アンパンマン』の相性が良いのです。公明正大で優しく、みんなを助ける力強さに満ちたアンパンマンは、幼少期における同一化の登竜門としてかなり有用といって差し支えないですね」(杉山氏)
今回話題になったツイート投稿者の夫は、アンパンマンと自己を同一化している部分があったのだろうか。
「もちろん完全に同一化はしていないでしょうが、心の根っこの部分でアンパンマンと自分を比較して、彼に倣うように行動しがちということなのかもしれません。ちなみにこういった同一化は、映画や本といったその他のエンタメ作品、また実際に身近にいる人間など、無数の存在が対象になるものです」(杉山氏)
先の「社会的排斥リスクのモニタリング」と『アンパンマン』、両者は具体的にどのような影響関係にあるのだろうか。
「アンパンマンはとても道徳的な存在、つまり『社会的排斥リスク』から縁遠い存在です。ですから、仮にこのツイート主の夫がアンパンマンを根源的な行動規範にしていた場合、何が幸せにつながり何が尊ぶべき行為なのかを、エンタメから楽しんで無理なく吸収していったのでしょう」(杉山氏)
今回のツイートへのリプライや引用には、“幼少期にアニメなどのエンタメに触れることを禁止されると、モラハラ人間になる”といった指摘もあった。
「楽しんで無理なく吸収していく、という行為は、人格形成にとって非常に大切です。人間は、これはやっちゃダメ!と行動を禁止されるとストレスホルモンが分泌され、同時にそれが原因で記憶に深く残る『心理的リアクタンス』と呼ばれる反応を見せてしまいます。これは、禁止された行為への固着や禁止してきた行為を模倣することにつながり、大人になったときに爆発して、いわゆるモラルハラスメントなどを起こしがちなのです。
こうした抑圧からくる危険を避けて人格を育ててくれるのが、楽しんで吸収するという行為。『アンパンマン』のようなエンタメは、いわば情報を無理なく吸収させるオブラートのような存在といえますね」(杉山氏)
最後に、杉山氏はアニメを観せておくなど、ある種のほったらかし教育が注目される昨今の育児事情において、極論に走らないことの重要性を教えてくれた。
「ほったらかしと言っても、子供が孤独を感じてしまうレベルは虐待です。逆に、子どもにはアニメなど観せずいつも目をかけるべき、と旧態依然に締め付けるのも、先に言った『心理的リアクタンス』を誘発します。
何事もバランスが大事ということです。ツイート主の夫は“ほったらかされていた”と語られていますが、それはあくまで当時の価値観で言えばの話で、おそらく現代の価値観で見れば、バランスよく自由やエンタメを与えられ育てられていたのではないでしょうか」(杉山氏)
杉山氏は「はじめて子育てをする親はいわば“教育の素人”。そういう人ほど早とちりせず、教育コンサルタントや保育士といった教育のプロの手を借りるべき」とも語ってくれた。メンタルに好影響を与えるエンタメ作品などを上手に取り入れ、他者と協力して子育てをしていくことが肝要なのかもしれない。
(文=A4studio)