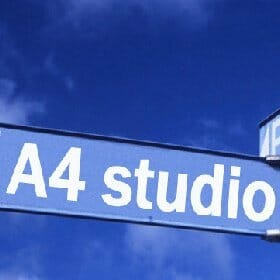昨年12月13日に「PRESIDENT Online」に掲載された、拓殖大学准教授の佐藤一磨氏による記事「『弟がいる長女は文系を選びやすく収入が低い』きょうだいの組み合わせが人生に及ぼす意外な影響」が大きな反響を呼んだ。
要約すると、兄弟姉妹の組み合わせが子どもたちの人生に大きな影響をもたらすというもので、なかでも長女・弟の関係の場合、長女は収入が低くなるといった負の影響“ブラザーペナルティ”の現象が起こり得るといった内容である。
この記事に対して「当たってる」「理屈はわからないでもない」「“ブラザーペナルティ”なんて言われる弟がかわいそうすぎる」「家庭内でのジェンダーってそこまで影響するか?」など、さまざまな声が集まり、ちょっとした議論を呼んでいた。
記事で説明されているように、きょうだいの組み合わせが人生に影響を及ぼすことは実際にあるのだろうか。そこで今回は『女子学生はなぜ就活で騙されるのか』(朝日新書)、『就活のワナ』(講談社プラスアルファ新書)を著書にもつ、大学ジャーナリスト・石渡嶺司氏に話を聞いた。
長女は進路選択の際に母親の影響を強く受ける?
まず、きょうだいの組み合わせが人生に影響を及ぼすことはあるのだろうか。
「私は佐藤氏の指摘どおりだと思います。特に長女・弟の組み合わせほど、男性=仕事、女性=家事育児という影響が出てしまうというのも当たっているのではないでしょうか」(石渡氏)
姉と弟の間でジェンダーによる差が生まれてしまうのには、時代的な背景も影響しているという。
「文部科学省の『学校基本調査』に基づいて4年制大学への進学率を男女別に見ていくと、男子は1971年に30%に到達しているのですが、この当時、女子はわずか8%ほど。2000年に男子の4年制大学進学率が約48%と半数近くを占めるようになった段階で、初めて女子も30%を超えました。それに対して、短大の進学率を見てみると、男子の進学率は1954年から現在に至るまで、3%を超えたことがありませんが、女子は1969年に10%台に到達、1994年には約25%と昔からかなり割合が高いのです。
このデータから、2000年代以前の女子の高卒後の学歴は短大か専門学校が中心だとわかるので、世代的に多くの母親の学歴は、短大ないし専門学校卒、あるいは高卒といえるはず。そして自分自身の学歴から、娘にもそこまで高い学歴は求めなくなりがちでしょう。特に、長女・弟という組み合わせだと、同性である長女と母親はどうしても結びつきが強くなります。長女はその母親の影響を強く受けますので、無理に大学に進学しなくてもいいかと考える傾向が強くなってしまうのは、充分あり得る話です」
続いて職業面に関しても深掘りしていこう。「PRESIDENT」の記事で、弟がいる長女は「職業面では男性よりも女性比率が高い職種を選びやすい可能性があります」と記載されている。
「2000年代以前だと女性が少ない職場では、女性差別が起きやすいというイメージがかなり強くありました。2000年代以前の企業では、基本的に女性社員=一般職・補助職。1985年に男女雇用機会均等法が制定されて、女子も総合職として入社できるようになっても、どう育成すればいいのかわからないという企業が非常に多かったのです。このイメージを強く持つ母親が、女性社員の多い職業や業界を娘に勧めたのが影響したという可能性はありますね」
時代の変遷で薄れゆく“ブラザーペナルティ”
これまでの話を踏まえると、2000年代以降に進路選択をしてきた若い世代が親世代へ移行する頃には、また状況が変わってくる可能性があるということだろうか。
「もちろん、その可能性は高いでしょう。4年制大学の女子の進学率は18年に50%を超えています。具体的にいうと、男子が56.3%に対して女子が50.1%です。また、社会全体で見ても徐々に高学歴化が進んでいますよね。年を追うごとに大卒の母親は増えていますから、それを考えると“ブラザーペナルティ”は徐々に縮小していくと考えられます」
しかし、地方では固定観念が強く根付いていることも少なくなく、都市部よりも“ブラザーペナルティ”による影響が大きいことも考えられるという。
「都市部では大卒の母親が増えていますし、誰しも社会全体の高学歴化、IT・情報化を肌で感じています。こうなると2000年代以前のように、母親が自分の娘に対して高学歴を望まないという考えは徐々に減少していきますよね。今後の社会を生き抜いていくためには、学費が大変だったとしても高学歴でなければならない。そのため都市部での“ブラザーペナルティ”は縮小しつつあると思います。
一方で、地方の女子学生の4年制大学進学率はそこまで高くありません。かつ、地方のほうが保守的な発想に立つ傾向が強いため、男は仕事、女は家事という価値観を持つ方がまだまだ多い。そうなると、地方では“ブラザーペナルティ”による影響は少なくないかもしれませんね。
今回の『PRESIDENT』の記事も、全体の内容としては間違ってはいないと思います。ただ、先に述べたように“ブラザーペナルティ”による影響の大きさは、都市部と地方で違ってくるのではないでしょうか。また、2000年代以前以後という観点で考えると、今後“ブラザーペナルティ”はさらに縮小していく可能性が高いと考えられるでしょう」
最後に、日本に残る“ブラザーペナルティ”の考え方に対して、今後我々はどう向き合っていく必要があるのかを聞いた。
「日本の会社員平均年収というのは先進国のなかでは唯一上がっておらず、むしろ微減しています。男は仕事、女は家庭という発想が成立するためには、前提として男のほうが稼がなければならない。ですが今ではその前提すら成り立たないのです。であれば、男性も女性も正社員で、結婚して出産期を迎えても一時的に産休・育休をとって復職するという共働きの形が、増加していく可能性が高いでしょう。
女子だから大学に進学しなくてもいいという考えのうえで、自分の娘に進学や就職の話をする時代ではなくなっているのです。就職キャリアの構造が大きく変化しているということを踏まえた意識変革が求められるのではないでしょうか」(石渡氏)
男女が平等に活躍できる時代へ移り変わりつつあるとはいえ、未だに人々の間で性別役割分業意識が存在している地域もある。この意識をいかに解消できるかが今後重要になってくるだろう。
(文・取材=海老エリカ/A4studio)