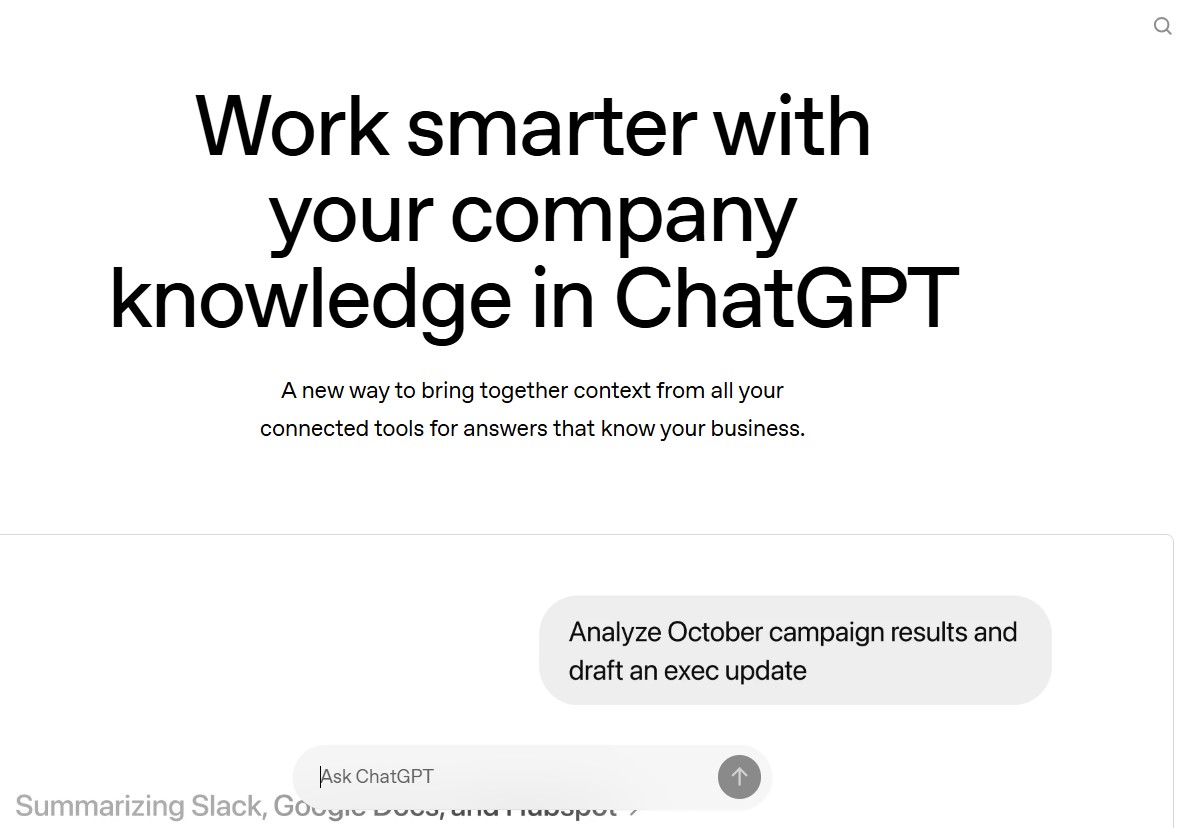
●この記事のポイント
・ChatGPTの「Company Knowledge」は社内データをAIが理解・活用する仕組みで、検索の手間を省き生産性と業務品質を大幅に向上させる。
・一方で、機密情報漏洩や誤情報の拡散、AIへの過信といったリスクも大きく、ガバナンスとAIリテラシーが不可欠となる。
・AIが社内の知を統合し「賢い同僚」として機能する時代が到来。知識管理のあり方が「探す」から「届ける」へと変わろうとしている。
2025年、生成AIの進化は新たな段階に入った。単なる文章生成や質問応答の枠を超え、企業内部の知識そのものを理解・活用するAIが現実化している。その中心にあるのが、OpenAIが提供する「Company Knowledge」機能だ。
ChatGPTをはじめとする生成AIは、すでに多くの企業で業務効率化やアイデア創出に使われている。しかし、その多くは「外部の一般知識」に基づいた回答にとどまっていた。
「Company Knowledge」は、そのAIに企業固有の情報を学ばせる仕組みを提供する。社内の議事録、マニュアル、ナレッジベース、チャットログ、プロジェクト資料などを接続することで、AIがその企業ならではの知識に基づいて回答できるようになるのだ。
では、この仕組みはどのような変化をもたらすのか。そして、どのようなリスクが潜むのか。
●目次
生産性を根底から変える「検索の終焉」
これまで、社員が必要な情報を探すには社内Wikiやクラウドドライブを横断検索し、数分から数十分を費やすのが当たり前だった。
だが「Company Knowledge」を使えば、ChatGPTに「前回の製品発表のプレス対応マニュアルを教えて」「A社との契約更新手順は?」と尋ねるだけで、即座に正確な情報を得られる。
「この“検索不要”の構造は、情報探索に費やしていた膨大な時間を解放することになります。特にナレッジが分散しがちな大企業や、リモートワーク環境では効果が顕著でしょう。社員がAIに自然言語で質問し、必要な情報を即座に得る。これは、インターネット検索の次に訪れる『社内情報検索の終焉』とも呼べる変化です」(ITジャーナリスト・小平貴裕氏)
AIが企業特有の知識を理解するということは、単に「早く答える」だけでなく、「より正しく、より一貫した判断を下せる」ことを意味する。
「意思決定の前提となる情報を常に最新・正確に保つことで、属人的な判断を減らし、組織全体のアウトプットの品質を底上げする効果が期待できます」(同)
また、新入社員や異動者の教育にも有効だ。社内ルールや業務プロセスをAIが理解しているため、「この業務の流れを説明して」と聞くだけで、AIが最適な手順を提示してくれる。研修資料を読むよりも、AIに“質問しながら学ぶ”ほうが圧倒的に早く、実践的だ。
「知識のブラックボックス」を解体する
もう一つの大きな効用が、知識の偏在解消だ。日本企業では長年、熟練社員のノウハウが属人化し、共有が進まないことが生産性のボトルネックとされてきた。
「Company Knowledgeの導入により、チャットや報告書、議事録といった“非構造的情報”がAIの知識として再利用可能になります。これにより、『誰が知っているか』ではなく、『組織が知っているか』という構造へ転換するわけです。AIがナレッジを橋渡しすることで、ベテランと若手の知識格差が縮まり、全社の知的基盤が強化されます」(同)
言い換えれば、AIが“企業の記憶”を再構築するのだ。
一方で、この仕組みは強力であるがゆえに、リスクも大きい。
「第一に挙げられるのは、機密情報漏洩のリスクです。AIが接続するデータには、顧客情報や社外秘の戦略、取引条件などが含まれる可能性があります。OpenAIや各AIベンダーは、企業専用環境やデータ分離を強調していますが、接続設定やアクセス権限の管理を誤れば、情報流出のリスクは残ります。特に、『誰が』『どの情報に』アクセスできるかを厳格に管理しなければ、AI経由で機密情報が思わぬ形で再利用される危険もあります。
第二に、情報の正確性とガバナンスの問題です。AIは学習データの内容に忠実ですが、古い資料や矛盾する情報が含まれていれば、それをもとに誤った回答(ハルシネーション)を出します。そのため、AI導入後も『情報の鮮度』『レビュー体制』『出典の明示』といったガバナンス整備が不可欠です。
そして第三に、AIへの過信です。AIが正確そうに見える回答を出すことで、社員が最終確認を怠る可能性があります。『AIがそう言っていたから』という理由で誤った判断が下される危険は、むしろ人間側の油断から生まれます」(同)
AIは「答える装置」から「考える同僚」へ
Company Knowledgeは単なる機能拡張ではなく、人間とAIの関係性そのものを変える技術だ。従来、AIは「社外の知識」をもとに一般的な回答をする存在だった。しかし、企業固有のナレッジにアクセスできるようになることで、AIは組織の文脈を理解する“内部の知性”へと進化する。
たとえば、マーケティング担当者が「昨年のキャンペーンと同様の施策を提案して」と言えば、AIは過去の資料や議事録を参照し、社内基準に即した提案を返す。これは、もはや「検索ツール」ではなく、「社内の賢い同僚」と呼ぶべき存在だ。
この方向性は、AIを“企業のOS”として活用する構想と重なる。意思決定、教育、ナレッジ共有──すべての知的活動を支えるプラットフォームとしてのAI。その未来の入口に立っているのが、Company Knowledgeだといえる。
「現状では、Google DriveやSlack、Notionなどのクラウドストレージが主要な接続対象ですが、今後はさらに多様な基幹システムとの統合が進むでしょう。ERP(基幹業務システム)やCRM(顧客管理システム)と連携すれば、AIは財務データや顧客履歴を踏まえた助言も行えるようになります。
たとえば、経理担当者が『今期の売上傾向を分析して』と尋ねれば、AIが会計データを参照してリアルタイムに回答。営業担当者が『A社の契約更新リスクを評価して』と言えば、過去の交渉履歴や売上推移をもとに提案を返すという光景が、現実のものとなり得るのです」(同)
つまり、AIが「知識を検索する存在」から「企業活動を伴走する存在」へと変わる時代が始まっているのだ。
ナレッジマネジメントのパラダイムシフト
この変化は、単に技術的進歩ではなく、知識管理そのもののパラダイムシフトを意味する。
これまでのナレッジマネジメントは、「情報を集め、整理し、分類しておく」ことが中心だった。
しかし、AIが介在する世界では、「必要なときに、AIが自動で最も関連性の高い知識を引き出す」ことが主流になる。社員はデータベースを探す必要がなく、AIが代わりに“最適解”を提示する。
つまり、「人が知識を探す」時代から、「AIが知識を届ける」時代への転換だ。これは、企業の知的生産性の構造そのものを変える。
とはいえ、技術の進歩だけでは未来は拓けない。AIが社内知識を扱う以上、情報の扱い方、責任の所在、倫理的判断を含めた人間側の統治(ガバナンス)が重要になる。その中心にあるのが「AIリテラシー」だ。
AIが万能ではないこと、情報の正確性や偏りを常に検証する姿勢を組織全体で共有する必要がある。また、誰がどの情報にアクセスできるか、どのように更新されているかを可視化する仕組みも欠かせない。
AIを恐れるのではなく、“信頼できる知的基盤”として育てる姿勢が企業に問われている。
Company Knowledgeが示すのは、単なるツールの進化ではない。それは、企業という“知の集合体”の在り方を根本から変える可能性を秘めている。情報が人から人へと渡るのではなく、AIを介して常に最適化され、全員が同じ知のレベルに立てる。そんな世界が、すぐそこにある。
だが同時に、その力は「扱い方次第」で善にも悪にも転じる。AIが企業の知を拡張する未来を迎えるために、必要なのはテクノロジーではなく、人間の知恵と覚悟なのかもしれない。
(文=BUSINESS JOURNAL編集部)



