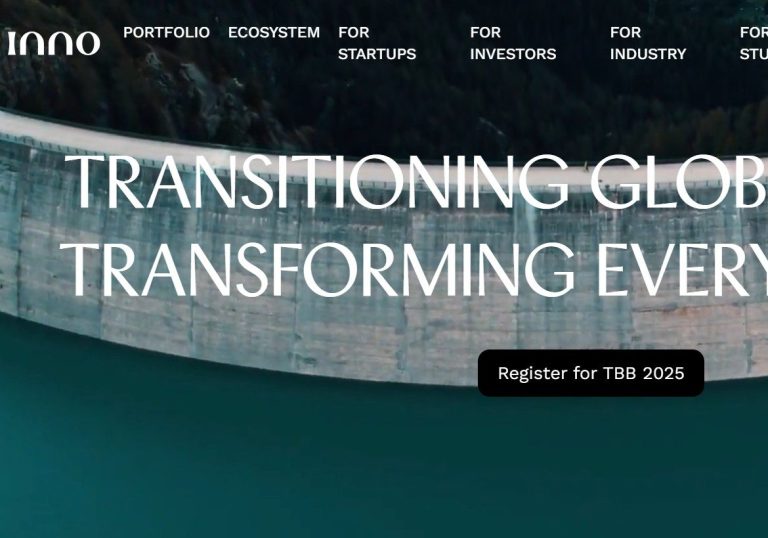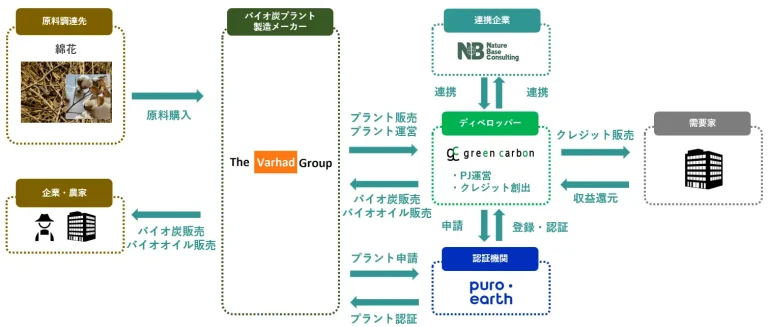●この記事のポイント
・理研などの国際共同研究チームは、海水中などで溶ける「超分子プラスチック」の開発に成功
・環境汚染や人体への悪影響が問題となっているマイクロプラスチックが生じない
・他のプラスチックは共存する中でも水平リサイクルが可能
・食品添加物や農業用途に広く用いられている安価な原料から製造
理化学研究所(理研)などの国際共同研究チームは、海水中などで溶ける新たなプラスチック「超分子プラスチック」の開発に成功した。容易に原料にまで解離し、生化学的に代謝されるため、環境汚染や人体への悪影響が問題となっているマイクロプラスチックが生じない。世界で年間4億トン以上生産されるプラスチックは、リサイクルされているのは9%以下であり、残りは燃焼・廃棄されている。燃焼に伴い温室効果ガスが発生し、化石資源由来であるため回収・分類・分解・再利用などで多大なエネルギーを要する。一方、超分子プラスチックは食品添加物や農業用途に広く用いられている安価な生化学的な物質代謝を受ける2種類のイオン性モノマーを用い、モノマーによっては難燃性で温室効果ガスを出さず、遺伝毒性も持たない。土壌の上に置いておけば土壌に吸収される。成形加工性、耐熱性、高い力学特性など、従来のプラスチックに匹敵、あるいはそれらをしのぐ性能を備えているため、従来のプラスチックの代替材料として期待される。「夢の新素材」の特徴、想定される用途、そして実用化に向けた動きについて、理研 創発物性科学研究センター 創発ソフトマター機能研究グループ グループディレクターで東京大学卓越教授の相田卓三氏に話を聞いた。
世界ではプラスチックの使用に制約
研究チームは、生化学的な物質代謝を受ける2種類のイオン性モノマーを室温の水中で混合した。水素結合で強化された静電相互作用(塩橋)により2種類の原料が互いに接着し、架橋構造体を形成すると同時に、この混合物は上相と下相に相分離を起こす。上相(水相)はモノマーの無機対イオンを取り込み(脱塩)、下相は塩橋によって生成した架橋構造体がつくる凝縮相である。この相分離により、架橋構造が安定化して、塩を外部から添加しない限り、架橋構造体から原料への解離ができなくなる。この凝縮相を分離して乾燥させると、無色透明で超高密度のガラス状超分子プラスチックがほぼ定量的に得られることを発見した。
超分子プラスチックは、堅固でありながら、モノマーによっては加熱により容易に成型加工することができ、複雑な形もつくれ、既存のプラスチックと遜色がない物性が確認された。一方、塩水に入れると、原料モノマーにまで速やかに解離し、バクテリアなどによる生化学的な物質代謝が可能となるので、マイクロプラスチックを形成しない。原料モノマーの一つのヘキサメタリン酸ナトリウムは、食品添加物や農業用途に広く用いられているうえに安価。もう一つの原料モノマーである硫酸グアニジニウムの一部は天然由来のアミンから合成することができ、両原料モノマーに含まれているリンや窒素は肥料として重要だ。
今回、超分子プラスチックの開発に取り組むに至った背景について、相田教授は次のように説明する。
「世界では『サステナビリティ(持続可能性)』が共通のキーワードになっており、温室効果ガス排出やマイクロプラスチックの問題から、欧州ではプラスチックの使用にさまざまな制約が出てきています。マイクロプラスチックはヒトの体内に蓄積されて、脳に達するとアルツハイマー型認知症の原因になるとも近年では指摘されています。世界では毎年、大量のプラスチックが製造され、一部が海洋に廃棄されており、欧州では規制の動きが強まる一方で新興国では安価なプラスチックへの需要が増加しており、今後も世界における製造量は大きく伸長していくと予想されています。
こうした環境問題を未来の子どもたちに残してよいのか、ということが、科学者にとっても世界にとっても非常に大きな問題になっているわけです。そこで我々は新しいプラスチックの開発に取り組み、昨年11月に『サイエンス誌』に発表しました」
“鍵が開く”ようにして原料モノマーに戻す
そもそもの発想の起点は何だったのか。
「プラスチックはモノマー同士の結合が半永久的で壊れないということになっていますが、もしこの結合を可逆的、リバーシブルにしたらどうなるのか。プラスチックは容易にモノマーに戻せるようになりますが、力学的に弱いプラスチックしか得られないでしょう。結合の可逆性に鍵をかけ、プラスチックに十分な強度を維持させながら、必要に応じて鍵を開け、モノマー分子に戻せるようにすれば、物質代謝がおこるようになり、問題が解決するはずだと考えました。モノマーが炭素を含まなければ、温室効果ガスである二酸化炭素を排出することもありません」(相田教授)
リサイクルに伴うプラスチックの弱点も解決するという。
「従来のプラスチックは無限にリサイクルできるわけではありません。なぜかというと、リサイクルの工程で原料にまで戻しているわけではなく、粉々に砕いて溶かして成型しているためです。例えばリサイクルしてポリエチレンの白い容器をつくった場合、最初の強度は出ません。一方、超分子プラスチックは原料モノマーにまで戻す(水平リサイクル)ことが可能ですので、毎回100%新品のプラスチックをつくることができます」(相田教授)。
海外の企業から大きな反響
どのような用途が想定されるのか。
「できればパッケージングなど、廃プラスチック問題の原因になっている部分に使えるように磨き込んでいきたいと思っています。廃プラスチック問題を少しでも軽減できれば本望です。世界の耕作地の3分の1は農業ができない土壌になっているのですが、肥料に使われているモノマーからできた超分子プラスチックは、農業用地の拡大に貢献できるかもしれません。いずれにせよ、従来とは全く違った価値観で考える必要があります。プラスチックが発明されてから約100年がたち、改良が重ねられ低コストで製造できるようになったことで、業界全体がコンサバティブになっており、マイクロプラスチックのような問題が発生しても“現状を変えたくない”という力が働きます。ですが、特に欧州などでは環境負荷低減に関する基準を守らなければ企業はビジネスを展開できないという状況になりつつあり、企業が本気で取り組む必要に迫られています。
全く表面を加工せずに使うと、汗が垂れただけで溶けてしまうということが起こりえるかもしれませんが、今のプラスチックを100%、超分子プラスチックに置き換えるのは容易ではないと思います。塩水に触れない環境で利用されるプラスチックも多々あります。建築素材やインテリア、壁の中に入っているものなどですね。ラミネーションやコーティングをせずにそのまま使える用途も少なくないと考えています。現在はできるだけ種類を増やし、触り心地の改良などを含め、多様なニーズに応えられるように努力をしています」(相田教授)
気になるのが、実用化に向けたロードマップだ。
「日本よりも海外の企業からの反響が大きく、大小80社ほどから問い合わせがありました。大手の海外ベンチャーキャピタルなども興味を示しています。我々自身が製造会社を作るというかたちではなく、製造技術を有する企業と提携してプロモーションするかたちを想定しています。実用化が始まるメドとしては、個人的には3年後くらいかなというイメージを描いています」(相田教授)
(文=BUSINESS JOURNAL編集部、協力=相田卓三/東京大学卓越教授)