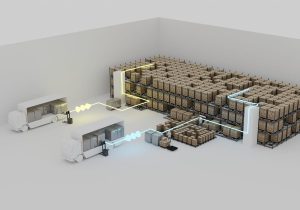OpenAI、営利企業化を断念の裏に巧妙な生存戦略?両方のメリット確保
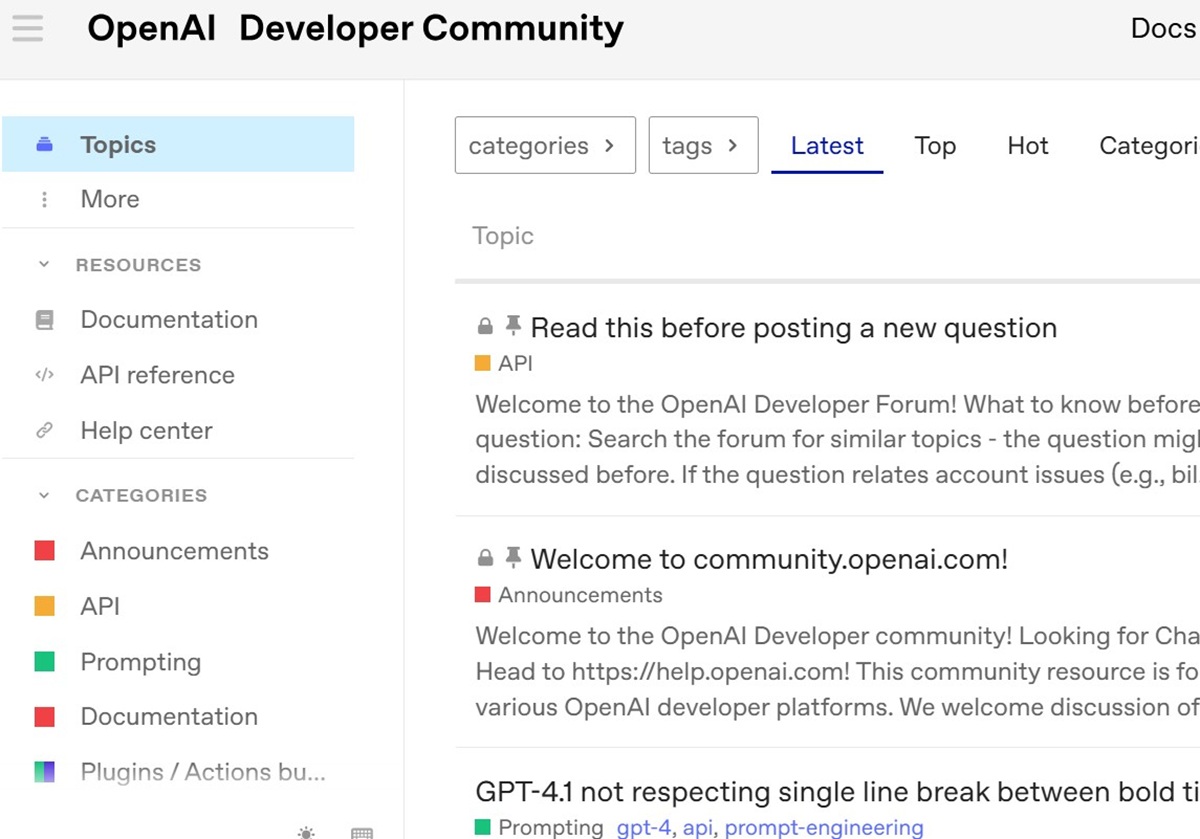
●この記事のポイント
・米OpenAIは営利企業への転換を断念。同社は現在、NPOのOpenAI Incが、営利企業であるOpenAI LLCを支配・管理するという特殊な組織構造
・大企業と真っ向勝負しなくて済む立ち位置を確保し、独自のスタンスを貫き差別化を図れる
・AIのオープン化の波が強まるなか、営利企業化にはリスクも
米OpenAIは今月5日、営利企業への転換を断念すると発表した。同社は現在、NPOのOpenAI Incが、営利企業であるOpenAI LLCを支配・管理するという特殊な組織構造になっており、2024年12月には、後者をPBC(パブリック・ベネフィット・コーポレーション)と呼ばれる公益重視の営利企業に移行し、NPOの支配下から外す方針を示していたが、営利企業のPBCへの移行は進める一方、引き続きNPOが支配する形態をとることになった。3月にはOpenAIはソフトバンクグループ(SBG)などから400億ドル(約6兆円)の出資を受けることで合意し、OpenAIが年内に営利企業化しない場合は出資額が200億ドルに減額される条項が含まれていたため、OpenAIの営利企業化をめぐる動向が注目されていた。なぜOpenAIは巨額の資金調達をする一方で、非営利企業が営利企業を支配するという形態を維持するのか。その目的や背景について、識者の見解を交えて追ってみたい。
●目次
社内に営利企業化を危惧する声
もともとOpenAIは2015年にNPOとして創業。19年から米マイクロソフトから累計約2兆円もの出資を受けたことで一躍、世界的に大きな注目を浴びる存在となり、22年には生成AIの「Chat GPT」を公開。その翌年にはサム・アルトマンCEOがNPOの理事会によって一時解任されるという騒動が起きたが、アルトマン氏が営利企業化を進めることに内部で強い反発があったことが背景にあるとされる。
そして今回、組織全体として完全な営利企業への転換をしないと判断したわけだが、その理由はなんなのか。AI開発者で東京大学生産技術研究所特任教授の三宅陽一郎氏はいう。
「OpenAIはもともと非営利団体として『全人類への奉仕』を旨として立ち上がった組織であり、以前は言語AIだけではなくて、ゲームをはじめさまざまな分野のAIを開発していました。そのなかで言語AIが大きく成長したという経緯があります。GPTも2までは誰もがフリーで使える形でしたが、マイクロソフトなどから資金が入り始めて営利企業化していきました。GPT3以降は明確に有料化していきます。そして今回の決定によって、営利企業と非利益企業の両方からなる体制でやっていくとうことで、一応は筋を通したというかたちではないでしょうか。NPOだからといって収入があってはいけないわけではなく、もともと大規模言語モデルの開発には莫大な予算がかかるために、その資金集めに奔走していたOpenAIは、市場に参入せざるを得なかった、という経緯があります。
もう一つの要因としては、完全に営利企業化してしまうと自社の技術が完全に産業に取り込まれてしまい、それが社会的に負の方向に働いてしまうのではないかという危惧が、同社のなかに社風としてあるかと思います。『持続可能な社会』はAI分野においても懸案事項であり、AIの急速な発展と社会の発展や精度の拡充の歩調を合わせなければなりません。同社内には『AIの安全性をきちんと考慮するべき』という考えがあります。同社が創業されたときの起点は『ノンプロフィットで社会に奉仕する』というところであり、アルトマン自身も人間の総合的知能を超えるようなAGI(人工汎用知能)が普及するかもしれないと言っていますから、NPOを持ち続けることで完全な営利企業化に歯止めをかける自由度を持ち続ける』という決断に見えます」
営利企業とNPOの両方のスタンスを取れる
今回の決定には、OpenAIの生き残り戦略的な意味合いもあるという。
「外部企業から多額の出資を受けると、『OpenAIがそれらの会社のものになってしまう』可能性が生じますが、引き続き非営利企業という体制を維持することで、うまくそれを回避したと思います。現在ではグーグルやメタなどのGAFAMも生成AI開発に注力しており、企業規模的には、はるかに小さなOpenAIが、そうした大企業と長期的に対抗して行くには、大企業と真っ向勝負しなくて済む立ち位置を確保し、独自のスタンスを貫くほうが差別化もでき、小さい組織で継続していくための生存戦略もあるでしょう。営利企業であることを完全にやめるわけではなく、営利企業とNPOの両方のスタンスが取れますし、買収されにくいというメリットもあるかと思います。
またノーベル賞受賞者であり現代のAIの立役者であるジェフリー・ヒントンや故ステファン・ホーキング博士に代表されるようなAIの進化への批判と歯止めを行おうとする世論は、これからなおいっそうAI倫理として盛り上がっていきます。そういった世の中の風潮の中で、NPOのスタンスを保ち続けることは、むしろそういった世論の側に立つことを意味します。そうすることで、他の企業には真似できない有利でユニークな立場を確保することにつながります」(三宅氏)
AIの世界におけるオープン化の波も背景にはあるという。
「ソフトウェア開発の世界では、昔から『その一部や全部を世の中に公開するオープン戦略によるコミュニティ開発』と『クローズ戦略を取った営利企業による独自開発』という対照的な図式があります。たとえば、オペレーティングシステム『Linux』に代表されるように『全部オープン化』して広く世の中からコントリビューターを集める文化が90年代から長く存在します。オープンだからといって営利企業がないわけではなく、『Linux』をパッケージングしてサービスを提供する会社は存在します。ライセンス上開示義務を持ちながらも、オープンコミュニティに貢献しつつ。自社の利益を追求することもオープン戦略では可能なのです。Webブラウザー『Firefox』などもその典型です。『オープン・イノベーション開発』『オープン・イノベーション戦略』とも呼ばれます。
そして今、言語AIの世界にもオープン化の波が来ています。オープン戦略は世界中の開発者が自発的に開発してくれるので、オープン戦略に対して営利企業のクローズドな戦略が不利になる場合もあります。なぜならオープンというのはフリー(無料)も意味するので、品質さえよければあっという間にシェアを取ってしまえるからです。問題はメンテナンス性です。そうした情勢のなかで完全に営利企業になるというのは、逆にOpenAIにとってはリスクを取る選択であるわけです。 非営利企業であれば『古いソースは公開しますよ』という決断をしやすいですが、株式会社だと株主をはじめとする多くのステークホルダーとの知的財産権の調整も必要になり、ハードルは高くなってきます。『NPOだから公開するんですよ。公益に資すんですよ』といえるのは、オープン戦略的に非常にいい立ち位置ではあります」(三宅氏)
(文=BUSINESS JOURNAL編集部、協力=三宅陽一郎/AI開発者、東京大学生産技術研究所特任教授)