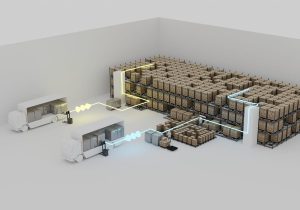迷走する日本のスタートアップ、お金も支援もあるのになぜ?その本質的課題とは

●この記事のポイント
・スタートアップが市民権を得る一方で、凡庸化や閉鎖的「界隈化」も進行。挑戦者精神の再確認が必要だと伊藤信雄氏は語る。
・スモールIPO難や資金過多の副作用を経て、M&Aやソリッドベンチャーなど多様な成長モデルが台頭。
・AI時代にビジネス構造が変化するなか、「まずは稼ぐ」「良いネットワークを持つ」など原点回帰の重要性を強調する。
かつて一部の“異端児”の領域だったスタートアップが、いまや行政も大企業も支援する「社会の表舞台の存在」になった。
だが、その一方で「キラキラ化」「スタートアップ村(の閉鎖性)」といった批判的な視線もある。テンキューブ株式会社代表で、資金調達面などで多くの起業家を支援してきた伊藤信雄氏は、「スタートアップが当たり前になったからこそ、改めて“挑戦者精神”をアップデートする必要がある」と語る。
●目次
- 「市民権を得た」スタートアップの光と影
- 「界隈化」するエコシステムの危うさ
- 「一人でもやり抜く」人間の底力
- スモールIPO難の時代に変わる「出口戦略」
- 「ソリッドベンチャー」の台頭とポジティブな変化
- スタートアップと中小企業の境界を越えて
- ユニコーンだけが成功ではない
- 生成AIがスタートアップの定義を変える
「市民権を得た」スタートアップの光と影
「10年前は、スタートアップといえば“端っこの人たちの世界”だった。でもいまは大企業も行政も巻き込み、日が当たる存在になった。これは本当にポジティブなことです」
伊藤氏はこう語る。
日本のスタートアップ・エコシステムはこの10年で大きく変貌した。起業家、投資家、行政、支援者が連携し、社会的な認知も飛躍的に高まった。その一方で、「スタートアップと名乗れば誰でもそう見なされる」といった側面も見逃せない。
「本来少数の“挑戦者”だった人たちが、いつの間にか“当たり前の存在”になっている。その分、挑戦の泥臭さや、歯を食いしばって地道な作業を続ける面が見落とされるようにも感じます」
「界隈化」するエコシステムの危うさ
伊藤氏は、「スタートアップ界隈」という言葉に象徴される“閉じた空気”にも警鐘を鳴らす。
「エコシステムは本来、起業家を支えるための“応援団”の集まりのはずなんです。投資家も支援者も行政も、同じ方向を向いていた。でも顔ぶれが固定化して、外から見えにくくなっていないか。仲間内で盛り上がっているだけでは、仲間の“外”にいるスタートアップを社会につなぐ役割を失ってしまう危険があります」
かつては“アウトサイダー”として始まったスタートアップが、いつの間にか“内輪の世界”になっていないか。
「外の人が入ってこられない」「自分たちだけで回っている」と見られるようになれば、エコシステムは社会的信頼を失いかねない――。その危機感が、伊藤氏の根底にある。
「一人でもやり抜く」人間の底力
伊藤氏の言葉の背景には、支援してきた数多くの起業家の姿がある。
「スタッフが全員辞めて社長一人になっても、数年後に数十億円の売上を出すような人を複数、見てきました。あの“人間の底力”こそスタートアップの本質です。他人の評価やSNSの空気ではなく、“やり抜く力”にこそ価値がある。それを揶揄したり“ブラック”の一言で片付ける風潮があるなら、それこそが危ういと思います」
スタートアップとは、表面的な華やかさではなく「逆境の中で挑戦を続ける意思」に宿るものだ。その原点を、スタートアップが定着した今の時代だからこそ、思い出すべきだと伊藤氏は強調する。
スモールIPO難の時代に変わる「出口戦略」
近年、東京証券取引所がスモールIPOに対する基準を厳格化したことで、「上場ゴール」と呼ばれる動きが難しくなっている。
「以前は『とりあえずIPOを目指す』しかなかった。でも今は“上場したあと、どう成長するか”まで問われている。結果、起業家も投資家も、より真剣に事業の持続性を考えるようになりました」
IPO一択から、M&Aやセカンダリーマーケットの活用へ――。「売却=敗北・撤退」ではなく、「次の挑戦への合理的な選択肢」として評価されつつある。伊藤氏はこれを「健全な多様化」と捉えている。
一方で、コロナ以降の金融緩和やスタートアップ支援政策により、資金調達環境は好転した。
しかし、それが「副作用」も生んでいないかと伊藤氏は指摘する。
「シード段階から投資家も資金量も層が厚くなり、詰めの甘いまま多額のエクイティをまず狙いにいってしまうようなケースも散見される。本来は希薄化やデットとの併用を意識すべきなのに、ダウンラウンド(株価の低下)で苦しむ企業も少なくない。“調達して、赤字を掘っての成長ありき”ではなく、“しっかり事業を作りながら資本政策をどう組んでいくか”が問われるフェーズに来ています」
「ソリッドベンチャー」の台頭とポジティブな変化
そんななかで注目されるのが、“非・急成長型”のスタートアップ――いわゆる「ソリッドベンチャー」だ。堅実なキャッシュフローを重視し、自己資金や融資を活用して成長する企業群である。
「これは非常にポジティブな流れです。昔からある中小企業とやっていることは、外見上は変わらないけれど、“自分たちは社会を変える”という意思を持って挑むのがスタートアップ。ユニコーンだけが正義じゃない。成長カーブは多少ゆるくとも、強い企業をつくる行き方が、見直されてきていると思います」
スタートアップと中小企業の境界を越えて
では、「スタートアップ」と「中小企業」の違いとは何か。伊藤氏は、「切り離す必要はない」と断言する。
「飯を食えて、社員が雇えて、税金を納めてるなら立派な経営ですよ。どちらが偉いとかじゃない。ただ、スタートアップには“社会の認識と人の行動様式を根本から変えていく力”がある。そこを本気で目指し行動しているか。そこが最大の価値」
儲けることは共通の使命。だが“世の中を変えること”にコミットするか否か――。その一点に、スタートアップの本質があるという。
今後のエコシステムに求められるのは、閉鎖的な“界隈”を超えて、社会全体のインフラとなることだ。
「東京の真ん中でキラキラしたイベントをやっても、独特のノリに外の人が入れなければ意味がない。誰でも参加できて、“自分も挑戦してみたい”と思えるコミュニティに変わること。それが、次の10年の成長に必要だと思います」
ユニコーンだけが成功ではない
伊藤氏は、ユニコーン志向以外にも多様な成功パターンがあると強調する。
「国内でドミナントな地位を築く。海外市場に直行する。あるいは、キャッシュフローを重視して堅実に育つ――。これからは、そのどれもが“正しいスタートアップの姿”になるはずです」
米国ではすでにExitの8割がM&Aによるもの。日本でも同様の構造変化が進みつつあり、それが主流になるだろうと見ている。
「IPOありきの思考を変えないと、また“オルツ事件”のような歪みを生むだけです」と、伊藤氏は冷静に語る。
生成AIがスタートアップの定義を変える
そして、生成AIの急速な進化は「スタートアップの形そのもの」を変えると伊藤氏はみる。
「生成AIを使うことがデフォルトになる、いや既にそれが前提。圧倒的なスピードとレベルの機能進化により小規模なSaaSなどは無力化されかねない。従来型の大量の資金と人を投入しながらARRを伸ばすやり方だけでは通じなくなりつつある。AI前提のビジネス構築力が問われます」
最後に、これから起業する人へのアドバイスを尋ねた。
「とにかく“1円でもいいから、まず売上を立てる”こと。イベント登壇や受賞も素晴らしいことだけれど、まずは自分の足で顧客に会い、物を売る。解は顧客との向き合いからしか生まれないから。その経験がすべての基礎になる。そして、良いネットワークに早くつながること。自分の顧客や、その顧客を直接知る人にアクセスできる環境を持つだけで、事業の成長は10倍早くなります」
最後に、エコシステム全体への提言として、伊藤氏はこう結んだ。
「行政は“お金を出すだけ”ではなく、AI時代に即した柔軟な政策を。投資家やわれわれ支援者はIPO一辺倒ではなく、M&Aやグローバル展開など多様な成長やExitを一層支え、そのために自らも高い次元で汗をかくこと。そして起業家は、“本丸の成長”を常に問い直すことに尽きます。
スタートアップは特別な存在ではない。しかし“社会を変える挑戦”であることを忘れてはいけない。市民権を得た今こそ、10年前には手探りだった挑戦のレベルを何段もアップデートできるか、試されていると思います」
伊藤信雄氏のこの言葉は、次の時代を担う起業家たちにとっての道標だ。キラキラではなく、地に足のついた挑戦――それこそが、日本のスタートアップが次の10年に向けて再び進化するための原動力になる。
(文=UNICORN JOURNAL編集部)