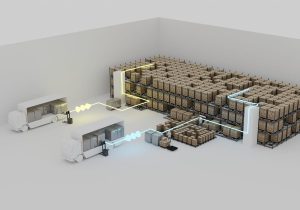スモールIPO乱立で上場維持基準の見直しも検討…M&Aが市場に変革をもたらすか

東京証券取引所が、グロース市場の上場維持基準について、「上場10年後に時価総額40億円以上」から「上場5年後に100億円以上」への引き上げを検討していると報じられ、大きな注目を浴びている。日本の市場においてIPO(新規上場)した企業は“上場ゴール”と揶揄されるように、多くが上場時の株価を下回り続けている。そもそも、IPOをするタイミングは適切なのか、疑問に思われるケースも少なくない。かねて専門家の間でも、スタートアップ企業について、「IPOを急ぎすぎるきらいがある」との指摘があがっている。
スタートアップ企業が成長して、目指す先は多くの場合、IPOだ。大手企業などに譲渡するケースもあるが、ほとんどの起業家がIPOをすべく、自社を大きく成長させようと奮闘している。そのため、IPOに至らずに会社を売却することは、ネガティブにとらえられることが少なくない。
だが、M&Aマッチングプラットフォーム「M&Aクラウド」を展開する株式会社M&Aクラウドの代表取締役CEO及川厚博氏は、M&Aはスタートアップ企業が大きく成長するための有効な手段であると語る。また、後継者不在による倒産を減らすためにも役立つという。

「M&Aは、大きく2つの分け方があります。一つは、事業承継。事業承継が進まないと、黒字経営を続ける会社が倒産する可能性が高まります。そういった後継者のいない会社を、いかに別の企業に引き取ってもらえるかというのが、事業承継型のM&A。もう一つは、スタートアップのM&A です。スタートアップが事業成長やExitのためにM&Aを選択することで、継続的なイノベーションを実現することができるようになると考えていますが、ここの市場はまだ成熟していません。
それぞれの課題を説明しますと、まず事業承継について。2025年までに中小企業・小規模事業の経営者のうち約6割(245万人)は70歳以上となり、そのうち約半数(127万社)が後継者不在とされていますが、実は約半数(60万社)が黒字経営の会社です。そのため、日本において事業承継を進めていくことは、喫緊の課題といえるでしょう。会社の財産となるブランドや社員が存在する中で、黒字のまま倒産するというのは、日本社会や経済に大きな損失を与えるため、企業の価値を理解し、承継してくれるような事業承継件数を増やす必要があります。一方で、事業承継の別の問題として、M&Aアドバイザーの人数が足りていません。さらにいうと、アドバイザーだけが人海戦術でM&Aを進めるのは生産性が低いため、根本的な解決にはなりません。この課題に対して、テクノロジーを活用して効率的にM&Aを進めようというのが、M&Aマッチングプラットフォーム『M&Aクラウド』の開発の背景です。
また、スタートアップM&Aについては、日本ではExitの手段としてM&Aを選択するスタートアップの割合が少ないことが課題の一つだと考えています。米国と日本のスタートアップにおけるExitの方法を比較すると、米国では8割がM&Aで、IPOが2割くらいですが、日本はその逆です。その比率を変えていかないと、小さい上場、いわゆるスモールIPOをする会社が日本市場に乱立してしまい、グローバルで勝てないという流れになってしまいます。
そこで、なるべくM&Aをして規模の大きい会社へ成長し、グローバルで勝てるような規模の会社を増やす必要があると考えています。スタートアップ企業が右肩上がりで増加する中、M&Aで会社を売却することは、ネガティブに捉えられる風潮が続いていました。しかし近年では、“スモールIPO”よりM&Aのほうが会社や従業員はハッピーなんじゃないか、という空気に変わってきていると感じています」

2つの課題解決のために、具体的にどのような解決策を提示しているのか。
「現在は、全部で5つの事業を展開しています。1つ目は、M&Aマッチングプラットフォーム『M&Aクラウド』。プラットフォーム上で買い手と売り手がマッチングできる仕組みを提供しています。次に、事業会社やCVCから資金調達ができる『資金調達クラウド』というサービスです。エクイティでの資金調達を検討している企業と出資を検討している企業をマッチングするプラットフォームなのですが、M&Aクラウドにあった“資金調達機能”をプロダクトとして切り出したサービスです。
スタートアップは、出資やセカンダリーをきっかけとしてM&Aに至ることが多いので、この資金調達クラウドもM&A推進に寄与するといえます。3つ目は、M&Aの専門知識や経験を持ったアドバイザーが支援に入るM&Aアドバイザリー事業の『M&A Cloud Advisory Partners(MACAP)』です。数億~数十億円程度の高度で大型なM&A案件を支援するM&A専門部隊です。4つ目は、MACAPから誕生した、スタートアップM&Aを専門に扱うチーム『Startup M&A Advisory』です。スタートアップからのニーズの増加を受け2024年に発足させました。最後は、独立したM&Aアドバイザーとエージェント契約を結ぶ『M&Aクラウド エージェント』です。弊社からシステムやオフィスを提供し、時には助言などもしながら、全国の事業承継案件を手掛けるアドバイザーを支援するサービスです。それぞれ、ターゲットや提供価値は異なりますが、M&A創出のためのサービスです」

M&Aクラウドの特徴は買い手の顔が見えること
M&Aマッチングに関するプラットフォームは他にも存在するが、競合他社との違いはどこにあるのだろうか。
「大きな特徴の一つは、買い手が掲載されているという点です。昨今、事業承継において、不適切な買い手による詐欺のようなトラブルが続出し、社会問題になっています。本来は、企業のブランドや社員といった企業の財産を引継ぎ、企業成長を目指すことを前提にM&Aをするはずなのですが、一部、不誠実な買い手が存在し、その買い手に対して、仲介業者が売り手候補企業を紹介してしまい、売り手の望まない買収が進んでしまうということが起きているのです。社会的に不安の声が出ている中、弊社のプラットーフォームでは、買い手企業へ直接取材にうかがい、社名をネット上にオープンにしているため、売り手企業にも信頼してご利用いただいています。
M&Aのビジネスモデルは、人材業界ととても近いのですが、M&A市場は超売り手市場に変わってきています。これは最近の話です。人材業界でいえば、紹介会社の倒産件数が過去最高になっていますが、求職者の仕入れコストが上がっていることで、経営を圧迫しています。M&A業界も同じように、この2年間程度で全国の中小企業経営者へ仲介業者から大量に手紙や電話によるコンタクトをした結果、売り手がすぐに売ろうと反応し、売却が進んだため、もともとM&Aに前向きだった売り手はみんなM&Aしてしまったような状態になっています。そのためこれからは、『いい買い手がいたら売ってもいいかも』と考えているような潜在層を取っていかないといけない状況になっています。
その点で当社のプラットフォームでは『〇〇社さんが御社のM&Aを検討しています』と直接プラットフォーム上でスカウトできる仕組みになっています。そのため、潜在的な売り手を見つけやすくなっています」
“潜在的な売り手”ということは、積極的に売却を検討しているわけではなく、当該会社側からシステムに登録もしていないと考えられるが、どのようにアプローチしているのだろうか。
「弊社には、買い手企業の希望する企業、すなわち『この企業をM&Aしたい』というバイネーム(指名)での買収ニーズデータが2万5000社程度あるんです。その企業に対してアドバイザーが、『M&Aクラウド』に掲載されている買い手の買収ニーズに関する掲載記事、いわゆる求人票に当たる情報、を持って売り手企業に連絡して口説くという流れです。だから基本的には、買い手なりアドバイザーなりから、売り手に交渉に行くという構図です」
売り手市場にあって、買い手がつかない会社は、どのような課題が考えられるだろうかと問うと、意外な答えが返ってきた。
「買い手がつかないということは、ほぼありません。超売り手市場であるので。むしろ、売り手がいないという状況なんです。黒字企業であれば、売りたいと希望すると、ほぼ買い手がつきます。だから、売り手は企業は強気の要望を提示しているのですよ。どんどん買い手企業が増えていて、PEファンド(プライベート・エクイティ・ファンド)も積極的に買収をしています。なかには、M&Aアドバイザーが事業会社に転職してM&A専任担当者になるなど、インハウス(企業内)だけでM&Aを完結させるような動きも高まっています。この2~ 3年で状況が大きく変わったので、『信頼できる買い手がいるのであれば売却してもいい』『これぐらいの株価がつくのであれば売却してもいい』と、売り手側の意識も変わりました」
エポックメイキングなM&Aの事例
今までに携わってきた中で、すごく面白かったマッチングや特徴的なM&Aがあるかを聞いた。
「ライドシェア事業を展開するnewmoさんが創業6カ月で、未来都さんという大阪の5番目に大きいタクシー会社をM&Aしたんですよ。スタートアップが創業間もなくして老舗企業を買収し、その瞬間に社員が数千人になるみたいなケースはこれまであまりなかったんです。そもそも、スタートアップが事業承継の買い手になるというのは、ほとんどなかったので、すごく面白かったですね。
古い産業とか既成産業とかに入っていくことは難しいですし、買収することで新規事業を立ち上げることにもなります。逆にスタートアップに買収資金が集まるということも意外なことですし、スタートアップみたいな不安定な会社にグループインするということも驚きで、エポックメイキングな事例です。今後も同じようなことが増えていく可能性はあると思います。
銀行もスタートアップに買収資金として、お金を貸す流れが来てるんですよ。しっかり金利が取れるようになっていることも大きいですね。買い手は多様化しています」
M&Aクラウド社は、顧客との距離感はどのようなスタンスを取っているのだろうか。
「M&Aでも資金調達でも結構濃淡があります。アドバイザーをつけてやる場合は、結構がっつり入ります。プラットフォームがあるので、『プラットフォームを使ってください』とお客さんに任せることもあります。」
及川氏自身、事業の立ち上げから売却に至るまで経験しているが、事業を大きくしていくためのポイントや、スタートアップでありがちな課題と解決策などあれば教えてください。
「事業が大きくなるかどうかは、その市場と競争環境の掛け算だと思うので、最初にやった事業が思ったよりもマーケットが小さかったとか、思ったより競合が強かったとか、市場は大きいけれど、このセグメントしか取れなかったみたいなことが、スタートアップの0→1(ゼロイチ)のタイミングでは結構あります。それを乗り越えるために、別の領域でプロダクトマーケットフィットをさせて、さらにセグメントを拡張するというのはあります。それができない場合は、ピボットするなり、新規事業を立ち上げたり買収するなりして、新しい手札を増やさなきゃいけないと思います。
そのときに企業経営者として難しいのは、事業の状況に応じて次々違うスキルが求められることですね。最初のゼロイチのタイミングで事業を立ち上げて、一個プロダクトを当てたときは、プロダクトマネージャーのスキルが大切です。その後、プロダクトマーケットフィットを支えるというタイミングだと、組織力が大事になりますし、また別で事業化しなければいけないとなると、ポートフォリオマネージャーみたいなことになります。どんどん全然違うスキルが経営者に求められます。そこのタイミングでみんな苦労するような気がしますね」
成長する企業の権限委譲
企業が成長していく際、権限の委譲がひとつのカギになってくるが、今までに見てきた企業で、権限委譲がうまくいくポイントはあるだろうか。
「まず、権限委譲できるような人がいること。権限委譲したとしても、実際はすべて任せられるわけではないことが多いので手を貸してしまういうことはあります。社長の気質というのもあるんですけど、権限委譲できるぐらい自分より優れている人がちゃんといるかどうかがひとつ。
もう一個は、自分がその分野をめちゃくちゃ詳しいこと。詳しいから任せられると思うんです。詳しくないまま任せてしまうと、ハンドリングできなくなってしまって、内部分裂したりします。相手に任せて、何かあったら助けられるくらいに詳しいことと、任せられる人を採用できるか、という2点だと思います。
M&Aクラウド社では、及川氏の右腕になる方とは、どのような関係性なのだろうか。
「弊社だと事業立ち上げとか、事業のフェーズによって、大きく変わってはいるのですが、最初プラットフォームを作る時は、売り手と買い手の両方を集めないといけなかったので、もう1人の創業者と役割分担をしました。売り手集めとマッチングに関しては僕がやって、買い手集めは(もう一人の代表である)前川(拓也氏)という体制で進めました。一定のタイミングで僕が(現CFOの)村上(祐也氏)と一緒に今のスタートアップM&Aの仲介事業を立ち上げました。ゼロイチを作って、渡してという感じです。あと想定外だったことは、M&Aのためのプラットフォームの中で、なぜか資金調達が自然に決まっていたことはびっくりしました。M&Aじゃなかったので『あれ?』みたいな(笑い)結果、時代のニーズを読んで『資金調達クラウド』という新しいプロダクトをリリースしたんです」
前川氏とは、起業する前から知り合いだったのだろうか。
「前川は同じ北海道の出身なのですが、2014年に北海道で開催された経営者が集まるイベントで出会いました。出会って30分もしないうちに、『一緒に起業しようよ』と声をかけられ、意気投合した形です。冒頭申し上げた通り、M&AにはスタートアップのM&Aもあれば、事業承継の課題もあり、それぞれ違ったM&Aスキルが求められます。僕は、1回学生起業した経験がありその会社を売却していますが、その会社でも社長同士の相性って結構あるなと思っていました。僕はいわゆるITやスタートアップの領域の知見を持っていてプロダクトにも明るい方ですが、反対に前川はご年配の経営者との相性がよいタイプであり、僕とは別の強みを持っていました。タイプや強みが逆だったので、共同代表になったら両方取れるんじゃないか、と思い一緒に起業をして、結果スタートアップ側、事業承継側、両方の経営者との接点が増やせたと思います」
共に事業を大きくしていくために、意識は必ず一緒の方を向きつつも、権限をうまく分けているというところが、重要なのだろうか。
「権限を分けることも重要ですが、個人的には権限を完全に分けてしまうのも良くないのではと感じています。分業みたいになると、『自分のテリトリーだから口を出すな』みたいになったりしかねない。なにか壁にぶつかった時、議論が必要になった時に、口を挟めないような状況は避けたいなと。やはりお互いに口出ししまくったほうがいいと思いますね。情報は共有して、互いに話し合うということです」
今後のビジョン
事業承継やスタートアップのM&Aの課題解決といったところでプラットフォームを作っているが、まだまだ解決しなければならない課題には、今後どのように向き合っていくのか。
「今後、買い手が自分で売り手候補を探してきて、自分で売り手にコンタクトして、成約するみたいな流れが起きてくると思うんですよね。
そうすると、仲介とかを通さずにM&Aがどんどん進んでいき、日本のM&Aの数ってすごい爆発的に増えて、やっとグローバルでも勝てるような会社が生まれたりするのだと想像しています。『M&Aクラウド』もそんなプラットフォームにしていきたいと思っています。今は買い手向けにM&Aを進める方法のガイドや、売り手向けに買収ニーズ記事をネット上に掲載していますが、今後は例えば、M&A仲介会社のために買収ニーズのデータベースを作成して提示するとか、採用管理ツール(ATS)のM&A版を作るとかは考えていたりします。2025年1月から、M&A仲介会社向けに提供するプラットフォーム『M&Aクラウド for アドバイザー』のβ版の運用を開始していますが、すでに70社以上の仲介会社に興味を持っていただき、複数社で活用を始めてもらっています」
M&Aクラウド社はIPOを目指しているが、IPOをした後も含め、会社の方向性としては、どこを目指しているのだろうか。
「『テクノロジーの力でM&Aに流通革命を』というミッションに加えて、『時代が求める課題を解決し時価総額10兆円へ』というビジョンを掲げていますが、方向性としてはM&A領域でプラットフォーム事業をどんどん拡大していく予定です。実はまだまだやれることはいっぱいあるんですよね。例えば、デューリジェンスをSaaS化するとか、バリエーション(企業価値)算定をSaaS化するとか、PMI領域までSaaS化するとか。M&Aやファイナンス支援に関するトータル的な事業展開をやっていきたいなと思っています。上場後は、M&A・資金調達支援だけではなく、弊社も投資やM&Aをやっていきたいという思いがあるので、ファンドを作るということも考えています。
スタートアップ関連でいうと、VC(ベンチャーキャピタル)にとってはファイナンスリターンの観点から見て、IPOではなくM&A売却することはどうしても消極的になりがちですが、M&Aを積極的にサポートするCVCを作ってもいいかなとは思っています。売却の支援だけではなくて、買い手としてロールアップM&Aをする企業の伴走もありかなと。そういう投資をCVCとして自社でやるというのは、ひとつ構想としてあります」
海外のIPOに比べて、日本のIPOは成長の規模が格段に小さい。人口縮小フェーズに入った日本においては、企業の規模拡大にはM&Aが不可欠になってきているとの指摘もある。そのM&Aが仲介を通さずに成立するのであれば、画期的な革新といえる。M&Aクラウドはそれに挑んでいる。
(構成=UNICORN JOURNAL編集部)