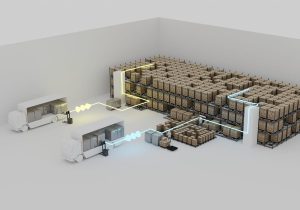「ユニコーンを目指すならM&Aは必須」…日本のスタートアップみんなでグローバルに

小粒の上場企業が増加していることが社会課題のように注目されている。スタートアップ企業にしてみれば、IPO(新規上場)は一つの大きな目標であり、投資してくれた投資家たちに対しての義務のように思われている節もある。だが、上場した後に株価を上げることは容易ではなく、高い成長可能性を有する企業向けの市場とされる東証グロース市場に上場している約600社のうち、時価総額500億円以上の企業は約20社にとどまり、100億円未満の企業が3分の2にあたる約400社を占めているのが現状だ。
そのため、東京証券取引所が、グロース市場の上場維持基準について、「上場10年後に時価総額40億円以上」から「上場5年後に100億円以上」への引き上げを検討していると報じられ、大きな注目を浴びている。
そんななか、株式会社ACROVE代表取締役CEOの荒井俊亮氏は、「国内のIPOでユニコーンを目指すならM&Aは必須である」と強調する。

ACROVEは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどの主要なECモールや自社ECサイトの運用支援を行う一方で、人的リソース不足、資金不足、マーケティングノウハウ不足、事業承継等で悩んでいるECブランドなどを、M&Aを通じて譲り受け、そのブランドを成長させるという“ECロールアップ事業”を展開する。
ユニコーン企業を目指すにはM&Aが必須と語る真意と、その際の戦略、M&Aのメリット・デメリットなどについて、話を聞いた。
国内IPOとアメリカのスタートアップ事情の違い
荒井氏は、アメリカと日本のスタートアップ事情には大きな違いがあると指摘する。
「アメリカでは、売上500億円、利益100億円であれば100倍、最低でも50倍の評価がつくため、IPOの出口も大きく、シード期から時価総額が大きく、資金も多く集まります。一方、日本のスタートアップはプレシードで時価総額1億円くらいが多く、アメリカのように最初から50億円、100億円ということは稀です。
この背景には、アメリカのVCでは、Yコンビネータなどのシードアクセラレータが大きなリターンを形成しており、1社に対して100億円を投資して、巨額のリターンがあれば、ほかの投資先が回収に失敗しても構わないといった価値観があることがあります。このような信用経済、レバレッジ経済を見ると、日本とはマーケットが全く異なります」
米国のスタートアップに関する経済事情は、日本とは文字通り桁が違うわけだが、荒井氏は、そもそも背景が異なるため、日本ではM&Aによって成長戦略を描くことが必要だと力説する。
「日本では、シードのバリエーションで1億円や2億円、シリーズAでもやっと何十億円で、レバレッジが効かず、上場企業もマルチプル20倍とか、良くて30倍で評価されているなかで、それをコンプスに比較対象にしているため、どうしてもユニコーンやデカコーンは生まれてこないと考えられます。ドル円の強さやマクロ経済など、さまざまなバックグラウンドが違いすぎるため、アメリカと同じような成長戦略は難しいのが現状です」
日本におけるM&Aの重要性

このような状況を踏まえ、荒井氏は日本でユニコーンを目指すにはM&Aが重要なキーになると力説する。
「M&Aによってコンプスの領域を広げていけば、限界がないと考えています。人口1億人でGDPも下がりつつあるなかで、マーケットが限られているため、海外に行くかM&Aでシェアを上げていくか以外には、毎年2倍、3倍の成長は正直難しいでしょう。
人口も減少トレンドで、日本経済自体が停滞気味のなかで企業を大きく成長させるためには、他社と互いの強みを掛け合わす成長戦略としてのM&Aが非常に重要です。例えば、ヤフーが売上1兆円になっている中で、2倍成長しようとしたら、ほかに1兆円の企業を買収するのが効果的です。120%の成長にするにしても、2000億を伸ばすのは容易ではありません。ZOZOレベルの企業を毎年買収しなければ、株主が思っているような成長は無理です。だから、ある程度企業が大きくなった後に、さらに伸ばそうとする際に、M&Aを検討するのは自然の流れです」
その点で、創業早い段階からM&Aを繰り返し、M&Aに慣れていくことは、非常に重要だと指摘する。
M&Aのメリットとデメリット
まだまだ広く普及しているとはいいがたいM&Aだが、メリットが大きいとしても、デメリットはないのだろうか。
「デメリットは、ないに等しいと考えています。もちろん、PMI(統合プロセス)の難しさとか、マネジメントの難しさなどはありますが、それは多分ビジネスをやる上で採用が難しいとか、育成が難しいというのと同じレベルの悩みでしかありません。それに比べて、M&A以外に事業をもうひとつ立ち上げて、営業利益100億円の会社を来年200億円にしようとするほうが難易度は高いでしょう」
荒井氏は、M&Aをいかに使うかということが、事業戦略の中心になるのだろうとの持論を語る。
「M&Aによって成長していくという事業戦略は、当社に限らず、どの会社も採用せざるを得なくなってくると考えています。アメリカのM&Aは、例えば特許を持っているからこそ、何十倍で買収するとかが普通にありますが、日本の場合、インスタグラムやユーチューブみたいなサービスがゼロから立ち上がる事例はほとんどありません。日本のM&Aは会社を買うと企業の経営者自身も引き続き経営に携わり、事業計画にコミットするという前提が共有されている傾向があります。アメリカみたいに高く売れたからよかったねという感じではなく、割とみんな合意した事業計画と、そこから引いた時価総額でイメージしているを思います」
ACROVEのM&A戦略
では、ACROVE社が他社をグループジョインする際には、どのような点を重視するのだろうか。
「まず、相手先の事業のポイントをしっかりと見ています。Eコマースで事業をしているため、アマゾンや楽天、ヤフー中心にEコマースで伸ばせるかどうか、また、最近はEC支援系の会社もグループジョインしているため、B to BでEC支援やソフトウェアのサービスを提供するにあたって、シナジーがあるかということを見ながらM&Aをしています」
プロダクトが面白いかや、製品を売った後の販路なども含め、その会社の伸びしろを推し量るのか、もしくは経営者の資質を重視するのか、どちらが主軸になるを尋ねると、荒井氏は冷静な視点で分析していることを明かす。
「どこが一番というよりは、全ての要素に対して、両社が一緒になった時に相乗効果が発揮できるかという観点において点数的なものをつけ、総合的に何点かという判断をしています」
ACROVEのM&A事例:EMAのグループジョイン
荒井氏がこれまでに携わってきた会社の中で、特徴的だった事例を尋ねた。
「宮城にあるEMAという、乾燥機や洗濯機など一人用の家電を扱っている会社があります。ここは28年くらいやっている会社で、売り上げが伸びていましたが、一方で直近は円安の傾向も非常に強くなったので赤字になっていました。
その時にM&Aをしたのですが、月商が5000~6000万円だったのが今は1億円を超えて、損益もマイナス4000~5000万円だったのが、逆に数千万円の利益が出るような状態になっています。赤字経営であっても、この企業は黒字化できると踏んで、ジョインしてもらいました。その結果、社員の方々の給与も上がりますし、みんなにとっていいなと考えたからです」
では、“ここを改善すれば絶対黒字化できる”と判断したポイントはどこにあるのだろうか。
「商品は良かったので、それがACROVEの持っているアクローブフォースのデータによって、どれくらいECで今後売り上げが伸びるか、ある程度わかります。サッカーで例えるなら、選手の全員のデータを持っているとして、AIでその高校生を見たら、ある程度その後の伸びがわかるようなものです。50m走の記録などと、身体のデータやそれまでの動きなどがデータ化されているので、それを入れたら得点確率がわかります。それと似ています」
その際、会社の人的資源なども数値化するのだろうか。
「そこまではしていません。どちらかというと、もう少しロジックというか、ECの中のSEO順位がいくらで、広告費が今いくら使っているかなど、そういうところを見ています」
M&Aで成長させていく上でネックになるポイント
では、グループジョインした企業を成長させていく上で一番ネックになるポイントについて聞くと、答えに困る様子を見せた。
「もともとは大企業同士のM&Aや、大企業がある程度の中堅企業を買うところからスタートして、やっと2000年代にGMOやサイバーエージェント、光通信、ソフトバンクなどがベンチャー系のM&Aを行い、広まってきましたが、中小企業のM&Aは意外となかったため、歴史が浅く、どこに着目すべきか見えづらいといえます。
例えば、財務数値についてです。M&Aの実務みたいな教科書で想定されているのは、大企業同士のM&Aで、財務数値が正確に整っている前提で、どこを見るかが示されています。一方、会計監査の設置が義務付けられていない中小企業では、上場企業のように厳密な会計基準を適用する必要はありませんので、デューデリジェンスでは企業の財務を含めた実情をお伺いしながら把握し、特に財務数値については丁寧にコミュニケーションを取りながら整備するところから始まることもよくあります」
つまり、教科書通りには手続きが進まず、一つひとつのステップを細かく精査しなければならないという苦労があるというわけだ。
中小企業M&Aの可能性
M&Aによって事業が大きくなっているACROVE社として、目指しているのは、どのようなポジションなのだろうか。
「ロールアップで言うと、GENDAさんがゲーム事業でM&Aをして、日本のスタートアップの歴史の中で一番早く売上1000億円を達成したといわれていて、ベンチマークというか、後を追いながら、Eコマース領域ではうちが一番M&Aをやっています、というポジションを打ち出していきたいですね。実際に、2年で16件のM&Aを実現と、短期間での実行数は1番だと思います。ただ、M&Aは目的ではなく手段だと考えています。グループジョインした事業を着々と成長させ、Eコマース領域で何か課題があった際にはACROVEに一任、という具合に思ってもらえるようにグループ全体で力を付けていきたいなって思います」
成長していくうえで、ACROVE社が現状、課題と感じていることは何かあるのだろうか。
「当社ほど短期間にM&Aをする事業会社って、日本のスタートアップの歴史上ほとんどないので、グループ経営のナレッジはしっかりと貯めていかないといけないと思います。具体的に言うと、例えば証券会社さんや監査法人さんへのコミュニケーションも含め、上場前にM&Aしました、というノウハウを持っている企業は多くありません。
例えば極端な話、M&Aは業績の予測に一切入れないのかといえば、本当は入れないんですが、うちであれば10社もM&Aするのに一切入れないのか、というのも不自然です。だからこそ、投資家の皆様にしっかりと納得してもらえるように、ご不安を与えないように、誠実な対話を一つ一つ重ねながら、業界を良くしていくために丁寧に取り組んでいかなくてはいけないなと思っています。そこは、今後大変なところなのかなと思います」
最後に、スタートアップ業界に対して思うところを聞いた。
「一つあるとしたら、やっぱり日本のみんなでチームになっていくことも大事だなと思っています。やっぱり中国がすごいところって、海外にいたとしても、国や地域を超えて協力する強いネットワークを築いているところにあると思うんです。どこの国にも中華街があります。日本の人って、どちらかというと“俺はユニコーンだけど、あいつらはちっちゃいよね”みたいに個で戦う傾向があると思っています。でも今こそ日本のスタートアップ、ベンチャー企業が協力して、みんなでユニコーンになって、みんなでグローバルになって、そのナレッジを分け合えばいいと思っています」
荒井氏は、自社をユニコーンにすべく奔走するとともに、日本のスタートアップ全体で世界に立ち向かうべきとの野望を抱いている。業界の垣根を越えて、日本企業が世界に羽ばたく未来を描けるか、注目したい。
(構成=UNICORN JOURNAL編集部)