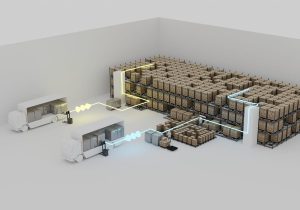“スタートアップのあるべき姿”を壊す…VCの「勝つための投資」と長期視点の戦略

●この記事のポイント
・DeNA発VCのデライト・ベンチャーズが日本VC界に投じる“異端の哲学”に迫る。
・「起業家がつくった、起業家のためのVC」を標ぼうする同社は、スタートアップやVCの慣習にとらわれず、日本のスタートアップ・エコシステムそのものを変えようとしている。その投資方針に迫る。
スタートアップ支援において、表面的な資金提供だけでなく、起業家と本質的な伴走関係を築くベンチャーキャピタル(VC)が日本でも増えてきた。なかでも異なる存在感を示しているのが、デライト・ベンチャーズである。同社はディー・エヌ・エー(以下、DeNA)を出自としながら、その投資領域は、DeNAの事業領域とは相関がないように見える。
日本のスタートアップ・エコシステムを大きく変えることを志し、支援の在り方や契約の設計にまで“哲学”を貫くこのVCは、どのような姿勢で投資と支援を行っているのか。今回は、同社マネージング・パートナーの渡辺大氏にインタビューし、支援スタンスの背景を聞いた。
目次
「社会に必要なリスク」を引き受けるVC
DeNAを出身母体とし、「起業家がつくった、起業家のためのVC」を標ぼうして、2019年に設立されたデライト・ベンチャーズ。
その投資方針は明快だ。経済や社会に大きなインパクトをもたらす「巨大イノベーション」を生むスタートアップに、果敢に投資する。DeNAのCVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)として戦略投資するのではなく、あくまでも独立したVCとしてキャピタルゲインの最大化を追求する。
投資対象は主にシード、プレA、シリーズAといった初期ステージのスタートアップで、投資額は数千万円から数億円規模に上る。投資先の選定基準は3つの観点で成り立っている。一つ目は「情報の非対称性を解消する事業」である。情報格差によって不利益を被っている人々に、テクノロジーや仕組みを通じて力を取り戻させるような事業を評価する。
二つ目は「社会的生産性を劇的に改善する事業」である。「世界的に見て日本は国全体の生産性が低い。構造的な問題が多く、そこに取り組むスタートアップに投資しています」(渡辺氏)。業務効率化やSaaS、AIを用いたソリューションは、その核心領域といえる。
三つ目は「サステナビリティ」である。クライメートテックやエネルギー、ヘルスケアといった領域で、長期的視野に立った課題解決型のビジネスが求められている。
また同社には、本業の傍らで起業にチャレンジできる環境を提供する「ベンチャー・ビルダー事業」と純投資を行う「ベンチャー投資事業」という2つの事業がある。
ベンチャー・ビルダー事業では、今年3月に米サンフランシスコ・ベイエリアにてAI特化の起業支援プログラム「DelightX」を開始した。現地のVCや連続起業家のメンタリングを受けながら、ベイエリアでの滞在を通じて起業準備と資金調達を目指す内容となっている。

日本のVC構造への問題提起
DeNAからスピンアウトしたVCでありながら、同社が得意とするエンタテインメント分野への投資を中心とはしていない。先述の投資基準に照らし合わせると、エンタテインメント業界は対象から外れるケースが多いためだ。得意分野であっても、信念に基づいて「投資しない選択」も行う。
同社が大切にしているのは、ハイリスク・ハイリターンを追求するアセットクラスとしてのVC投資に相応しい基準で投資をすることだ。日本のVC業界では、依然として大企業資本への依存度が高く、「潰れないスタートアップ」が選好されがちだ。結果として、Exit時の企業価値は100億円前後にとどまり、上場後は四半期ごとの業績圧力にさらされ、抜本的なイノベーションが生まれにくい状況が続いている。
デライト・ベンチャーズは、こうした状況に対する強い問題意識から、あえて「ハイリスク・ハイリターン」の本流を選ぶ。これは、米国が50年かけて育んできたスタートアップ・エコシステムの本質に近い考え方である。
「米国の経済成長を支えたのは、VCが投資したスタートアップです。世界の時価総額トップ10のうち半数以上がその例。一方の日本は、エコシステムとしてはまだ初期段階で、低リスク・小規模な上場が主流です。しかし、上場後は短期視点に陥り、イノベーションの芽が摘まれてしまう。だからこそ、VCがリスクを取る姿勢に転換すべきだと考えています。当社はその立場から投資をしています」(同)
契約構造にまで及ぶ支援姿勢
特徴的なのは、こうした思想が支援や契約の設計にまで及んでいる点である。
国内のVC投資では、一定の水準に達したスタートアップに対して上場を“強制”し、達成できなければ創業者に株式の買い戻しを求めるといった契約も少なくなかった。その結果、スタートアップの成長戦略において、上場が至上命題になっていることが多い。
「日本のスタートアップは株主のExitを優先して早く上場することよって、より大きく持続的な成長を犠牲にしている面があると思います」(同)

この考えのもと、デライト・ベンチャーズはこうした日本独特の契約構造を否定する。あくまでもデライト・ベンチャーズは、企業の成長フェーズに最も適したタイミングでのExitを支援する。起業家が本質的な挑戦に集中できる環境づくりを重視している。それが結果的にVCの収益に貢献すると考えるからだ。
また、日本のスタートアップにおけるストックオプションの設計慣行にも異議を唱える。
「(日本のVCの多くが)慣習として、社員などに割り当てるストックオプションの枠(いわゆるプール)を10%と定めており、契約上もそれ以上に拡大しにくい構造になっています」(同)
同社では、この枠にも柔軟性を持たせ、長期的な視点でインセンティブ設計を行っている。日本も米国のようなスタートアップ・エコシステムが回るようになる日が来るのだろうか。
「米国も60年前は終身雇用が当たり前でした。しかし、スタートアップのエコシステムが進化するなかで、起業家個人が金銭的リスクを追わずにアップサイドを目指せる仕組み、そして失敗してもキャリアにプラスとなる仕組みが整っていきました。こうした実質的なセーフティネットの形成と長年にわたる自然淘汰の積み重ねによって、今の姿があるのです」(同)
時間はかかるかもしれない。それでも、VCが変わっていくことは、エコシステム進化の重要な一歩となるはずだ。
起業家に“使い倒される”関係性を
まず注目すべきは、DeNAのアルムナイネットワークを活用した「人材支援」である。
デライト・ベンチャーズはDeNAと連携し、経験豊富なアルムナイ(退職者)コミュニティを運営。このネットワークを通じて、投資先企業への人材紹介や採用支援を行っている。
たとえば、定期的に開催される座談会では、活躍中のアルムナイをゲストに招き、南場氏がモデレーターを務める。ネットワークメンバー限定で公開される情報や、イベントを通じた人材のマッチング機会も提供している。
また、南場氏が毎月設けている「オフィスアワー」は、投資先企業が必要なタイミングで直接対話できるよう設計されており、実務に直結するサポートが特徴的だ。
次に、「海外展開支援」だ。
渡辺氏自身が米カリフォルニアに拠点を持ち、現地での立ち上げや展開に関する戦略的支援を行っている。グローバルを視野に入れたスタートアップにとっては、貴重なハンズオン支援となっている。
さらに、「政策連携」も大きな特徴だ。
南場氏は経団連の活動にも深く関与しており、政策決定の場にスタートアップの声を届ける役割を果たしている。推薦制の経団連への参画を通じて、投資先企業が大企業や行政との接点を得る機会も創出されている。
「日本のテックを代表する企業の創業者である南場がいて、かつ自らも事業に関わっているVCであるという点は、他のVCとの最大の差別化要因だと考えています」(同)
投資先に見る未来志向の実践例
デライト・ベンチャーズの投資先は、2025年5月10日時点で79社に上る。その顔ぶれからは、同社の思想が色濃く反映されていることがうかがえる。
たとえば、「日本の生産性向上」というテーマに沿った投資先として挙げられるのが、代理店管理プラットフォームを運営するパートナープロップだ。同社は、日本特有の構造的課題に向き合い、代理店の業務効率を革新する次世代PRM(パートナー関係管理システム)を提供している。

また、グローバル水準のイノベーションに挑む投資先として注目されるのが、エネルギー分野への取り組みだ。福岡発のスタートアップ・Tensor Energyは、再生可能エネルギーの需給予測をAIで最適化する事業を展開しており、世界市場での勝機を視野に入れている。
さらに、ディープテック領域にも注力しており、ムーンショット領域や国家戦略技術といった「今は見えにくいが、10年後に不可欠となる技術」への投資も積極的に進めている。長期視点に立った賭けとも言えるこれらの投資姿勢は、同社の思想を象徴するものだ。
投資先のソーシングについては、比較的起業家からの紹介が多いが、方針としては広く門戸を開いている。たとえば、新卒向けダイレクトリクルーティングを展開するABABAへの投資は、問い合わせフォームを通じたメールから始まったという。
起業家に求めるのは“信念”
では、どのような起業家がデライト・ベンチャーズの投資対象となるのか。共通しているのは、「強い信念とミッションを持つ人物」である。
「社会や環境に対する怒りを原動力に、それを解決しようとするスタートアップは、結果として大きく成長する傾向があります」(同)
目先の利益よりも、「この課題をどうしても解決したい」「社会を変えたい」という熱意を持つ起業家にこそ、投資の意義があるというのが、同社のスタンスだ。
もっとも、こうした企業はリスクを取りながら、長期戦を強いられることも多い。ファンドには期限がある以上、VCとしてはどこかのタイミングでリターンを得る必要がある。その点について尋ねると、渡辺氏は次のように語る。
「よく誤解されますが、私たちが重視しているのは“10年以内の上場”ではなく、“10年でどれだけ成長したか”です。たとえば、10億円投資した会社が30億円の価値しか生まなければ問題ですが、300億円の時価総額に成長していれば、上場していなくてもセカンダリーで株式を引き受ける投資家は必ず現れます。成長さえすれば、出口の形にはあまりこだわっていません」(同)
デライト・ベンチャーズの投資と支援は、単なるスタートアップの成長支援に留まらない。日本のVC業界に根付く慣習や構造的な歪みに疑問を投げかけ、その枠組みそのものに変革を迫る姿勢が貫かれている。
「マイクロソフトやグーグルのように、人々の生活を一変させるようなインパクトを目指す起業家を、私たちは応援したいと考えています。従来、VCから言われてきた『スタートアップのあるべき姿』は一度忘れて、大きな野望を持って進んでほしいと思います」(同)
その姿勢には、「志ある起業家とともに、日本の社会・経済を前進させる」という強い意志がある。VCの役割を再定義し、それを現場で実践するデライト・ベンチャーズの挑戦は、これからの日本にとって大きな示唆を与える存在となっていくだろう。
(寄稿=相馬留美/ジャーナリスト)