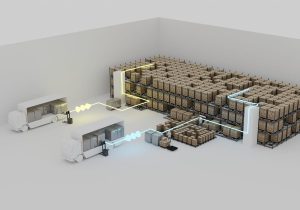「汗」から体の状態を可視化…スタートアップが医療・美容・セルフケアを変革

●この記事のポイント
・PITTANは汗に含まれる情報に着目し、医療や美容、フィットネスなど、さまざまな分野に応用できる技術を開発。
・すでに世の中で研究・開発された技術を、実用化させることができたのはスタートアップだからこそだという。大企業だと実現できないことを実現できるのは、現場の声を聴く傾聴力である。
・「まだ誰も使っていない生体情報」を利用して生活習慣病を減らす。
「まだ誰も使っていない生体情報」を起点に、医療・美容・セルフケアの境界を再定義しようとするスタートアップがある。PITTANは、汗や唾液といった体液に含まれる情報を可視化することで、体調変化の兆候や肌トラブルの要因を読み取る独自のセンシング技術を開発。大企業が見過ごした構造的ギャップに着目し、技術とビジネスをまたぐインターフェースを築こうとしている。今回は同社代表取締役CEOの辻本和也氏に、PITTANが目指す未来を聞いた。
目次
「体液」の情報に注目したディープテック・スタートアップ
――PITTANでは、どのような事業を展開しているのでしょうか。

辻本氏 当社では、汗などの微量な体液から人間の状態を分析するという新しいセンシング技術を開発・提供しています。たとえば、3分ほど肌にパッチを貼るだけで汗を吸収し、それを専用機器で分析することで、皮膚の状態や体内代謝に関する情報を得ることが可能です。
この技術は、エステやフィットネス、コスメ店舗といった「BtoBtoCの現場」に導入されており、お客様の状態に合わせたレコメンデーションや商品提案に活用されています。
――なぜ「汗」だったのでしょうか。血液や唾液など、他の生体成分ではなく。
辻本氏 汗というのは、実は皮膚細胞の周囲から染み出してきた水分です。血液や唾液と比べて、より局所的な情報を持っているのが特徴です。皮膚のある場所だけ赤くなる、ニキビの出る場所が違う――そういった局所性の違いに着目したとき、汗の持つ情報量に非常に価値があると気づきました。
たとえば皮膚炎などは、今の医療では「見て判断する」のが主流で、原因特定が難しい。私たちは、その診断プロセスを汗で補えるのではないかと考えています。
――分析には、どんな技術が使われているのですか。
辻本氏 当社が開発したプロダクト「Nutrifull(ニュートリフル)」は、汗に含まれる複数の成分を同時に定量分析します。分析対象は、アミノ酸などの栄養成分、ホルモンさらには皮膚炎の兆候につながる物質にまでおよびます。これらを短時間で、しかも現場で完結できるのが特徴です。最先端科学のラボオンチップデバイス技術を搭載した卓上型ハードウェア「Pitagoras(ピタゴラス)」を使っていただくと、パッチを肌に3分間貼って微量な汗を採取し、Pitagorasにセットするだけ。10分で分析が完了し、あとは付属タブレットのアプリに自動でデータが送信され、結果が可視化されます。

――現場が導入しやすい工夫もされているのですね。
辻本氏 はい。技術的にどれだけ優れていても、ユーザー体験が伴っていなければ意味がありません。当社では、エンジニアとデザイナーがチームで動き、UI/UXも含めて、「現場で迷わず使える」ことにとことんこだわっています。
たとえば化粧品の世界では、官能的な納得感が非常に大切にされます。だからこそ、数値を出すだけでなく、「自分の肌の状態を知ることができた」「自分の体の状態に気づけた」と感じられるような体験設計にしています。
――医療分野での利用はありますか。
辻本氏 汗分析をしている強みから、皮膚炎については研究を進めています。皮膚炎は局所性があり、見た目が同じでも原因は様々です。そこで現在、シンガポールのナショナルスキンセンターと共同で、汗から皮膚炎の原因を推定する研究に取り組んでいます。
――なぜシンガポールの研究機関と共同研究を?
辻本氏 ナショナルスキンセンターはアジアで唯一の国の皮膚研究機関なのですが、展示会をきっかけにラブコールをいただき、「一緒にやろう」と、私たちをパートナーとして迎えてくださいました。現地での医療機器化に向けたプロジェクトも始動します。
「出向起業」プログラムがきっかけで創業
――辻本さんは29歳の時に京都大学の医工学分野にて、博士号を取得されたのち、東京エレクトロンやロームで研究者として勤務されていますね。
辻本氏 はい。ただ、大学で研究されている技術が社会で活用されないことに対して、非常に強いフラストレーションがありました。京都の大企業には、優秀なエンジニアが多く、技術の蓄積もあります。設備も非常に整っていて、資金も潤沢です。ところが、海外の先進的な新興企業と比較するとビジネスとしてのイノベーションが起こせていないことに疑問を感じていました。
それで思い切ってキャリアチェンジしました。ITコンサルティングや戦略コンサルティングの仕事に携わり、保守運用体制の構築やDX組織の立ち上げなどにも関わりましたね。ただ、スピード感に欠けると感じ、スタートアップへの志向が強くなっていきました。
――珍しいキャリアですね。そこからMonozukuri VenturesというVCに転職しています。
辻本氏 昔、メディアでハードウェアやディープテックのスタートアップにだけ投資するVCだと紹介されていたことを覚えていました。それで、Monozukuri Venturesのホームページから応募したら採用いただき、同社ではスタートアップのものづくり支援や投資に携わりました。
京都で技術を持つ優秀な人材は大企業に多くいて、起業に対してリスクを感じているというのが現状です。しかし、ロームやオムロン、日本電産など京都の大企業は、かつてのスタートアップなんです。京都府はもう一度この地をスタートアップが生まれる“都”にしたいという思いがあり、Monozukuri Venturesと組んで、2021年から大企業からのカーブアウト(親会社が戦略的に子会社や事業の一部を切り出し分社化を実施すること)を生むプロジェクトが始まりました。
時を同じくして、経済産業省が「出向起業」の支援を開始しました。出向起業とは、大企業等の人材が所属企業を退職せず、外部資金の調達等により自らスタートアップを起業し、出向等の形でその経営を担うという制度です。カーブアウトプロジェクトの視察に訪れた内閣府の担当者が、のちに当社CTOとなる児山浩崇でした。彼は島津製作所から内閣府に出向しており、このプロジェクトに非常に関心をもって視察にきてくれました。
――創業のきっかけは、二人の出会いによるものなんですね。
辻本氏 私たちは偶然にも大学での研究テーマがMEMS(Micro Electro Mechanical Systems、微小電気機械システム)だという共通点がありました。当時は、あらゆるものがウェアラブルになり、センシングされているという未来が来るといわれていたのに、何年たってもその時代が来ない。その原因は、電気的に、または光でセンシングしているものばかりで、汗、唾液、血液などの液体を取り扱えていないからです。私たちは技術的にポテンシャルがあることを知っていたので、「実現できないのは、ビジネスモデルやリスクテイクの姿勢の問題だ」と二人で意気投合して、気づけば2022年には自分たちがカーブアウトしていました(笑)。
――カーブアウトといっても、研究開発にはお金がかかります。資金はどのように調達したのですか。
辻本氏 先ほど話した「出向企業制度」を作った経済産業省の奥山恵太さんがスピンアウトキャピタルというVCを自身で起業し、当社にも出資してくれました。ほかにも、理念に共感してくださる個人投資家、企業、地銀系のキャピタルが出資してくれました。
技術そのものよりも重要な「チーム体制」
――他社にはない、PITTANの強みはどこにありますか。
辻本氏 技術そのものももちろん重要ですが、当社の本当の強みは「総合力」だと思っています。分析装置やセンサー技術、データ解析、UI・UXデザイン、さらにマーケティングやビジネスの実装まで、一貫して社内で完結できるチーム体制があります。分析、メカトロニクス、ITの専門人材が三位一体で連携しています。ディープテックと聞くと難解でとっつきにくいイメージがありますが、私たちはそれを「体験」にまで落とし込むことに価値があると考えています。
エンジニアや研究者も、高度な専門性を持つ人材を揃えています。研究開発統括ディレクターの山本真寿は、京都大学で分子生物学の博士号を持ち、熊本大学で助教をしていた生命科学の専門家です。アカデミアの研究者だけでなく、ヘルスケアアプリ開発のエキスパートもいます。また、海外インターン生を毎年10人以上受け入れており、そこからリクルートにもつながっておりますが、これは外から見ると珍しい光景かもしれません。
――しかし、PITTANの技術は、もともと世の中にあった技術です。御社のサービスは大手企業でも十分つくることができたのではないでしょうか。
辻本氏 私たちの開発する「Pitagoras」は、一つひとつの要素技術の多くは大学の研究や、すでに市販されている部品をインテグレーションしたものです。しかし、それらを簡便な分析サービスとして実装することは、スタートアップだからこそできると考えております。
――イノベーションのジレンマが起きているということですか。
辻本氏 そうですね。技術的な問題ではなく、ビジネス構造上の課題です。「Pitagoras」は、多くの研究者の技術を基に実現できています。一部にディープテックを活用しつつ、顧客のニーズをビジネスに実装できる点こそが、当社の本当の強みです。顧客の声を聞いてビジネスを設計してきましたが、投資家にはたまに「傾聴力がありすぎる」と言われます(笑)。
――現場に行くこともあるんですか?
辻本氏 めちゃくちゃ行きます。エステなど男性が入れないところにも、頼み込んで現場を体験させていただくこともあります。自分たちが育ってきた世界とは異なることを前提に、その方々に楽しんで使えるものになるように知恵を絞っています。
全ての生物の生体成分データのインターフェースを目指す
――今後の展望について教えてください。
辻本氏 私たちが目指しているのは、「世界一、生体成分データを取得できる企業」になることです。汗、唾液、涙など、まだ十分に活用されていない体液の情報には、大きな可能性があります。
2045年にはAGIの時代が来るといわれています。今後、技術革新が進めば、確実にデータは不足していくでしょう。たとえば、アップルはウェアラブルデバイスで多くの情報を今のうちから吸い上げ、備えているように見えます。ただ、私たちはプラットフォーマーになるつもりはなく、インターフェースの領域を目指しています。光や電気では取ることができない、体液から生体成分データを取得できるプレイヤーになるのが目標です。対象は人間にとどまらず、生物全体のデータです。

私たちが今取り組んでいるビジネスは、私たちの目指すビジョンを達成するための、一つの手段です。私たちはスタートアップの時期に、セルフケアのために自分の体のデータを取るサービスを提供していこうとしています。
今後は、自由診療の領域にも展開していく方針です。自由診療は今後の医療ビジネスにおいて重要性が増してくる分野であり、私たちの技術は、診断ではなく「レコメンデーションの提示」に重きを置くという立ち位置が、非常に相性が良いと考えています。
――最後に、スタートアップや投資家に向けて、伝えたいことはありますか。
辻本氏 私たちは、「まだ誰も使っていない生体情報」に注目し、そこから新しい健康のあり方をつくろうとしています。メディカルとノンメディカルの狭間にこそ、新たな道があると考えています。誤解されがちなのですが、「メディカルではない」ことが、「ディープイシューではない」ことを意味するわけではありません。どれだけ医療が頑張っても生活習慣病は減らない。ビューティーやフィットネスの領域との連携こそが、社会課題解決に向けた私たちのアプローチです。
一社だけではできないことばかりですので、スタートアップ、投資家、大企業問わず、ぜひ、“体液からウェルビーイングを生み出す”未来に共に挑戦できればと思っています。
(寄稿=相馬留美/ジャーナリスト)