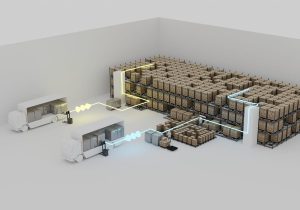市場規模は135兆円…すでに埋もれている+これから埋もれゆく「労働力」
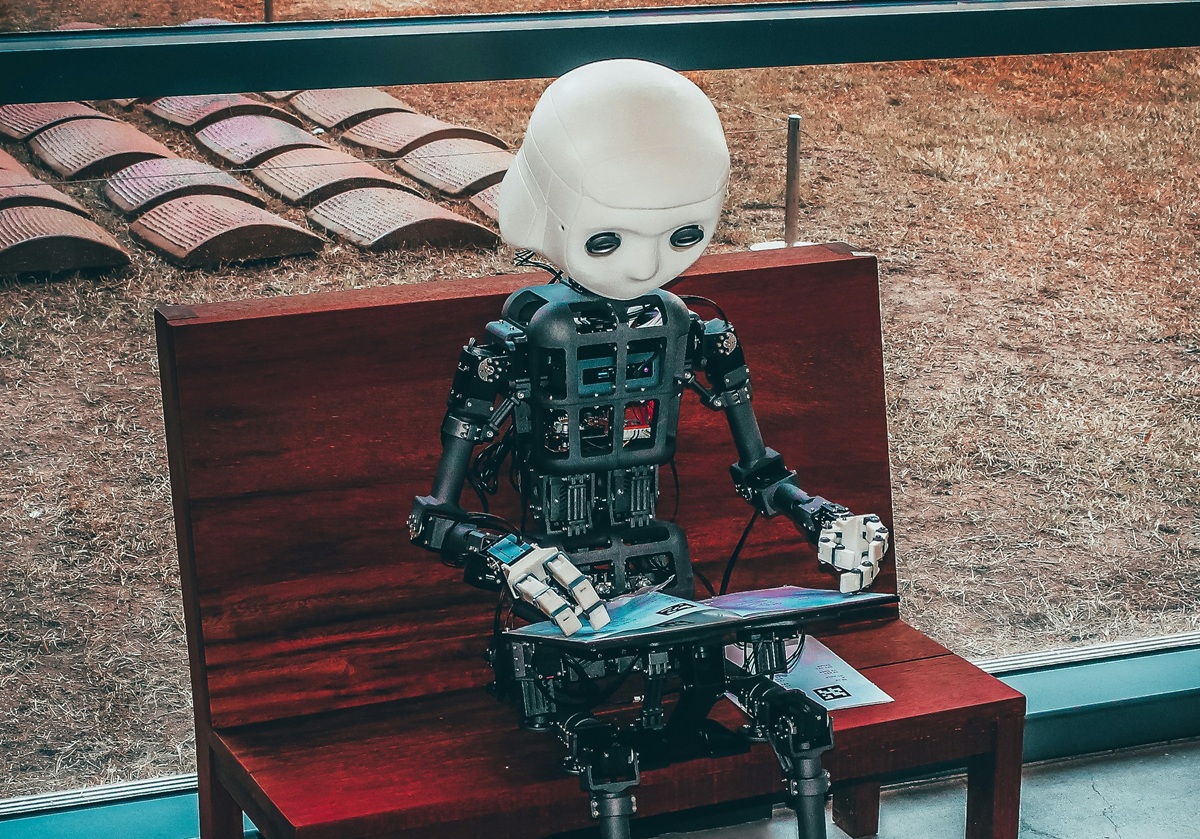
各業界で労働力不足が共通の懸案事項となって久しいが、その一つの解決策として「埋蔵労働力資産」を創出・活用すべきと提唱するのが、複数のSaaS事業を展開する株式会社うるるだ。同社代表取締役社長の星知也氏に話を聞いた。
うるるは、日本に存在する未活用の「埋もれている労働力」と、IT・AIの進展による労働代替によって生じる「埋もれゆく労働力」という2つの視点から経済的価値を初めて独自試算し、これらを総称して「埋蔵労働力資産」と定義。星氏は「埋蔵労働力資産」の総額がGDP換算で約135兆円に達するとの試算を述べつつ、「労働力不足というのはビジネスチャンスというふうに考えている。特に、既存の仕組みや枠組みにとらわれずに柔軟な発想で課題解決に取り組めるスタートアップ企業や、地域の特性を活かした雇用創出が求められる自治体などは、このテーマに対する感度も高く、今後はスタートアップの会社や自治体などにも啓蒙していきたい」と語る。

同社が提唱する「埋蔵労働力資産」の「埋もれている労働力」とは、労働意向があるにもかかわらず、現状以上に希望通りに就労できていない20~69歳の労働力を指す。例えば、“年収の壁問題”によって働き控えをしているパートタイム労働者などだ。
103万の壁や130万の壁といった年収の壁問題は、民間企業だけで乗り越えていくのは容易ではない。同社は、「働くインセンティブを高めていくといった国策によって還元されていくことが重要」との見解を示す。その解決のために、政治への働きかけは行っているのだろうか。
「各自治体や公的機関に対して、DX(デジタル化)をどんどん進めていきましょうとアプローチをしています。各機関にいるCIO(最高情報責任者、または情報統括役員)補佐官を集め、その方々が抱えている課題ですとか、隣の自治体ではどういうふうにやっているのかとか、民間企業とどういう取り組みができるのか、我々が情報を可視化し、デジタル庁や総務省の方を招いて、連携の場を設けるような活動をしています。
このような動きは、年収の壁問題などに対する直接的な働きかけではありませんが、結果的に間接的な制度改革や労働力の活用促進につながる可能性があると考えています」
では逆に、年収の壁問題を意識して働き控えをしている労働者側に対してのアプローチはあるのだろうか。星氏は、フルタイムで働けない理由はひとそれぞれのため、一律に解消できる方法はないとしつつも、さまざまな解消方法を提示しているという。
「例えば、自分の子供を保育園に預けられないというケースがあります。当社は『えんフォト』という事業を展開していて、保育士や幼稚園の先生のDX・業務効率化を支援しています。アナログな業務が多いこの業界において、DXが進むことで、人手不足が改善され、保育の受け皿が広がることで、結果的に保育園に行ける子どもが増え、保護者の就労が可能になる、という好循環が生まれます」
星氏は、何かの問題を点で見るのではなく連鎖で見ていくと、改善するためのアイデアが湧いてくると語る。
「同じように、残業時間に関しても今の日本では『働きすぎ防止』が重要視されていますが、それが逆に機会損失につながるケースもあると考えています。残業時間の上限があることで、働きたくても働けないという状況があります。この労働力不足の現代においては、制度が実態に合っていないと感じます。
年収の壁問題も同様で、制度的な壁を越えようとすると手続きが複雑になので、働き手にとってもハードルが高い。だからこそ、制度以外のところからアプローチし、着手しやすい領域から徐々に環境を変えていく・提言していくというのが、我々の具体的な動きです」
「埋もれている労働力」と「埋もれゆく労働力」の活用
労働力不足という社会問題に対する同社の取り組みは、「埋もれている労働力」の創出・活用にとどまらず、ITやAIの活用によって「人が働く余地を生み出す」こと、すなわち「埋もれゆく労働力」の創出・活用にも及んでいる。これらの取り組みは、民間企業・自治体双方にアプローチしているものの、意思決定のスピードという点では民間企業のほうが一歩先を行っているという。
「自治体はたとえば、予算を確保できるのは、ほとんどが次年度以降になるので、民間企業と比較すると時間がかかります。そのため、現在は民間企業と自治体両方のアプローチを並行して行っていますが、特に民間企業から、『DX推進を手伝ってほしい』といった相談が来た際には実際の施策展開までスピード感をもってサービスを提供することができています」

昨今、さまざまな企業がDX化を掲げるが、うまくDX化できていない会社には、どのような特徴があるのだろうか。
「DXの定義をきちっと理解してない会社のほうが圧倒的に多くて、なんらかのツールを導入することをDXだと解釈している会社もあるんですが、それは違います。本来のDXは『会社のあり方そのものを変革すること』が目的です。たとえば、外部から専門家を招いてツールを導入したとしても、企業文化や業務設計そのものが変わらなければ、根本的な変化にはなりません。そのためには、企業のトップ自らが旗を振って、組織のあり方を変えていくんだっていう覚悟が根底にないと、変わってうまくいかないんじゃないかなと思います」
採用人事についても、企業の一貫した理念が重要だと語る。人材を採用する段階で、人にしかできないことを任せようと考えて採用する企業と、なんとなく人材を採用した後で、どんな仕事を任せるかを考える企業があると思うが、最初からAIをどのように取り入れて、人には人にしかできないことを任せようと取り組んでいる企業の違いは、どのようなところに現れるだろうか。
「労働力不足が深刻な業界の方々に実際にインタビューしているのですが、やはりそういったことに感度高い会社は、常に無駄なことと無駄じゃないことの見直しを定期的なサイクルでやられているなっていうのは感じます。業務設計そのものを含めて、今やっている業務や仕組みに本当に意味があるのか、必要なのかをちゃんと見直す。その視点を持っている企業は、無駄に気づき、変化に柔軟に対応する力を持っていると感じます。“便利だから導入する”のではなく、本当に必要か問い直しているんですよね」
最後に、うるる社が思い描く理想的な社会像や、ビジョンについて聞いた。
「ずっと課題として掲げている、労働力不足を解決されてきているような社会っていうのを作っていかないと、日常生活がどんどん不便になっていくと想像しています。労働力不足は、今まで築き上げられてきた便利な社会、安心な社会、安全な社会というものが守られなくなっていくことにつながると思いますので、そういう社会にならないことが僕らの目指す社会ですし、それを事業などで解決していくことが、僕らの存在意義だと思っています。
私たちが理想とするのは、“働きたい人が楽しく働ける社会”です。今や完全に売り手市場になってきていますので、企業側は、より高賃金でとか、高待遇でとか、あるいはその場所や時間もある程度融通が利くといった体制を整えていかないと、働き手が取れないという状況になっていくでしょう。こうした流れが進めば、働く側はもっともっと楽しく、自分のやりたいことできる世の中になっているんじゃないかなと思います」
うるるは市場に眠る労働力を“資産”とみなし、日本には現在約15兆円分の「埋もれている労働力」が存在するという。さらに、IT・AIの進展による労働代替により、2030年までに約120兆円分の新たな価値が創出されると推計している。それは合計すると約135兆円に達し、日本のGDPの約2割に相当する。この「埋蔵労働力資産」の創出と活用を推進することは、市場の活性化や経済成長に不可欠といえるだろう。
(構成=UNICORN JOURNAL編集部)