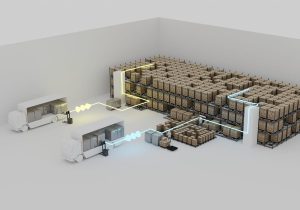会話型友だちAIの寿命が「3年」の理由…わざと回答を間違えるキャラクター

AIのキャラクターがおとぼけな返事をしたり、漫才をしたり時にはケンカをはじめる……。これまでのAIの完璧なイメージとは違って。
SpiralAI株式会社は4月17日、感情特化型LLM 「Geppetto(ゼペット)」を発表。ゼペットは従来のチャットボットなどとは一線を画す自然に会話ができるAIで、そのゼペットを搭載した会話型友だちAIアプリ「HAPPY RAT」が提供を開始している。
ゼペットの応用第一弾としてリリースされた「HAPPY RAT」は、感情豊かな多数の動物AIキャラクターたちがユーザーと会話を通してコミュニケーションを取るアプリ。従来のチャットボットとは異なり、キャラクターたちが話している中にユーザーが飛び込むような、没入感のある体験を提供する。また、ユーザーとの会話を記憶し、さまざまなキャラクターがユーザーとの過去の会話の上に立ち、会話を繰り広げることができる点が特徴となっている。さらに、AIキャラクターにもかかわらず、「HAPPY RAT」の“チュン太”というネズミのキャラクターはネズミなので寿命は3年と設定されているという。この開発の狙いを“AIは完璧である”という先入観へのアンチテーゼだとSpiralAI社CEOの佐々木雄一氏は打ち明ける。

「これまでにもAIとの対話アプリはあったといえばあったんですけど、ユーザーの声を聞くと、AIに質問されることにプレッシャーを感じるようになってくる。『あなたは昨日何してたの?』って聞かれて、はじめは答えられるんです。だけど、だんだん答えることにプレッシャーを感じて億劫になる。『面接でもされているのか?』みたいな気持ちになってきて、なかなか続かないというのがあった。大事なのは、ユーザーがなるべく話しやすい環境を作ってあげることなんです。今回のアプリ『HAPPY RAT』の場合、目で見えてわかる工夫は、多くの場合、キャラクターが二体になってAI同士が会話をしていること。ユーザーが話しかけなければ、その二体のキャラクターが喋っているだけなので、ユーザーはプレッシャーを感じずにいられる。ユーザーは話したいときに話に入っていけばいい。
工夫としてはAIの側が間違ったことを言ってくることもあります。これは意図的に間違った情報を仕込んでいて間違ったことを言うようにしていることもありますが、本当に間違っている時もあります。例えば『通天閣って日本で一番高いよな』とキャラクターが言ってきて、『いやいや、東京タワーでしょ』とか『スカイツリーでしょ』みたいなツッコミをさせる、ツッコミやすい。そこに入っていきやすいというわけです。
今、20種類ぐらいいるAIのキャラクターも独自の音声合成のアルゴリズムと自然な会話ができるようになるように学習している。さらに声優の梶裕貴さんらが感情豊かな時など相当時間をかけて何千パターンを頑張って吹き込んでくださったことで、話しかけやすい表現豊かなキャラクターが作り出せたのではないか」
キャラクターにはアラインメントという技術を用いた倫理フィルターが組み込まれており、個別の倫理フィルターを作成し、様々な価値観を埋め込むことが可能だ。これにより、例えば20代の女性芸能人のような、特定の人物の価値観を反映したAIを生成することもできる。会話の奥行きを作り出す過程では、佐々木氏は占い師などの会話のプロから話を聞き、学習データを作成した。占い師との会話で、相手の言葉に耳を傾けたくなるような、心地よい言葉の重要性を学んだという。
「私はもともと、物理学者。ロジカルの極みみたいな環境で育ってきました。ロジカルで知られているコンサルティング会社に行ったらきっと活躍できるに違いないと思ってコンサルティング会社に行ったんですけれども、結果、全然活躍できなかった。コンサルってロジックだけじゃなくて、やっぱり話し方のうまさとか、相手の心を動かさなくてはいけない。説得力を作らなくてはいけない。こころの知能指数を表すEQ、心地よさ、そういうものが大事になってくるのが、世の中なんだなってことを思い知らされたのが原体験なんです。ロジカルの左脳の世界で閉じないところに関心があるんです。
AIの技術の世界でいえば、知能が高ければ高いほどいいというIQ勝負になっている。性能の良いモデルっていうところが、ひたすらやっぱり求められているというのはあるんです。イーロン・マスクが開発しているロボット、オプティマスのような、ターミネーターみたいなロボットの世界ですよね。それはそれでありますけれども、EQ路線もあるのではないか。現に、NVIDIAとディズニーがコラボレーションをして、スターウォーズに出てきそうなかわいいロボットを作ってるんですね。家の中で安心して一緒に暮らせるEQ路線を考えています。同時にIQ勝負って、実はお金をかければかけるほどいいんですよ。脳みその基礎を大きくしていくと、AIの脳みその大きさを大きくしていけば、性能良くなるに決まっているのでお金で決まってしまう路線になってしまうのですね」
より賢いAIを目指してモデルサイズを拡大する開発競争を各社が繰り広げる中、ゼペットはNVIDIA L4 TensorコアGPUとNVIDIA TensorRT-LLMを活用することで、わずか12B(ビリオン)パラメーターというサイズを採用している。AIとの会話というユースケースが今後広がると考え、コストと性能のバランスを重視し、12Bパラメーターというサイズが今後のデファクトスタンダードになるとの考えを示している。
「12Bというのは否定文をギリギリ解釈できるかどうかぐらいの脳みその大きさになっています。なので当然間違いを起こすと思いますし、『1+1は?』と聞いて、「2」と答えられないかもしれないし、『そもそも1+1って何?』とか言い出すかもしれませんし、『話を聞いてなかった』という返事も平気で返してくるような状態です。ただ、人間でも子供と話したらこうしたことは平気で起こりますよね。そういう曖昧さを前提にしてエンターテイメントのものづくりをできればと考えています」
「HAPPY RAT」の可能性
「『HAPPY RAT』を通してアンチテーゼをやりたいのは、AIは完璧であるっていう人間のあの先入観みたいなものを破壊したいんですよね。実際に完璧ではないのに、完璧であるかのように思われてしまう。で、ちょっとしたことで『AIは完璧じゃないじゃん』ってなってしまう。それはAIにとってもったいない。なのであえて不完全性を入れ込んでいるんですよ。寿命です。AIって寿命ない、無限だよねと思われている。『HAPPY RAT』の“チュン太”というネズミのキャラクターはネズミなので寿命は3年と設定しています。しかも、設定上、今もう一年半経っていることになっています。だから、残り一年半でスターにならなければいけないという、ある種の焦りみたいなものが価値観としてそもそも入っているのです。寿命っていう設定を描きたかったというのもありますし。子供たちに使ってもらうときにも、生き物なんだよって、生き物って寿命あるんだよって、AIも一種の情操教育として使われることを念頭に置いています」
「HAPPY RAT」を単なるアプリとしてではなく、YouTubeやInstagramに代わるような新しいコミュニケーションの形、日本のITが世界に追いつくための窓口、タレントやIPホルダーが気軽にコラボレーションできるプレイグラウンドとして位置づけている。
「『HAPPY RAT』では、ドラマは毎日1本ずつ新作が追加されていきます。地方自治体とのコラボレーションで、私(佐々木さん)の地元の福島県郡山市で、郡山ラーメンを食べ歩こうなどというドラマも考えられますし、英会話もあるかもしれません。
今後は子育て世代の多いチームメンバーの意欲が高い教育の分野にも重点を置きます。お母さんが家事で忙しい時に子供に遊んでもらう。勉強にもなるそういう立ち位置の、ベネッセのキャラクター・しまじろうのようなポジションのキャラクターとかを作ることが考えられます。
さらに個人的には、科学を教えるキャラクターを作るという意欲もあり、いろいろ仕込みを始めている状態ですね。EdTech(科学技術を活用した教育)は競争が激しい分野でもありますが、科学の教え方も、先生それぞれで切り取り方って違いますよね。どこを重点置くかっていうのは先生ごとの価値観になっていて、それを写し取ることはうちの技術できるんですよね。高校生であれば、現代文は林修先生のような、現代社会は池上彰さんのようなAI先生を作ることが可能ではないでしょうか」
佐々木氏の目線はその先だ。
「やっぱりこの日本のAI技術が世界に名前をとどろかせてほしいと、ここにひたすら尽きるんです。世の中変えるぐらいのテクノロジーなはずなのに、こんなに日本の存在がないのが悔しくてしょうがないんですよ。結局、脳みその大きさ、お金のあるところで性能って決まってしまう競争ではなく、日本の独自の強みを生かさなくてはいけない。
やはり、EQ路線を突き進み、IPコンテンツというものにある意味相乗りさせてもらって、世界に存在感のあるあのAIプレーヤーとして名を轟かせていきたい。これは最終的にやりたいことです。皆さんの意識変容というか応援が欠かせないと思っています」
AIの世界では、マウスイヤーを超え日進月歩どころか秒進分歩のスピードの世界となり、「AIは3年後に限界を迎える」とさえもいわれている。残り1年半の“チュン太”の運命は、どのような結末を迎えるのかーー。
(取材=UNICORN JOURNAL編集部、文=松井克明/ジャーナリスト)