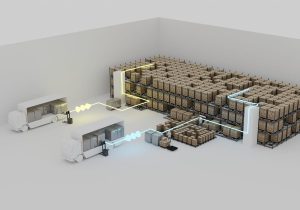スタートアップ企業の成功要因の一つは“チーム”…マーケティング人材の重要性

●この記事のポイント
・スタートアップの幹部社員対象にしたピッチイベントが行われた
・審査委員長の小泉文明メルカリ取締役会長は「社長以上に経営にコミットする人が3~4人いないと絶対に成功しない」と言及
目次
スタートアップ企業の経営者を表彰するピッチコンテストは珍しくないが、幹部社員を対象にしたピッチコンテストは珍しい。そのひとつ、マーケティング責任者を審査する「Glowth Hub Conference」が5月9日、都内で開かれた。GlowthHub共同発起人で思考合同会社代表の大前宏輔氏は「事業成長に必要な全てをやり切る人材がグロース人材」と定義した上で、マーケティング人材をテーマにしたカンファレンスの趣旨を踏まえて、その要件を3つ挙げた。
第一に、PL責任をみずから背負い、全てをやり切ること。第二に、単なるマーケティングの専門家ではなく周辺領域に積極的に関与すること。第三に、みずから挑戦し、従来の延長ではない劇的な成長である非連続な事業成長を実現すること。
カンファレンスの基調講演を行った松本恭攝(やすかね)ラクスル取締役会長は、ラクスルを成長させた仕組みを取り上げた。「すごくシンプル」(松本氏)という仕組みは、次のようにつくられた。
ラクスルを設立した2009年当時、印刷市場6兆円のうちチラシが2兆円を占めていたので、チラシを日本で一番売る会社になろうと決め、冊子やポスターなど他の印刷物を取り扱い対象から外した。チラシで一番になるには価格が勝負なので、一番安い価格を調べて、最初からそれよりも安く印刷しようと判断する。
すると最初は赤字を出すが、取扱量を増やせば規模の経済が働くと考え、そのラインを計算したら、売り上げ80億円だった。そこで、どんな施策を打ったのか。
「80億円売り上げるには、いくらの赤字を出さなければならないのか。マーケティングコストと赤字を加味した時に必要な資金は100億円ぐらいだった。100億円あれば2兆円市場で一番になれると確信して、ひたすら資金調達をして、ひたすらマーケティングをかけた。スタート時にマージンは7%だったが、35%まで達した。この仕組みを廻せるチームをつくった。グロースの仕組みは、これを実現しようとシンプルにして、目的から逆算をしてつくった」(松本氏)

競争力を発揮する企業では、松本氏が述べたような「チーム」で、有能なリーダーが八面六臂の活躍をしている。この現状を踏まえて、書類審査を経て選抜された6名のマーケティング責任者が、事業成長を成し遂げた体験についてプレゼンテーションを行った。登壇したのは、伊藤成美氏(Greenspoon売上部門責任者)、本間悠也氏(イングリウッド・三ツ星ファーム事業責任者)、齋藤大斗氏(MOSH、マーケティング責任者)、石井健輔氏(REALITY・LiveStreaming&Marketing部部長)、坂口光氏(Sparty・Digital Marketing Division Chief)、鈴木彩氏(TERASS・Marketing&PR Manager)。
企業の成長を担うのは社長以外の事業責任者
各人のプレゼンテーションに対して、9名の審査員と場内の参加者200名強が投票した結果、石井氏が最優秀賞に選ばれた。グリーの子会社・REALITYはスマートフォン向けメタバース「REALITY」を運営し、石井氏は、国内外63地域のマーケティング領域とライブ配信事業の責任者を務めている。
「大人になる時に何かをあきらめる必要はない。そのためにこの事業に命を燃やしている」と切り出したバンドマン出身の石井氏は、同社の成長がコロナ渦を経て鈍化し、地続きの成長ではなく非連続的な成長が求められる時期に現職に就いた。まず実行したことは、配信者のインサイトを理解するために10万円で機材を揃え、約1年にわたって毎日2~3時間の配信である。計278時間かけて配信して25万円を稼いだ。

同様にリスナーも理解するために1462時間視聴して314万円を課金する。この課金額は「大学受験ができて、クルーズ船で地球を2周できる金額。ロレックスの時計も買える」(石井氏)という。この時期、石井氏は会社の業務を毎日10時間こなした上で、配信と視聴に毎日7時間を費やした。最近は毎月コンスタントに10万円前後を課金し、ユーザーへのインタビューを3カ月に100名ペースで続けている。
この仕事の仕方を「狂気」と表現する石井氏がとりわけ重視したのは、組織文化の改革である。
「再成長が求められている場面で最も大切なのは組織文化を変えることだったが、社内で僕が『ユーザーの誰が喜ぶ企画か?』と質問を続けるうちに、徐々に組織文化が変わっていった。フワッとした仕事がなくなって、『この機能で誰々さんが喜んでくれた』という報告が増えた。深夜1時の配信に164件のリプライが付くようなった」
さらに顔出しをしないサービスにもかかわらず、オフラインイベントも実施した。共感を呼べると確信したのである。「理屈ではなく勘だった」と振り返る石井氏は、こう付言した。
「グロースにおいて何かひとつの施策で解決するという魔法はないと思う。勘ですべての施策が当たる状態をつくることが再成長のキモだった。僕がいることで僕の仕事の仕方が当たり前になる会社に変えることが、マーケッターの仕事だと思う」
石井氏だけでなく他の5名も、課題を鮮明にして一心不乱に解決に取り組み、数年間で劇的に業績アップを実現させた。5名とも現在の勤務先に中途入社した社員という立場だが、プレゼンテーションを聞くと、まるでアントレプレナーのような仕事ぶりである。
「社長以上に経営にコミットする人が3~4人いないと絶対に成功しない」
一方、この日のカンファレンスでは、登壇者の数名がスピーチの中で「めっちゃ」「超絶」「エモい」「エグい」「ガチで」などのスラングをしばしば口にしていた。プライベートな会話ならよいが、ピッチコンテストの檀上という、なかば公の場で平然と口にしていたことは、日本語の乱れが反映された光景だ。TPOの心得を学ぶ機会がなかったのかどうか。スタートアップ企業の多くは教育体制が未整備だが、社内に教え諭す人も不在なのかもしれない。その実態はさておき、審査員は次のような講評を述べた。
「皆さんに共通していて、私の気づきになったのは、とにかく足を使ってすべてをやり切って、顧客を理解し切ること。それぞれの方の狂気じみた顧客理解は、私も忘れていた一面があった」(田岡凌suswork代表取締役)
「皆さんの覚悟、ロジカル、冷静さの合わせ技で事業を引っ張っていることが感じられて、その上で身につまされるような狂気を持っている人もいた」(駒口哲也マネーフォワード執行役員・マネーフォワードビジネスカンパニーCMO)
「AIの普及で戦略や計画を立てることに価値がなくなってきた。実行できるかどうか、一歩踏み出せるかどうかに価値があるが、皆がそれを実行していた」(土井健ohpner代表取締役)
審査委員長の小泉文明メルカリ取締役会長は「グロースにいろいろな考え方がある中で、一人ひとりが自分の強みを遺憾なく発揮している。皆さんの熱狂的なプレゼンによってミクシィやメルカリの立ち上げ時期の自分を振り返って、寝食を忘れて働けることはすばらしいと思った」と述べた上で、スタートアップ企業の成功要因に言及。「皆さんのように社長以上に経営にコミットする人が3~4人いないと絶対に成功しない」と総括した。
(構成=UNICORN JOURNAL編集部)