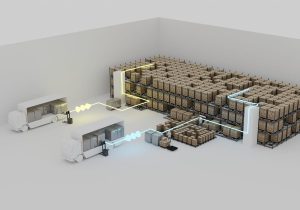日本の未来を共創する熱狂の現場へ――IVSが繋ぐ地域と多様性、その進化の軌跡

●この記事のポイント
・IVS2025において、「IVS JAPAN」と「Empower HER」という二つの重要ステージを牽引する藤本あゆみ氏へのインタビュー。スタートアップエコシステム協会代表理事も務める同氏は、「IVS JAPAN」において地域の魅力を可視化したいと語る。
・一方の「Empower HER」のステージにおいては、今のスタートアップに必要な変化の力をもたらす。ダイバーシティの視点をエコシステムに溶け込ませることが狙い。
日本最大級のスタートアップカンファレンスとして、その熱量を年々増しているIVS。今回は「IVS JAPAN」と「Empower HER」という二つの重要ステージを牽引するキーパーソン、藤本あゆみ氏にインタビューを実施。彼女のキャリアパスから、IVSへの深い思い、そして日本のスタートアップエコシステムの未来像まで、その熱いメッセージに迫る。
目次
- 「今、IVSに関わる意味」――日本のスタートアップの“現場感”を持ち帰る
- 「IVS JAPAN」――地域の可能性を、スタートアップの力で“可視化”する
- 「Empower HER」――ダイバーシティの視点をエコシステムに溶け込ませる
- 「託児所完備」――IVSは“社会全体で支える場”を目指す
- 「オープン化されたIVS」だからこそ、価値がある
- 「見たことがないなら、来てください」
「今、IVSに関わる意味」――日本のスタートアップの“現場感”を持ち帰る
「IVSは日本のスタートアップエコシステムを体感できる、いわば“現場の集大成”のような場所です。世界中のカンファレンスを見て回った私にとっても、ここでしか得られない熱量と視点があります」
そう語るのは、一般社団法人スタートアップエコシステム協会代表理事であり、「IVS JAPAN」のテーマゾーンおよび「Empower HER」ステージのディレクターを務める藤本あゆみ氏だ。

大学卒業後、キャリアデザインセンター、そしてGoogleで法人営業を経験。その後、2016年にat Will Workを設立し、続いてお金のデザインでPR・マーケティングを、Plug and Play JapanではCMOを勤め、在籍中の2022年にはスタートアップエコシステム協会を設立し、代表理事に就任。さらに、Plug and Play退社後、2024年11月からはA.T. カーニーのアソシエイテッドスペシャリストアドバイザーも兼任。現在は、東京都スタートアップ戦略フェロー、文部科学省アントレプレナーシップ推進大使、内閣府規制改革推進会議スタートアップ・イノベーション促進ワーキンググループ専門委員など、多岐にわたる要職を務め、政府のスタートアップ政策策定にも深く関わっている。
藤本氏のキャリアにおいて、最も長く携わったGoogleでの経験は、現在の活動の原点となっている。2007年から2015年までGoogleに在籍し、YouTube買収直後の変革期に立ち会った彼女は、「検索だけの会社」から「人々の世界を変える会社」へと成長するGoogleの姿に深く感銘を受けました。この経験こそが、「Googleのような会社をもっと多く生み出す仕組みを作りたい」という強い思いにつながり、スタートアップ支援の道へ進むきっかけとなった。
「一人で一つの会社に関わるだけでは、その会社の成長スピードをどう上げるか、という点にフォーカスしてしまいます。しかし、私自身が支援側に回れば、より多くのスタートアップに関わり、その成長に貢献できると思っています」
彼女の活動は、まさに日本のスタートアップエコシステム発展の最前線を走るものだ。そんな彼女のIVSとの関わりは2023年から。IVS代表の島川敏明氏との出会いがきっかけで、コミュニティイベントから1万人規模のカンファレンスへと進化を遂げたIVSを「グローバルのカンファレンスと遜色ないものにする」という目標に共鳴し、その運営に参画したという。GoogleやPlug and Play Japanなどで培ったグローバルとローカル両面の知見を武器に、今やIVSの“多様性と地域創生”という両輪を牽引する立場にいる。
「IVS JAPAN」――地域の可能性を、スタートアップの力で“可視化”する
今回、藤本氏がディレクターとして力を入れるのが、「IVS JAPAN」ステージだ。
「地域には大きな可能性があるのに、それがまだ“見える化”されていないことが課題だと感じています。だからこそ、今回の『IVS JAPAN』ステージを通じて、各地域のスタートアップエコシステムの魅力を、より多くの人に知ってもらう場にしたかったんです」
このステージには、京都府・京都市に加え、全国の自治体、地銀、研究機関が登壇する。東京と京都がタッグを組むセッションや、地方銀行が一堂に会するパネルなど、地域と都市、官と民を横断する構成になっているのが特徴だ。
特に注目すべきは、京都府知事、東京都副知事、京都銀行頭取が登壇するセッションだ。
ここでは、地域間の共創を軸としたスタートアップ政策、東京と京都の連携による国内外へのPR戦略、そして10年間で1000億円のスタートアップ投資を通じた地域経済とエコシステムへの還元について議論が交わされる。
「日本の最大の魅力は、47都道府県それぞれに異なるアセットがあることです。技術、文化、研究、人的ネットワークなど、多種多様な強みが全国に点在しています。これら全てを繋ぎ合わせられるのが、まさに今のIVSだと信じています」と、藤本氏は力強く語った。
藤本氏自身、東京に住み、東京都のスタートアップ戦略アドバイザーも務めている。しかし、彼は「東京だけで日本のスタートアップエコシステムが作られるわけではない」という強い思いがある。地域の歴史、技術、ネットワークがあってこそ、日本全体の魅力が引き出され、東京と地方の相乗効果が生まれると考えている。IVS JAPANの3日間は、まさにこの思想に基づいた明確なストーリー構成を持っている。
1日目:「現在地を知る」 各地域のエコシステムで何が起きているのかを「知る」ことに焦点を当てる。
2日目:「深める」 地域金融機関が一堂に会する機会を設けるなど、カテゴリーを絞って「理解を深める」。東京と京都のような2地域が連携することで何が起こるのか、その可能性を探るセッションも組まれている。
3日目:「未来を描く」 自動運転やAIが地域の課題解決にどう貢献するのかなど、新技術を地域にどう活かすか、といった未来志向のセッションが展開される。内閣府が発表した「スタートアップエコシステム拠点」の新拠点の紹介もあり、エコシステムの今後の発展を知る機会となる。
「IVSは“何を見つけに行くと、何が得られるのか”が明確になりつつあり、3年目の今ようやくそれができるようになってきた」と、藤本氏はその進化に自信を覗かせた。
「Empower HER」――ダイバーシティの視点をエコシステムに溶け込ませる

一方、「Empower HER」は、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)に特化したステージだ。しかし、「女性だけのための場」ではないと、藤本氏は強調する。
「『Empower HER』という名前だけ見ると、“女性向け”と思われがちですが、本質は“多様な人々が活躍できるエコシステムをどう作るか”にあります。年齢、性別、国籍、立場…あらゆる壁を越えていくための議論の場なんです」
このステージのユニークな点は、「IVS本体の運営チームが企画していない」ことだ。D&Iに取り組む外部団体が主導して企画しているため、現場の課題感や課題解決のストーリーがリアルに共有される。
「Empower HER」の根底には、日本のスタートアップエコシステムにおける多様性の促進がある。藤本氏は、「グローバルカンファレンスと日本のドメスティックなカンファレンスの大きな違いはダイバーシティにある」と指摘する。かつてのIVSが「男子校」的であったことを踏まえ、今年は、登壇者の選出基準に「すべてのセッションに必ず女性を一人以上登壇させる」というルールをIVS全体で導入したという。これは、昨年まで藤本氏が担当していた一部セッションでの取り組みが全体に広がった成果であり、グローバルスタートアップカンファレンスへと向かうIVSの大きな一歩といえるだろう。
「セッションに女性がいないと、それだけで視点が偏ってしまいます。視聴者にも“その話ならもう知ってる”と思われてしまうでしょう。多様な視点があることが、参加者のエンパワーメントにつながると考えています。」
「託児所完備」――IVSは“社会全体で支える場”を目指す
「起業家は一人ではありません。家庭やパートナー、子育て環境がある人も多くいます。だからこそ、IVSでは託児所を設けることにしました。それは“女性のため”だけではなく、誰もが参加できる空間を作るため、すべての人のためなのです」
藤本氏は、こうした配慮が「誰もが参加できる空間」を生むと語る。託児サービス導入は、これまでパートナーのどちらかが子どもの面倒を見るためにカンファレンスに参加できなかった状況を解消し、誰もが参加するチャンスを生み出すものと捉えている。IVSは今、誰もが何かを得られる“場のデザイン”を進化させているのだ。
「オープン化されたIVS」だからこそ、価値がある
かつてのIVSは「男子校的」で「限られた人しか参加する権利がない」ような雰囲気だったと藤本氏は振り返る。
「正直、昔のIVSは“選ばれた人の場”で、自分とは無縁だと思っていました。でも今は違います。誰もが参加でき、誰もが発言でき、誰もが成長できる場。それを肌で感じられるのが、今のIVSです」
IVSが毎年「ゼロからつくり直す」カンファレンスであることも、彼女が特徴的だと思う点だ。
「IVSは非効率なほど、毎年すべてゼロからつくっています。前例にとらわれず、必要な議論を必要な形で届ける。その姿勢が、日本のスタートアップに必要な“変化の力”を体現していると思います」
一般化され誰もが参加できるようになってから、IVSは今年で3年目を迎える。藤本氏は、この「3年目だからこその変化」に大きな期待を寄せる。これまでは、さまざまなセッションがごちゃ混ぜになり「おもちゃ箱」のような楽しさがあったIVSが、今年はテーマ別のセッション構成となり、「どこで何を得たいのか」「自分はどうするのか」といった問いを参加者に投げかける場へと進化している。
「見たことがないなら、来てください」
最後に、藤本氏から読者へのメッセージを紹介したい。
「IVSに来たことがない人は、ぜひ一度覗いてみてほしいです。“スタートアップ関係ないし”と思っている人にこそ、見てほしい。そこには、熱があります。成長したいという想いがあります。そして、それを実現する仲間がいます。日本の未来をつくるエネルギーを、ぜひ感じてほしい。『来て損はさせない』と言い切れる場所です」
「日本のスタートアップエコシステムに関わるのであれば、IVSを見ておかないともったいない」とまで言い切る藤本氏。そして、何度も参加したことがある人に対しても、「毎年すべてゼロから運営しているIVSは、過去の経験だけでは測れない“今年の面白さ”が必ずあります」と断言する。代表の島川氏が最も大切にしている「参加者全員にとって実利があること」という考えのもと、参加者にとって必ず何か得られるものがあるように、運営チームが心を込めて作り上げているのがIVSなのだ。
藤本氏の言葉からは、IVSが単なるイベントではなく、日本のスタートアップエコシステムの未来を共創する、生きたコミュニティであるという強いメッセージが伝わってくる。今年のIVSがどのような熱狂と発見を生み出すのか、期待せずにはいられない。
(文=UNICORN JOURNAL編集部)