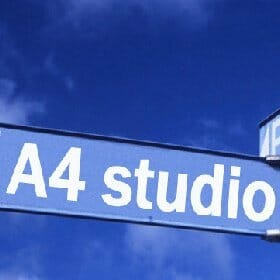利益1兆円のソフトバンクGが「法人税0円」、国が大企業を優遇する合理的理由

今年10月、お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実が、自身が設立した会社が数年間にわたり所得申告をしておらず、東京国税局から約1億2000万円の申告漏れ等を指摘された。一方、法人税に関していえば、2018年3月決算期のグループ売上高約9兆1587億円、純利益1兆390億円を記録したソフトバンクグループが、同年度の実質的な法人税の支払いが0円だったことが注目され、話題を呼んでいる。
そこで今回は、大企業による法人税回避のカラクリや、それに対する批判が的を射ているのかについて、税理士かつ日米の公認会計士であるユアクラウド会計事務所代表の村井隆紘氏に話を聞いた。
そもそも法人税とは? 大企業と中小企業の違い
まず、「大企業が法人税逃れをしている」という批判について、村井氏はいう。
「これは難しい問題で、大企業に法人税の支払いを実質的に軽減する措置があるというのは事実ですし、国全体の傾向として大企業が優遇され、中小企業が圧迫されているのも事実です。しかしそれにはきちんと理由がありますし、なにより大企業が法律上何か違法なことをしているわけではもちろんありません。早計な判断を下す前に、法人税というものと、大企業に対する減税措置の実態を知り、そのうえで批判されるべき部分は批判すべきでしょう」(村井氏)
では、そもそも法人税とはどういったものなのだろうか。
「一般的に法人税は、株式会社などの法人の利益に対して課税される税金のこと。これに対して所得税とは、会社員の給与や個人事業主の利益に対して課税される税金をいいます。シンプルにいうと、法人税の対象は『会社の売上から経費を差し引いた儲けである会計上の利益に、税務上の調整を加えた課税所得』。
ただし、大企業に関してはこれに加えて、資本金や付加価値といったものにも課税が行われ、それらも法人税の一部とされています。ですから当然といえば当然ですが、基本的には大企業のほうが支払う法人税は多くなるものなのです」(村井氏)
では、同じ法人でも、中小企業と大企業では法人税の比率に差はあるのだろうか。
「まず、中小企業の定義は法律や制度によってさまざまですが、法人税法では、資本金が1億円以下であれば基本的には中小企業(中小法人)、資本金が1億円超であれば大企業(大法人)とされます。
そして、法人税率の差についてですが、大企業には資本金や付加価値も加わるので、課税所得に対する税率の違いだけでは一概にいえませんが、中小企業への現在の法人税率(実効税率)は25~33%程度と幅があり、所得の多さで決定される一方、大企業は所得の多さにかかわらず、課税所得に関していえば現在は一律で30%程度と定められており、所得が小さい場合には中小企業のほうが低い税率となりますが、その差は、現在はさほど大きくなく、場合によっては中小企業のほうが高い税率となることがあります。
これは、中小企業で所得が小さい法人については、税負担を軽くするための措置があるものの、国際競争等を背景として、政府が年々、大企業の法人税率を引き下げているためです。大企業優遇の税率改正が行われていることは否定できませんが、中小企業に対して一方的に有利な税率とはなっていません。」(村井氏)
大企業が法人税を減額できる“4つの制度”とは?
では、なぜ「大企業が法人税逃れをしているのでは?」という指摘が多いのだろうか。
「大企業の所得に対する30%程度の税率は、各大企業の形態や状況を加味した特別措置がない場合の話で、実際は各企業によって異なります。その特別措置に対して批判が増えることもあるのです。
1つめは、『受取配当金の益金不算入』です。昨今の大企業の多くは、複数の子会社を持つホールディングス企業となっているケースがほとんどです。この形態の場合は、各子会社が得た所得に対して法人税が課せられ、その後残った収益の一部を持株会社である親会社が配当金というかたちで吸い上げています。このとき、すでに各子会社が法人税を支払っているため、その配当金には課税されないのです。○○ホールディングスやグループ企業の親会社が法人税支払いゼロとよく言われるのは、この持ち株会社だからという理由が大きいです」(村井氏)
要するに、親会社の利益がどんなに大きくても、支払う法人税は少なくなるという。二重課税を防ぐ意味では正当性はあるが、大企業の親会社は税金を支払う力(担税力)が大きいことから、受取配当金を含めて課税をすべきという意見もある。
「2つめは、『欠損金の繰越控除』という仕組みです。これは、過去の赤字と現在の黒字を通算し、黒字の年は過去の赤字を差し引いた額で所得を計算し、法人税を課すというものです。これは中小企業にも適応される制度なのですが、赤字を出した中小企業の多くは倒産してしまうので、何年も赤字続きでも耐えられる経営体力を持った大企業ばかりに適応されるという側面があります。また、大きなグループ企業であれば、子会社や他事業の欠損金を黒字の事業から差し引くことによる節税も可能です。ソフトバンクグループの例でいえば、株式を移管するなどにより、投資事業において税務上の欠損金を発生させ法人税の支払い額を減らしていました」(村井氏)
ただ最近は、この欠損金の繰越控除の控除額にも、一定の制限が設けられるようになったという。
「3つ目は『輸出戻し税』です。もともと国内で企業が取引を行う場合、例えば100円の売上に対して10%の消費税が加算された110円を消費者から受け取ります。この100円の売上に対して、商品製造時に税抜80円プラス消費税8円の経費がかかっていたとすると売り上げた際に預かった消費税10円から、経費にかかった消費税8円を差し引いて、2円の消費税を企業が納税する必要があります。
ですが、取引先が海外の企業の場合は、商品に消費税をかけられないので、製造時にかかった消費税を企業が丸々負担しなければならなくなるのです。企業側がそれを見越して商品を値上げすると、海外で消費税を課税することになってしまうので、輸出品を扱う企業には、製造時の消費税を国が還付するというものです。
これは一見すると、国が海外と取引している企業に多額の助成金を出している構図のようにみえますが、形式上は正しい仕組みです。ですが、企業側が商品製造の際に、部品の製造業者などに消費税分を差し引いた金額で部品を交渉することもあり、そういう取引が成立した場合、大企業側は消費税の還付を国からの助成金のように受け取れることになりますし、そうした面で批判があがるのは致し方ないかもしれませんね」(村井氏)
下請けの製造業者などに対して、消費税分を差し引いた額で交渉し、消費税還付を助成金のように受け取るという事例も、実際発生しているようだ。
「4つめは、『租税特別措置による減税』です。これは、景気向上の名目で企業に対して行われるさまざまな減税措置の総称です。一例ですが、とある企業が研究開発の目的で多額の投資を行った場合、国がその投資額を鑑みて減税してくれる、というものです。これも中小企業にも適用されるものですが、こうした大規模な投資は実質的に大企業しかできません。この仕組みで年間1000億円超の減税を受けている大企業もあり、この点は批判の対象になりがちなのもうなずけます」(村井氏)
高まる中小企業への負担と、大企業批判が起きるワケ
こうした実情のなかで、中小企業はインボイス制度の導入でさらに苦しめられるという。
「インボイス制度は2023年の10月1日から導入予定の、適格請求書等保存方式とも呼ばれるもので、領収書や請求書に軽減税率によって、8%と10%に分かれた消費税額のどちらが適応されているかを明記しなければいけない制度です。これにより、今まで取引の際に手元に来た消費税を納税しなくていい(実質利益に還元できる、『益税』とも呼ぶ)とされてきた、年間売上1000万円に満たない中小企業や個人事業主は、消費税を納めない限りインボイスを発行できなくなり、益税を得たままでのビジネスが事実上できなくなるとされています」(村井氏)
以上のように大企業が批判を受けるのは、デフレが続く日本では直接税より間接税が増えているという背景があるとの指摘もなされている。
「企業や個人の所得に左右される直接税に対し、消費税や酒税などに代表される間接税は、国からしてみれば景気の変動に影響されにくい安定した税収といえます。ですから不景気な今は間接税の割合を増やしたいという側面があります。しかし景気が安定して大企業からの直接税の割合を高められるかたちに、いつ移行するかは不透明です。そのなかで今回解説したような法人税への特別措置等は、高所得者優遇として目立ってしまい批判されるのかもしれません」(村井氏)
大企業が法人税の納税額を減額できる制度は批判されがちだが、なぜ国がこうした制度を整備しているのかを理解して、建設的な議論をする必要があるといえよう。
(文=A4studio)