スーツ不況でもオーダーメイド活況…ワークマンやAOKI、4千円台“ワーク”スーツ人気

国内スーツ市場で売上高トップを誇る青山商事の大規模リストラが注目を集めている。郊外型ス―ツ専門店として創業しカテゴリーキラーとして急成長し、1998年には「スーツ販売着数世界一」のギネス記録認定を受けた同社だが、400人程度の募集人数の希望退職に609人の応募(2月22日時点)があったと発表。2021年3月期には初の営業赤字となる見通し。22年3月期までに全店の2割にあたる160店の閉店も進める。
業界第2位のAOKIホールディングス(HD)も21年3月期は53億円の最終赤字を見込んでいる。革靴大手のリーガルコーポレーションも、3月19日までを期限に100人の希望退職者を募集している。小島ファッションマーケティングの推計では、コロナ禍に見舞われた20年の国内スーツ販売は約400万着。ピークだった1992年の1350万着と比較すると70%減となる。2018年と比較しても40%減となる。ビジネスマンのユニフォームとしてのメンズスーツの現状分析から、市場とメンズスーツ文化の将来を見てみたい。
1.戦後スーツ市場の歴史と原点回帰傾向
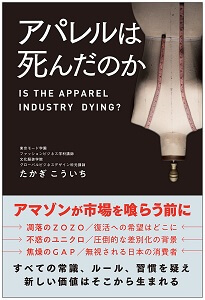
メンズスーツの原型は19世紀のイギリス上流階級で生まれた。日本では、明治時代に軍隊、警察の制服から採用され、西南の役で着用された軍服が払い下げとなり、着物より機能的で動きやすいとして東京で普及した。しかし、当時の日本でも洋装は、特別な階層が着用するものであった。皇室男性の服装スタイルが典型的な伝統的英国スタイルなのは、明治時代からの脈々とした伝統が踏まえられているからである。天皇陛下がスーツのベストドレッサーであるのは、世界が認める事実である。
メンズスーツは本来、顧客一人ひとりに合わせてつくられる「誂え服」で平均月収以上の価格であった。1950年代末に第1次産業と第3次産業の就業人口が逆転し、1959年に大丸百貨店(現Jフロントリテイリング)が国内百貨店初の紳士既製服「トロージャン」を誕生させた。以降、経済成長とメンズスーツ既製服市場は並行して成長した。
その間に、郊外型スーツ専門店による製造・直販流通が一般化し、スーツは食品の卵とならぶ戦後の物価優等生となった。バブル崩壊後の1990年代から2000年代のIT産業台頭のなかで、ビジネススタイルのカジュアル化が進んだ。2005年には環境省主導で「クールビズ」と呼ばれる、ドレスコードを無視したスタイルが推奨され、ますます日本のメンズスーツ需要とファッションリテラシーが失われた。
そして2020年のコロナ禍が、メンズスーツの年間最実需期である3~4月の店舗閉鎖、そして毎日の出社習慣を大きく変えた。それらがビジネススーツ業界に積み重なっていた諸問題を一気に表面化させた。
婦人服と違い変化の少ないビジネススーツは、長い歴史のなかで育まれてきたルールと文化を反映した商品である。日本は、西洋から伝わり日本で進化した自動車や西欧料理のように、日本人特有のスーツ文化を育てている。どんな流行があろうが、完成されたグローバルなビジネススーツスタイルが今も存在する。
大きく落ち込む既成メンズスーツ市場だが、面白い現象がいくつか見て取れる。ひとつは、オーダースーツブームである。オーダースーツ専門店は、生産から販売に至るDX(デジタルトランスフォーメーション)が支える低価格も武器となっている。タンゴヤ(本社大阪市)が展開する「グローバルスタイル」は、コロナ禍をものともせずに21年7月期に過去最高の売上93億円を目指している。オンワードHDもオーダースーツ・シューズのKASHIYAMAに注力し急成長を目指している。
メンズスーツは1950年代と同じ「誂え服」に回帰したが、価格だけは優等生を続けることで生き残る。誂え服を一度でも着た人は、既製服は着られなくなる。自分の体型に合わせた着心地を憶えれば、必ずやリピーターになるからである。
2.異業種新興企業に再定義されたスーツスタイル
また、他業種からの新規参入も注目を浴びている。従来のメンズスーツと呼ばれるものは、テーラード技術である身頃の一部分が折り返って、カラー(衿)と接続するテーラード・カラー (背広衿)や肩部分のパッドが入るスタイルである。しかし最近、作業着機能とスーツ風のデザインを兼ね備えた「作業着スーツ」と呼ばれる商品の売上が急伸している。
服飾史的には、上流階級を起源とするスーツスタイルと労働者階級の作業着は、素材・製法・目的がまったく違うものであった。しかし、新素材の開発、進むカジュアル化、よりコンフォータブルな服への需要の高まりと、スーツ市場は大きな転換期を迎えている。
オアシススタイルウェアが販売するスーツ型作業着「WORK WEAR SUIT(ワークウェアスーツ)」は、水道工事会社の社内向け制服として開発された「デートに着ていける作業着」がコンセプトの商品である。18年から一般販売が始まり、21年2月期には売上高10億円を見込んでおり、今も他社からの協業依頼が引きも切らない状況が続いている。
主力のスーツ販売が不振の青山商事も、スーツと作業着の融合をコンセプトにセットアップスーツを販売。ワークマンは、リバーシブルワークスーツとして多機能なスーツながら上下4,800円で販売。AOKIは、スーツ専門店の縫製、生地を売り物にアクティブワークスーツとして2月に上下4,800円(税込・以下同)で発売し、第3弾予約も即完売した。工具販売のモノタロウはPBスーツを上下2万円弱の中間価格帯で展開し、企業受注で手堅く成長している。
3.まとめ
低価格の新スーツスタイルが日常着として、あるいは作業着として浸透している。かたや、おしゃれ着としてのオーダースーツが、若い世代からの支持を集めている。会社員の制服としてのスーツの概念は変わりつつあるが、長い歴史を持ち完成されたスーツスタイルは、なくならない。業界で「丸縫い」と呼ばれるフルオーダーは、顧客ごとに型紙から仕上げてゆく職人仕事だが、高価であっても再評価を得るだろう。
スーツは、素材ひとつとっても個別に特徴があり、AI(人工知能)ですべてを解決するには深すぎる世界である。いき過ぎたカジュアル化からオーダースーツの再評価により需要が戻ったのは、揺るぎない事実である。メンズスーツ業界もファッションの素晴らしさと楽しさを消費者に発信して、誰もが手に入る喜びを増幅させてほしい。どんなに時代が変わっても、洋服は着替えるだけで人を幸せにできる魔法でもあるのだから。
(文=たかぎこういち/タカギ&アソシエイツ代表、東京モード学園講師)











