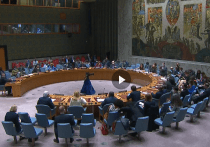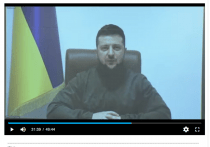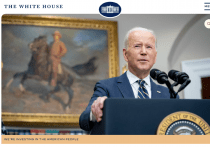世界のドル離れ加速、揺らぐ基軸通貨…リーマンショック級の経済危機再来に警戒
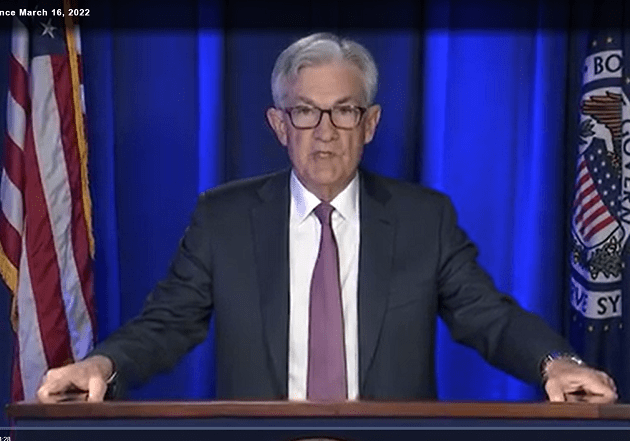
歴史的なインフレのせいで世界の中央銀行は金融引き締めに舵を切らざるを得なくなっている。米連邦準備理事会(FRB)は4月6日、早ければ5月から量的引き締め(QT)と呼ばれる資産圧縮を毎月950億ドルのペースで実施する可能性を明らかにした。資産の削減幅は前回(2017~19年)のピーク時の500億ドルを大きく上回る。足元で生じている40年ぶりのインフレに対するFRBの警戒感のあらわれだ。FRBは3月に約3年ぶりとなる利上げにも踏み切っている。
短期金利の急騰を招いた前回の2倍に近いペースでマネーを引き揚げることから、金融市場が大きく混乱するとの懸念が浮上している。市場では予想を上回るペースで金融引き締めが進むと見て、米長期金利(10年物の米国債利回り)は2.6%を上回り、3年ぶりの高水準となっている。これに連動して住宅ローンや社債金利の上昇も加速している。住宅ローンや社債金利は米国債の金利をベースとし、借り手の信用力などに応じて上乗せ金利(スプレッド)を加えて決まるからだ。
30年固定の住宅ローンは2018年11月以来3年5カ月ぶりに5%を上回った。ダラス連銀が3月下旬に「米国の住宅価格は再びファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)から遊離し始めている」と指摘したように、物件の値上がりを前提とした個人の資金調達が急増するなど過去の住宅バブルを想起させる動きが顕著になっている。住宅ローンの金利水準は1.6倍に跳ね上がっており、利払いの負担増で住宅購入の勢いが急減速すれば、住宅バブルが再び崩壊する可能性がある。
社債市場でも信用リスクに対する警戒感が強まり、資本調達コストが急騰している。3月の欧米の社債利回りの平均は2.8%と昨年9月末時点の1.4%の2倍となった。特に信用リスクの高いジャンク債の発行額は今年第1四半期に574億ドルと急減した。低格付け企業への融資であるレバレッジドローンも売られている。
世界の債券市場全体のセンチメントが悪化していることも気になるところだ。世界の公社債価格を示す指標も2008年の金融危機時を上回る値下がりとなっており、「米国債の40年間にわたる強気相場は終了した」との声も聞こえてくる。
ウクライナ侵攻の影響
長年、金利の低下を享受してきた債券市場が転換期を迎えているのは、中央銀行の利上げの影響だけではない。「ロシアのウクライナ侵攻によって地政学リスクが高まり、世界の経済成長を牽引してきたグローバル化が後退したことでインフレに拍車がかかる」とのシナリオが急浮上しているからだ。世界経済の分断により高インフレが定着し、金利が上昇する「債券受難」の時代が迫りつつあるというわけだ。
ロシアのウクライナ侵攻は世界の金融市場の流動性にも悪影響を与えている。2月下旬以降、世界で総額450億ドル以上の金融取引が延期又は撤回された(4月5日付ブルームバーグ)。ウクライナ危機は市場を動揺させ、ボラテイリティーと不確実性が高まるなかで投資家の意欲を減退させている。
流動性の低下は相場の値動きを荒くし、さらに取引が減るという悪循環を呼ぶ。市場の厚みがなくなれば、相場の流れに乗る「順張り」投資マネーが存在感を増し、一方向の流れができやすくなる。金融市場がかつてないほど不安定になっているのだ。
ドル以外の通貨への分散投資が加速
米国の金融市場に流動性を供給してきたのは海外勢、特にオイルマネーだ。産油国が毎年石油収入を元手に多額の米国債を購入することで基軸通貨ドルの価値が保たれてきたから、現在の国際通貨システムは「ペトロダラー体制」と呼ばれることが多い。
だが、米国がロシア中央銀行が保有するドル資産を凍結したことで動揺が広がっている。ドルを決済に使えなくなったことで事実上デフォルトに追い込まれつつあるロシアの惨状を見て、「明日は我が身」と捉え、米国との関係が良好ではない国々の間で米ドルへの依存を減らす動きが活発化するとの憶測が出ている。
1974年以来、ドル建てで石油取引を行ってきたサウジアラビアの1月の米国債保有額は1190億ドルとなり、2020年2月の1850億ドルから大幅に減少した。原油価格の高騰で潤っているのにかかわらず、米国債を買い増す動きを示していない。
米国政府はドルを経済的な兵器として使う傾向が強まったことが災いして、世界の中央銀行の外貨準備高に占めるドルの割合は1999年の71%から昨年59%に減少した。ドルは現在でも世界第1位の準備通貨だが、今回のロシアに対する制裁で多くの国々がドル以外の通貨への分散投資を加速させてしまうのではないか。
ドルが準備通貨の地位にあるおかげで米国債をはじめとする米国資産の需要が堅調だったのだが、米国自身がその基盤を毀損しているという皮肉な構図となっている。
前回のQTの際は、オイルマネーをはじめ海外勢が米国債を積極的に購入したおかげで米国の長期金利が急騰することはなかったが、今回はこの安全装置が働かない可能性がある。米国債の利回りが上昇すれば、景気減速懸念からすでに動揺している住宅や社債市場の状況はさらに悪化してしまうだろう。
ドイツ銀行は4月5日、「米金融当局はインフレ抑制のために強力な利上げを進めることから、米国は来年リセッション(景気後退)に陥る」と予測したが、リーマンショックのような金融危機が再び起こらないことを祈るばかりだ。
(文=藤和彦/経済産業研究所コンサルティングフェロー)