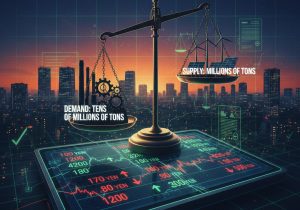中国経済が米国を追い抜くとの予測、世界で崩れる…中国が衰退期突入か、不動産危機

「中国がやがて米国を上回るとの予測は過去の外れた予言と相通じる部分がある」
このように述べるのはサマーズ元米財務長官だ(8月19日付ブルームバーグ)。半年前までは「中国経済が近い将来、米国経済を追い抜くことが自明だ」と受け止められていたが、サマーズ氏は「今ではそれほど明確ではない。1960年代の旧ソ連や90年代の日本が米国を追い越すという(間違った)予測と同様のことが現在の中国でも繰り返されるのではないか」と主張する。
たしかにこの半年で世界の中国経済に対する見方がガラッと変わった感が強い。中国人民銀行は8月22日、事実上の政策金利と位置づける「ローンプライムレート」を3カ月ぶりに引き下げた。今年3度目の引き下げを実施したが、「これにより経済が再び上向く」との期待がまったく生じてこない。
7月の人民元建て新規融資は6790億元となり、前月の2兆8100億元から急減した。新型コロナの感染拡大や不動産危機の悪化で企業や消費者が借り入れに慎重になったことがその要因だ。7月の不動産投資は前年比12.3%減となり、減少幅は今年最大となった。市場で安価なマネーがあふれているものの、財務力が低下している不動産企業の資金繰りはさらに困難になっている。当局が潤沢な資金を供給して再生を図ろうとしても経済が一向に回復しないという、1990年代の日本経済が直面した「流動性の罠」に中国経済も陥ったのではないかと思えてならない。
中国の国力の陰りが鮮明に
中国政府に対する市場の信頼感もがた落ちだ。半年前は当局による思い切った政策に対する期待が高まっていたが、今では「中国経済は脆弱さに対応できるだろうか。当局の行動は不十分で遅すぎたとの懸念がある」との声が高まるばかりだ。中国で長期金利の指標となる10年物国債の利回りが約2年3カ月ぶりの水準に低下している。足下の不安要素に加え、人口減少といった中長期の構造要因も金利の下げ圧力となっており、2002年に付けた過去最低水準に接近しつつある。急成長する経済をバックに台頭してきた中国の国力の陰りがここに来て鮮明になってきたかたちだが、このことは日本をはじめ国際社会にとってどのような影響を与えるのだろうか。
「浮上する中国」よりも「頂点を極めやがて衰退期を迎える中国」のほうが国際社会との間で大きな対立を引き起こすという指摘がある。新興大国はパワーが拡張し続ける間はできる限り目立たずに行動し、覇権国との対決を遅らせるが、成長が天井に達し衰退期が目の前に近づくと悠長ではいられなくなる。これ以上の発展を期待できなくなった新興大国が「挑戦の窓」が閉ざされる前に戦略的成果を得るため、より大胆かつ軽率に行動するようになるというわけだ。
8月上旬のペロシ米下院議長の台湾訪問を契機に、東アジアの緊張がにわかに高まっている。中国軍は台湾周辺を対象とした史上最大規模の軍事演習を実施するなど台湾に軍事的圧力をかけ、日本など周辺国を巻き込む国際問題となっているが、今後の動向を読み解く際に見逃せないのは中国国内の世論の動向だ。
中国政府がペロシ氏の訪台を阻止するための措置を採らなかったことへの不満が噴出するという異例の事態になっている。ネット空間では「あまりにも恥ずかしい」「メンツが丸つぶれじゃないか」とのコメントが飛び交っている。昨年9月の米国のアフガニスタンからのぶざまな撤退ぶりを目の当たりにして、多くの中国人は「現在の米国なら台湾を見捨てるだろう。千載一遇の好機が訪れた。台湾侵攻は間近だ」と考えるようになっており、今回の中国政府の弱腰ぶりに憤懣やるかたないのだ。
こうしたネット世論を気にしてか、中国外交部は定例の記者会見の場で「中国人民は理性的に国を愛する(理性愛国)ものだと信じている」と述べているが、中国国民の愛国感情をあおり立ててきたのは、他国を攻撃的な言葉で厳しく非難する「戦浪外交」を展開してきた外交部自身に他ならない。
ナショナリズムからショービニズムへの暴走
中国では今、ナショナリズムが猛烈な勢いで台頭しているが、ナショナリズムの風潮が強まったのは1990年代からだった。ソ連崩壊により「共産主義」という統治の根拠を失った中国政府が国民の支持を取り付けるためにナショナリズムを利用したのが始まりだ。中国のナショナリズムはリーマンショック後に中国が世界経済を牽引するようになると攻撃的なものに変わり、2012年に誕生した習近平政権が「中国の夢」を語るようになるとその傾向はさらにエスカレートした。
中国のナショナリズムは政府に奨励されてきたが、最近では国民のほうが過激になっており、皮肉にも政府は自らつくりだしたナショナリズムを制御できなくなっている。気がかりなのは「中国文明は世界で一番優れている」と信じ、ナショナリズムの傾向が強い若者の雇用をめぐる状況が過去最悪になっていることだ。ナショナリズムがショービニズム(好戦的愛国主義)へと暴走してしまうことは過去の歴史が教えるところだ。
3期目の続投を目指す習近平指導部は5年に一度の共産党大会を年内に控え「台湾侵攻」というギャンブルに出る可能性は低いとの見方が一般的だが、衰退期を意識し始めた中国政府が国民の不満をそらすために対外的な強硬手段に出る可能性がこれまでになく高まっていると言わざるを得ない。
軍事専門家が指摘するように、「台湾有事」は「日本有事」に直結する。日米同盟を強化していくのはもちろんだが、台湾有事をなんとしてでも回避するための日本の外交力の真価が問われているのではないだろうか。
(文=藤和彦/経済産業研究所コンサルティングフェロー)