早稲田・MARCHら有名私立大学、一斉に合格者実質減の理由…地方の文系私大は存亡の危機
 早稲田大学の大隈講堂(「Wikipedia」より/Arabrity)
早稲田大学の大隈講堂(「Wikipedia」より/Arabrity)
大学の経営に強い逆風が吹いている。少子化にもかかわらず大学の数は増えており、今後は淘汰が加速していくことになりそうだ。もはや、各大学のサバイバル戦略は待ったなしといえる。
昨年11月に『大学大崩壊 リストラされる国立大、見捨てられる私立大』(朝日新書)を上梓した教育ジャーナリストの木村誠氏は、大学崩壊の理由について4つのポイントを挙げる。「近年、定員割れを防ぐために大学のスモール化が進んでいる。淘汰されないためには、地域連携や大学改革がカギとなる」と語る木村氏に話を聞いた。
大学が大崩壊する4つの根拠
――本書で「大学の崩壊が始まった」と主張されていますが、その根拠について教えてください。
木村誠氏(以下、木村) 大学崩壊の主な要因は「18歳人口の減少」「4年制大学の増加」「大学財源の減少」「大学教育と社会的ニーズのズレ」の4点です。
まず、少子化により、2018年から大学を受験する学生が大きく減少する「2018年問題」が本格化しています。一方で、学生数が減っているにもかかわらず大学の数は増えています。そして、これが最大の要因ですが、大学向けの国家予算が減少しています。国立大学は運営費交付金が、私立大学は私学助成金が、それぞれ減少しています。その結果、大学の財政基盤は脆弱になり、財政状況が逼迫化しているのです。
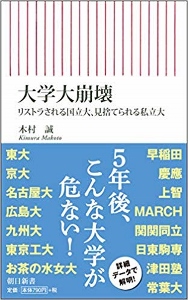 『大学大崩壊 リストラされる国立大、見捨てられる私立大』(朝日新書/木村誠)
『大学大崩壊 リストラされる国立大、見捨てられる私立大』(朝日新書/木村誠)対策として、私立大学は学費を上げて運営費をまかない、国立大学は非常勤講師を増やしたり研究・教育費のリストラをしたりしています。今や大学も市場競争にさらされ、地の利を得るところにお金と人が集まっているのが実情です。
特に苦境なのが、教育系や人文科学系など文系の地方の単科大学です。これらの大学は必ずしも企業が喜ぶような研究をしているわけではなく、他大学と比べて科研費など競争的資金の獲得において不利な立場です。昨今の国立大学文系不要論も「大学では企業が求めるスキルのある人材を養成すべき」との風潮が背景にあり、文部官僚の中には以前から「旧帝大系を除き、人文系学問を国立大学でやる必要はない」という意見がありました。
今や4年制大学の進学率は55%になりますが、そこで行われる大学教育が社会的ニーズに対応していないという問題があるわけです。
――実践的な職業教育を行う専門職大学については、どうお考えですか。
木村 教育と企業のニーズをマッチさせるために、文部科学省は専門職大学において「実務家教員の登用促進」を提案しました。実務家教員とは「専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者」と定義されており、いわば企業から大学へ人材を流出させる仕組みです。しかし、この人手不足の時代に企業が優秀な人材を手放すはずがありません。定年間近で古い技術しかないようなエンジニアなら企業も手放すかもしれませんが……。つまり、専門職大学も矛盾を抱えてしまっているのです。
定員割れを防ぐために“スモール化”する大学も
――昨年、日本大学商学部は入学定員の大幅超過により補助金が没収され、他大学にも激震が走りました。
木村 文科省は18年度から私学助成金の交付基準を厳格化し、入学者数が定員の10%を超えた場合は補助金を全額カットするとしていました。日本大商学部は定員超過率19%で、最終的に6億円の補助金が没収されたといわれています。当時、日大の臨時理事会は大荒れになって商学部関係者は吊るし上げられたそうです。他学部に影響はなかったのですが、文科省の本気度が明らかになったといえます。
これからは「数名でも定員をオーバーすると私学助成金が減額されるかも」と私大の入試セクションはおののいているでしょう。入学式前夜に欠員を出さないため、追加合格(補欠合格)で徐々に補充するテクニックが必要になるかもしれません。
今後も、早慶クラスが一般入試の募集人員を減らし、MARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)も定員を厳格化し合格者を絞り込む傾向は続くでしょう。かねてから学内併願が多い早稲田大学の政経学部などは第1志望者の多いAO入試などに力を入れ、一般試験の枠を狭くしていく方針です。他学部や他大学でも入学率の読みが難しい一般入試より、他大学との併願が少ないAOや系列校、指定校推薦などの枠を広げる動きが出てくると思います。
――本書では、「大学のスモール化」についても指摘されています。
木村 都心部では上位校が定員を厳格化したことで、学生は下位校も受験するケースが増え、ひどい定員割れは解消しつつあります。
問題は地方の大学です。地方では18歳人口そのものが大きく減少しており、さらにその少ない若者が都心の大学に流れていくため、状況が改善される可能性は低い。そこで、収容人員を減らし、スモール化を図って定員充足率の低下を防いでいる大学もあります。ただし、それは受け入れる学生を減らすということなので規模の縮小につながり、最終的には命取りにもなり得ます。地方の中小私立大学は、もはや大学だけで経営を改善するのは難しいでしょう。
また、地方の大学で研究や教育の実績をつくった大学教員が、退任して東京に戻るケースもよくあります。その理由は、給料が上がらないこと、十分な研究環境が確保されていないといったことです。一般企業であれば実績を上げると給料も上がりますが、地方の私立大学には事務員の給料すらおぼつかないところもあるのが実情です。極端にスモール化していたり収容定員充足率が改善されていなかったりする大学は要注意といえるでしょう。
――そのスモール化から抜け出して反転攻勢に出た大学はありますか。
木村 神奈川県厚木市の松蔭大学が好例です。同大は定員充足率が全国でも最低ランクだったのですが、逆に定員を増やしました。さらに定員充足率が低くなると思われましたが、2年ほど前に看護学部を創設したこともあり、定員充足率はむしろ改善しています。スモール化を避けるためには、学生のニーズに合致した学部を創設するなど大学の改革を行うことが肝要です。
潰れる大学と生き残る大学の違いとは
――増えた結果、淘汰され潰れる大学も多いです。
木村 大学の倒産を避けるためには、地域の理解や連携が必須です。地方で生き残っている事例を見ると、大学法人でありながら実際の学校法人全体の運営は高校が主体に行っているケースがあります。地方に多いのですが、まず高校ができ、その後で「大学も必要」ということで大学を新設したケース。その場合、学生は高校から大学にうまくスライドしていけば経営的にも安定します。
たとえば、京都の福知山公立大学はもともと福知山成美高校を主体とする学校法人が運営していました。それを公立化で地元の自治体が引き受け、定員割れは解消し、今は新学部の増設を計画中です。これは地域連携が成功した好例です。
関西では関関同立(関西、関西学院、同志社、立命館)が次々と系列校を創設していますが、その狙いは受験生の獲得です。関東でも、日大をはじめ、駒澤大学や専修大学が地方に付属校があるのは有名です。一方で、単独の大学法人で定員割れのケースは厳しいでしょう。
――経営的に不安定な大学の特徴などはありますか。
木村 地域との連携がまったくない大学は厳しいです。地方では昔の名士が大学を創設するケースもありますが、時代の変化に沿った教育プログラムを組んでいればいいものの、「昔のままでいいだろう」という感覚では危険です。
また、私立大学経常費補助金交付額の中に、一般補助とは別に特定の分野や課程などにかかわる教育・研究の振興を図るための「特別補助」があります。医療系を除き、この特別補助の交付額がゼロの大学は教育研究活動が低調の場合も多く、経営が厳しいといっていいでしょう。また、学校法人の財政状態を見る場合、将来の投資や改革のために必要となる「基本金」も経営の健全度を計るバロメーターになります。
(構成=長井雄一朗/ライター)
『大学大崩壊 リストラされる国立大、見捨てられる私立大』 大学が殺される――! 疲弊した全国の大学は国立も私立も、多くが崩壊寸前だ。有名校も安閑としてはいられない。最新データを駆使して、その病巣をえぐる。関係者には「不都合な」数値も分析し、ダメ大学、オススメ大学を実名で明らかにする。OB、受験生、保護者必読。











