造船大国ニッポンの象徴・三井E&S、造船から事実上撤退…日本勢、中韓勢に完敗
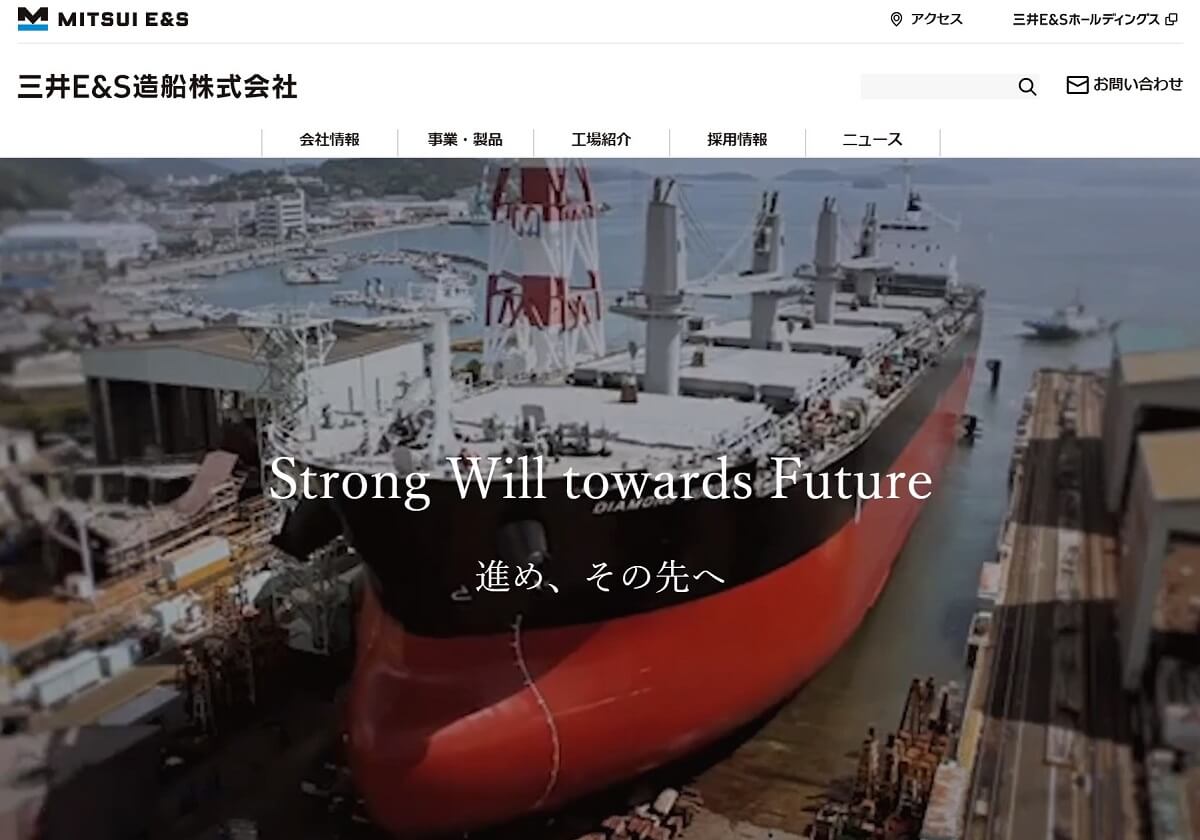
政府が造船と海運業を金融支援する。政府は世界の造船市場のシェアを拡大する韓国と中国に対抗して、造船業界に大規模な金融支援を実施する方針を固めた。産業基盤を維持し、海上輸送力を確保する。船舶を購入する特定目的会社(SPC)を海外に設立し、政府系金融機関を総動員して資金を供給する。日本国際協力銀行(JBIC)はSPCに直接融資し、日本政策投資銀行(DBJ)はSPCに融資する民間銀行に公的保証を付与するなど、可能な限りの手段を尽くすとしている。
政府系金融機関などの資金でSPCが船舶を購入。海運会社はSPCを通じて運用船舶を買い取ったり用船したりする。低利で資金を借り入れたSPCは、低価格での用船が可能になる。この結果、海運会社が日本の造船会社から船舶を調達する割合も増える。一石二鳥、いや一石三鳥の青写真が描かれている。
韓国や中国勢の攻勢が続く造船業は消滅の危機
低迷する日本の外航海運・造船業の支援策を検討するため、赤羽一嘉国土交通大臣は5月20日、交通政策審議会へ諮問。これを受けて7月2日、国際海上輸送部会と海事イノベーション部会が合同会議を開いた。日本の外航海運、造船業の活性化に向けた施策を審議し、11月末まで方向性をまとめて、答申することとなった。
合同会議の冒頭、国交省の大坪新一郎海事局長は「外航海運、造船業はわが国の経済安全保障上、必要不可欠な産業だ。両業界が共に好循環を生み出し、成長していくためにどのような方策を講じるべきか議論していただきたい」と強調した。
日本の造船業が消滅するかもしれないという危機感が、政府を突き動かした。日本の造船業の世界シェアは受注量基準で2015年の32%から19年には16%とわずか4年半で半減した。韓国と中国の低価格攻勢に晒され、思うように受注できなくなったからだ。日本の海運会社が日本の造船会社に発注する割合も、14~18年に75%まで落ちた。1996~2000年には94%に達していた。大規模な金融支援が、窮地に陥った造船・海運が国際競争力を向上させる近道なのだ。
19年の世界の造船会社の建造量ランキングのトップは韓国の現代重工業、2位は中国船舶集団、3位が韓国の大宇造船海洋。いずれも政府主導による再編が行われてきた。中国船舶集団は中国船舶工業集団と2位の中国船舶重工集団が19年11月経営統合した。いずれも国有企業だ。韓国でも現代重工業と大宇造船海洋が統合作業を進める。統合によって生まれる両国の新会社2社だけで、世界の4割のシェアを握ることになる。これでは日本勢は太刀打ちできない。
韓国政府は大宇が2015年に経営難になって以降、1.2兆円規模の金融支援を実施。その後も受注拡大のため政府支援を続けてきた。日本政府は、韓国が自国の企業に国際ルールに違反する過剰な公的支援を行っているとして、世界貿易機構(WTO)に2度にわたり提訴した。現代重工業と大宇造船海洋の経営統合は、各国の独禁法当局が審査を進めているが、コロナ禍もあって当初計画より手続きが遅れている。
中韓の政府支援を強く批判してきた日本政府が造船業の金融支援に乗り出すことに関して、政府高官は「このままでは消滅しかねず、WTO協定に違反しない範囲内で政府が手を差し伸べるしかない」と苦しい胸のうちを明らかにした。
三井E&S、造船から撤退
三井E&Sホールディングス(HD)はツネイシホールディングス(広島県福山市、非上場)と、造船子会社同士が資本提携する方向で協議に入った。三井E&SHDが子会社・三井E&S造船(東京・中央区)の株式の一部をツネイシ傘下の常石造船(広島県福山市、非上場)に譲渡する。三井E&S造船と常石造船は18年に業務提携した。資本提携に踏み込むことになったことについて、三井E&SHDの岡良一社長は「常石造船と協業して、グローバルで中小型のばら積み船市場をけん引する」と語った。出資比率などは今後詰めるが、常石の資本参加後も三井E&SHDは三井E&S造船の過半以上の株式を保有する方針で、親会社の地位は維持する。12月をめどに合意をめざす。
あわせて、玉野艦船工場(岡山県玉野市)での商船建造からの撤退を検討していることも明らかにした。千葉工場(千葉県市原市)での商船建造を21年3月末に終了する。6月中旬には護衛艦などの艦艇事業を防衛最大手・三菱重工業に売却する協議を始めた。年内にも最終契約を結び、21年10月末までに手続きを完了する予定だ。
三井E&SHDの艦艇を含む船舶事業の売上高は1151億円。これがなくなる。岡社長は「(造船事業は)設計が中心となる」としている。三井E&SHDはインドネシアでの火力発電所工事での大幅な損失計上で業績が悪化し、資産売却や1000人規模の人員の削減を進めてきた。造船事業も20年度(21年3月期)まで6期連続の営業赤字を見込む。完全子会社の三井E&S造船の受注は官公庁からの艦船1隻にとどまる。
三井E&SHDの21年3月期の売上高は前期比19.9%減の6300億円、営業損益は100億円の赤字(前期は620億円の赤字)、最終損益はゼロ(同862億円の赤字)を見込む。大幅赤字の原因だったインドネシアの火力発電所の採算は改善するが、原油安や新型コロナウイルスの影響による子会社・三井海洋開発の業績悪化が痛手だ。
三井海洋開発は20年12月期の最終損益の予想を100億円の赤字に下方修正した。従来予想の120億円の黒字から一転して赤字転落だ。三井E&SHDは三井物産造船部としてスタートしたが、造船からは撤退することになった。
非上場の専業メーカーが造船再編の主役だ
造船大手が中韓勢の攻勢に打ち負かされるなか、海外の造船所の活用などで競争力を磨いてきた専業メーカーが造船再編の主導権を握る。建造量の国内ランキングによると、常石造船は4位、三井E&S造船は8位。両社の建造量を合わせると、川崎重工業を抜き、首位の今治造船(愛媛県今治市、非上場)、2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU)に次いで3位になる。ツネイシHDは瀬戸内海の造船所以外に中国やフィリピンでも造船所を運営し、海外進出の先駆的存在だ。
ツネイシHDは1903(明治36)年、創業者の神原勝太郎氏が海運業(現・神原汽船)を興したのがルーツ。1917年(大正6)年、塩浜造船所(現・常石造船)を創業し、造船業に進出した。同族経営を貫いており、ツネイシHDの神原宏達社長は創業者の直系の四代目。神原家は長年、地元選出の宮澤喜一元首相を支援してきたことで知られる。
ツネイシHDの2019年12月期の連結売上高は前期比4.3%増の2287億円。3期連続で増収を達成した。主力の造船事業は7.5%増の1646億円。建造隻数は18年から6隻増えて46隻だった。ばら積み船を得意としていたが、コンテナ船などにも船種を広げたことが奏功した。
連結利益は開示していない。単体の決算公告によると、常石造船の最終損益は56億円の赤字、ツネイシHDのそれは43億円の黒字。海運事業などほかの事業が黒字化に貢献したことがわかる。
日本の造船業は2000年前後には三菱重工業など重工系の大手が建造量の6割を占めていた。その後は今治造船や常石造船など専業系が伸び、19年には専業系が6割を握った。国内造船最大手の今治造船(愛媛県今治市、非上場)は10月にも、2位のジャパンユナイテッド(JMU)に3割を出資する。三菱重工は創業の地である長崎造船所の香焼工場(長崎市)を大島造船所(長崎県西海市)に売却する。
戦後の高度成長を支え、「造船王国」を謳歌した日本の造船業は中韓勢に土俵際まで追い詰められた。政府の支援をバックに今治造船、常石造船の専業系が“造船ニッポン”の復活を担う。ただし、大型再編・造船所の整理に大ナタを振るう必要がある。税金でゾンビ造船会社を延命させてはならない。
(文=編集部)










