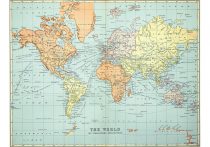全国に乱立する「日本最古の●●」、根拠崩れる例が相次ぐ…単に“古さ”競う意義乏しく

人口減少や少子高齢化に悩む地方自治体の町おこしの切り札として各地で利活用されている歴史的文化財。他地域にある同様の施設や物産との差別化を図るため、郷土歴史研究家らの提言を踏まえて“日本最古”“日本の〇〇発祥の地”というキーワードを多用されがちだ。だが、その流れに一石を投じる記事がNHK NEWS WEB上で公開された。
28日に公開された記事『「日本最古じゃなかった」正直に言うべきか、どうしよう…』では、兵庫県豊岡市にある“日本最古の時計台”として観光パンフレットなどで紹介されてきた時計台「辰鼓楼」がクローズアップされた。時計設置140年の節目に当たる今年、コロナ禍で集客に悩む地元のそば店店主が余暇を使って古文書を調べたところ、辰鼓楼の設置は札幌市の時計台の27日後だったことがわかり、「堂々と日本で2番目と名乗る」ことになったのだという。
日本最古の“灯台”はどこなのか
“日本最古”というキーワードは魅力的だが、前出の「辰鼓楼」の事例のように、いざ“そうでなかったこと”がわかると大きな影響がでる。どの部分を持って“日本最古”とするのかは重要なポイントでもあるようだ。
例えば、青森県野辺地町の常夜灯公園に建つ「浜町の常夜灯」。かつて盛岡藩の“野辺地湊”に寄港する北前船の夜間の目印として文政10(1827)年に同港湾部に建立されたもので、同県や同町は「現存日本最古の常夜灯」とPRしている。一見、「日本最古の灯台」と読み取れるかもしれないが、どうやらそうではないらしい。
例えば青森と同じ東北地方にある山形県酒田市の「日和山公園の常夜灯」は、文化10年(1813年)年、酒田に寄港する北国廻船の航海安全を祈願して建てられたのだという。野辺地のもののように、実用性のある灯台機能を目的に建立されたものかどうかは定かではないが、酒田市教育委員会の担当者によれば「日和山公園内で移設はしているが新築はしていない。建立当初のものです」と説明する。
一方で、常夜灯型ではない灯台としては、福井県敦賀市の「洲崎の高燈籠」は享和2(1802)年の建立で、同市の観光案内では「日本海側最古の石積み灯台」と銘打たれている。また、兵庫県明石市の「明石港旧灯台」は明暦3(1657)年に建立されたとされる。灯明台型の石造り灯台の中では数少ない遺構という。
ちなみに航路標識に関する知識啓発や灯台に関する歴史的文献などを収集している公益社団法人燈光会(東京都)の公式サイトによれば、最初の洋式灯台は観音埼灯台(神奈川県横須賀市)で明冶2(1869)年1月1日点灯、最古の石造り灯台は樫野埼灯台(和歌山県串本町)で明治3(1870)年6月10日点灯となっている。
同会事務局の担当者は「現在、海上保安庁の管轄下にある現役の灯台のうち、最初の灯台が観音崎灯台です。現在は3代目ですが、告示された年月日を記載しています」と話す。
当編集部が調べただけでも、どの部分を“日本最古”と打ち出すかによって違うものの、”日本最古”と言えそうな文化財が多数あった。専門的な見地からみた“日本最古の灯台”や“常夜灯”は他にもあるのかもしれない。
古さのランキングより地域全体の歴史のオリジナリティー
JRグループの大型観光宣伝事業「デスティネーションキャンペーン」を担当したことのある元JR東日本関係者は次のように語る。
「各自治体の皆さんや郷土歴史家の方々が文献調査やフィールドワークによって、地域の魅力を再発掘してくださっています。文化財は大きな観光資源にもなります。昔から各地域で守られてきた史跡に加え、そうした努力が全国的に行われているからこそさまざまな“日本発祥の〇〇”や“日本最古の〇〇”が掘り起こされているのではないかな、と思います。
あくまで観光誘客事業に限っていえば、複数の文化財やその土地の伝統的な文化を組み合わせた『ストーリー』としてお客さんに見せることの方が重要だと思っています。ひとつひとつの観光資源や文化財が“日本最古”であったり、“唯一”であったりする必要はありませんし、ある文化財が他の地域のものより“何年古いか”などを比べて、『勝てる部分』を探す必要もないと思っています。だから、“日本最古”ではないことが判明したとしても、マイナスにとらえる必要はないと思います。
古さのランキングを競うより、その資源を含めた地域全体のオリジナリティーを競うことが重要なのではないでしょうか。地域に“日本最古”の文化財がポツンとあったとしても、それだけしか見るものがなければ、お客さんは来てくれません。
歴史的な建造物や遺構であれば、それを軸に他の文化財や伝統芸能、特産や郷土料理などを組み合わせると、ほぼどこの地域でも独自性が出るものです。要は、物を見せるのではなく、どのように地域が育んできた歴史や文化を見せるのかということではないでしょうか」
(文=編集部)