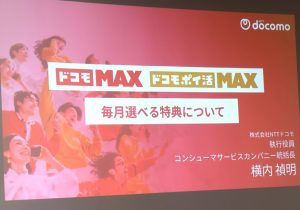最高裁判所裁判官国民審査はなぜ重要か、注目すべき点は…江川紹子のチェックポイント
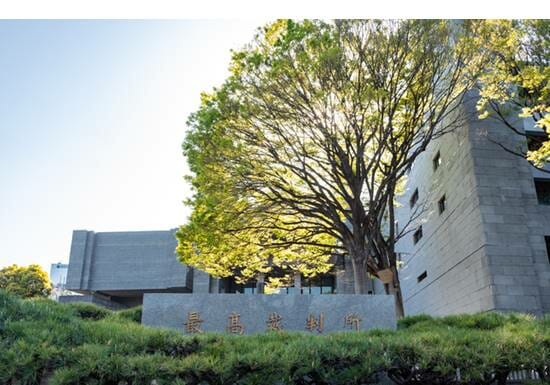
10月31日投開票の衆議院議員総選挙では、同時に最高裁裁判官の国民審査が行われる。裁判官たちに、今後もこの仕事を続けてもらうかどうかを国民が投票によって判断し、結果次第では、裁判官を辞めさせることもできる重要な制度だ。今回は、全部で15人いる最高裁裁判官のうち、前回の総選挙以降に就任した11人が審査の対象になる。
国民審査に関する情報発信に消極的な最高裁
日本国憲法では、最高裁の裁判官は「任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙」と「その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙」で国民審査を受ける、と定められている。ただ近年は、多くの裁判官が60歳過ぎてからの就任で、70歳が定年のため、2度目の審査を受けずに退職するケースがほとんどだ。
国民審査で投票した人の多数が「辞めさせたい」という意思表示すると、その裁判官は罷免されることになっている。これまで罷免された例はないが、それは必ずしも国民が最高裁裁判官を信任してきた、ということを意味していない。
というのは、国民審査の投票用紙にはあらかじめ対象裁判官の名前が印刷され、「辞めさせたい」人に「×」印をつける、というやり方で行われるからだ。そのため、積極的な信任の意思表示はできない仕組みだ。「この人はぜひ続けてほしい」という人がいても、決して「○」印をつけてはならない。「×」以外を記入すれば、それは無効票になってしまう。
「続けてほしい」人も、「よくわからない」という場合も、同じ無印にするしかなく、こうしたやり方は、投票する国民の側からすると、実にわかりにくい。本当は、「辞めさせたい」人には「×」、「続けて欲しい」人には「○」、「わからない」という場合には無印のままとすれば、国民は意思表示をしやすい。裁判官が国民からどれほど信任されているかもわかりやすい。にもかかわらず制度改正の議論が起きないのは、国民審査に対する関心度の低さも一因だろう。
そしてその原因は、メディアと最高裁の姿勢にある、と思う。新聞もテレビも、総選挙に関しては、各選挙区での情勢分析、候補者らの主張や選挙活動、各政党の公約や獲得議席予想など、さまざまな情報を伝えるのに、最高裁国民審査に関する情報はわずかだ。
最高裁も、各裁判官に関して国民が理解しやすい情報を提供することに、消極的だ。最高裁のホームページを探せば、全裁判官のプロフィールは掲載されているものの、国民審査対象が誰であるかも表示されていない(10月25日現在)。それぞれの裁判官が、どういう事件でどのような判断をしたのか、国民に丁寧に説明しようという姿勢はみじんも感じられない。投票日前に、選挙公報と同じ判型の国民審査公報が各戸に届くが、これもよほど司法に詳しい人でなければ、なかなか理解しがたい代物だ。
そのため国民の多くは、審査対象の裁判官についても、国民審査の意義についても、よくわからないまま審査に臨まなければならない、という事態が続いている。
女性にのみ存在する再婚禁止期間、婚姻における夫婦同姓規定の存在は合憲か違憲か、あの裁判官の判断はいかに?
しかし近年、国民審査は国民にとって重要性を増している。それは、人々の価値観やライフスタイルが多様化するなか、その生活や人生に直接影響する法律や制度について、個々の最高裁裁判官の価値観が判断に反映されるケースが相次いでいるからだ。
たとえば、女性だけに6カ月の再婚禁止期間を設けた民法規定の是非が争われた事件。この規定は、再婚後に生まれた子どもの父親を特定するために、明治時代に作られたものだ。医療や科学技術の発達で、子どもの父親の特定はこのような規定がなくとも、今では可能となった。離婚や再婚の件数も増えるなど、社会の変化を背景に、見直しを求める声が高まっていた。一方で、こうした規定を変えることに慎重な保守的な人たちもいる。
2015年12月16日に出された最高裁大法廷判決は、民法が規定する再婚禁止期間のうち、100日間を除いた部分は違憲、とした。つまり、女性だけに6カ月もの再婚禁止を強いるのは違憲だが、100日間の再婚禁止は残してよいという、まるで対立する両者の間を取り持ったような判断だ。ただ、2人の裁判官が再婚禁止期間を設ける規定そのものが違憲とする「意見」を明らかにした。
時代とともに人々の意識や価値観は変化するが、最高裁の対応は概して保守的で、現状変更には慎重だ。それでも、憲法に依拠しながら、少しずつ、ゆっくりと、社会の変化に対応してきたとはいえる。そうでなければ、司法は社会の現実や人々の価値観と大きく乖離したものになるからだ。再婚禁止期間についての最高裁の一見煮え切らない判断は、裁判官たちの価値観を巡る葛藤を象徴しているといえるのではないか。
この判決と同じ日に、最高裁大法廷は夫婦別姓を求めた別の裁判の判決も出している。10人の裁判官が民法の「夫婦同姓」規定を合憲とし、原告の請求を退けたが、5人の裁判官はこの規定を違憲とする「意見」を書いた。
民法には明治以来、「夫婦同姓」とする規定があるが、これを廃し、「夫婦別姓」を選択できるようにすべき、との声が巷では高まっている。一方、世の中にはあくまで「同姓」を厳守しようようとする人々もいる。この両者の根本的な違いは、夫婦とは、家族とはどうあるべきかという価値観といえよう。この価値についての判断が、裁判を通じて司法に求められているのだ。
最高裁大法廷は、今年6月にも「夫婦別姓」を巡る事件の決定を出した。そこでは、裁判官11人が「同姓」規定を「合憲」とした(4人が「違憲」)。今回の国民審査の対象になっている11裁判官のうち、7人がこの決定にかかわっている。深山卓也、林道晴、岡村和美、長嶺安政の4氏が「合憲」、三浦守、草野耕一、宇賀克也の3氏が「違憲」とした。
こうした判断を導き出す個々の裁判官の価値観を、国民1人ひとりが自分の価値観に照らし合わせてチェックする機会が国民審査といえる。
全国5つの裁判所で、同性カップルが「婚姻の自由」を求めて争っている裁判も、いずれ最高裁に上がってくる。本来、こうした夫婦や家族のあり方を巡る問題は、立法機関である国会で議論されるのがふさわしい。今回の総選挙でも争点には挙げられている。ただ、議会での多数派が消極的で動きが見られない時に、当事者が頼るのは司法。最高裁が違憲と判断すれば、行政や立法も制度の改正に取り組まざるを得ないからだ。そのため、このような法への適合性より価値観に基づく判断が裁判官に求められることになる。
どのような価値観の人に最高裁裁判官の仕事をしてほしいか。それを示す唯一の機会が国民審査だ。
「大崎事件」の再審不開始、「一票の格差」合憲判断、判断したのはどの裁判官?
国民審査が国民にとって、より重要になってきたもうひとつの背景にあるのは、2009年から実施されている刑事裁判における裁判員制度の存在だ。裁判員裁判が行われるのは、地方裁判所での一審だが、その判断を職業裁判官のみの控訴審(高等裁判所)が覆すことがある。この時に、最終的な判断を下すのが最高裁だ。
最高裁はこれまでに、「明らかに不合理でなければ一審判決を尊重すべきだ」として、裁判員裁判の判断を重んじる姿勢を示す一方で、裁判員裁判が求刑の1.5倍の懲役刑を課した事件では、「他の裁判結果との公平性は保持されなければならない」と判示した。市民の判断が職業裁判官によって次々に覆されたり変更されたりするのでは、裁判員制度の存在意義が薄らぐ。一方で、司法には公平性が求められる。そのバランスをとるために、最高裁は重要な役割を果たしている。
裁判員として司法に関わる市民にとって、最高裁の裁判官は決して遠い、無関係の存在ではなくなった。
刑事事件とのかかわりでは、国民審査は最高裁裁判官の人権感覚を国民がチェックする機会でもある。それは、1度確定した裁判のやり直しを求める再審手続きに顕著に表れる。過去の裁判所の判断を覆してでも、有罪とされた人の人権を守るかどうかが問われるからだ。
最高裁は1975年、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則が再審の判断にも適用されるとした「白鳥決定」によって、再審開始への道を開いた。しかし、現実にはその方針が守られているとはいいがたい判断がなされることもある。
2019年6月25日、最高裁第1小法廷は、1979年に鹿児島県大崎町で義理の弟を殺害したとして有罪判決を受けた原口アヤ子さん(2019年当時92歳)が起こしていた再審請求(大崎事件)に対し、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部が出した再審開始決定を取り消し、再審を認めない決定を出した。高裁は、弁護側が提出した遺体に関する新鑑定を新証拠として認め、殺人事件ではなく事故だった可能性を否定できないと判断していた。一方最高裁は、この新鑑定の証明力を否定し、共犯者の自白を重視した。
弁護団にすれば、これは思ってもいなかった「不意打ち」だった。高裁への差し戻し決定であれば、反論することもできたが、最終審の最高裁が自ら再審不開始を決めたために、その機会もなかった。白鳥決定以降、地裁、高裁の再審開始決定を覆し、最高裁が自ら再審不開始を決めるのは初めてのケースだ。
この判断をした第1小法廷の裁判官のうち、深山卓也裁判官が今回の国民審査の対象になっている。
昨年12月22日に最高裁第3小法廷が出した「袴田事件」の決定にも、各裁判官の人権感覚が反映されている。55年前の一家4人殺害で死刑判決が確定した袴田巌さんが再審を求めている事件だ。静岡地裁が再審開始を決定したが、東京高裁がこれを覆した。弁護側が提出した2つの科学鑑定を巡り、最高裁は1つは退け、もう1つは高裁での審理が尽くされていないとして、東京高裁に差し戻した。
ただし、これは5人の裁判官のうち3人の多数意見によるものだ。2人の裁判官は、「(高裁に差し戻さずただちに)再審を開始すべきだ」とする「反対意見」だった。
今回の国民審査では、林道晴裁判官が多数意見であり、宇賀克也裁判官はただちに再審を開始すべきとした。
このほか、国政選挙での「一票の格差」や沖縄・辺野古への米軍基地建設を巡っての国と沖縄県の争いなど、さまざまな重要課題で、最高裁が判断を行っている。
このところ、メディアも国民審査の大切さに気付いてきたようで、インターネット上などで情報発信をしている。たとえばNHKは実にわかりやすい特設サイトを作っていて、お勧めだ。また、朝日新聞は対象裁判官に詳しいアンケートを行い電子版に掲載している。
こうした資料を手がかりに、最高裁裁判官の価値観や人権意識を審査する機会を生かしたい。最後に、せっかくの審査結果を無駄にしないためにも、投票用紙には「×」以外は書かないよう、くれぐれも注意してほしい。
(文=江川紹子/ジャーナリスト)