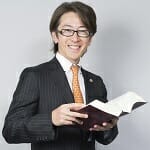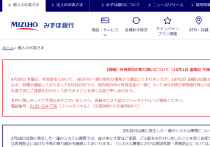野村、システム開発頓挫→IBMを提訴し敗訴…大手発注元、ベンダ“奴隷扱い”の実態
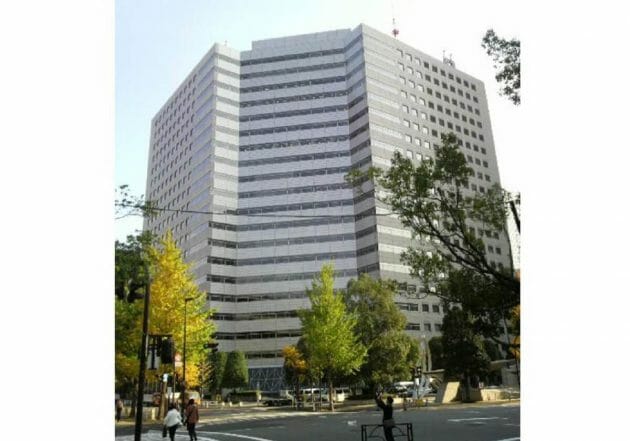
野村ホールディングス(HD)と証券子会社・野村證券が、自社のシステム開発案件が頓挫したことで損害を被ったとして、委託先の日本IBMを相手取り約36億円の賠償を求めていた訴訟。一審(東京地裁)ではIBMに約16億円の賠償が命じられたが、今年4月の控訴審判決(東京高裁)は一審判決を変更し、野村側の請求を棄却。そして12月13日付「日経クロステック」記事は、野村が最高裁への上告を取り下げ敗訴したと報じ、システム開発業界でにわかに注目されている。
野村は2010年、社内業務にパッケージソフトを導入するシステム開発業務をIBMに委託したが、作業が大幅に遅延したことから野村は開発を中止すると判断し、13年にIBMに契約解除を伝達。そして同年には野村がIBMを相手取り損害賠償を求めて提訴した一方、IBMも野村に未払い分の報酬が存在するとして約5億6000万円を請求する訴訟を起こし、控訴審判決で野村に約1億1000万円の支払いが命じられていた。
控訴審判決では、開発遅延の原因について、野村がIBMに何度も仕様変更などを要求し、またIBMからの工程数の削減提案に応じなかったことにあると認定したが、システムの委託元と委託先、しかもお互いに大企業同士が提訴し合うという異例の事態となり、その成り行きが業界内で注目を集めていた。
「大手金融機関の大規模システム開発案件ともなれば、ベンダ(システム開発会社)への発注額は数十億円単位になるので、たとえベンダが大企業であっても、重要顧客である発注元との間では明確な上下関係ができ、単なる“業者扱い”“下請け扱い”を受けることも珍しくない。そのため、要件定義や設計で一度フィックスしたにもかかわらず、発注元から何度も仕様変更を要求されれば、ベンダ側はコスト持ち出しでそれに応じざるを得ない。発注元からの追加仕様や修正依頼を受けて開発工数が増大しても、契約金額の増額を認めてもらえず、結果としてベンダ側が赤字を抱えてしまうというのはザラ。はっきり言って“ベンダは発注元の奴隷”というのは業界の共通認識。
特に銀行や証券、保険などの大手金融機関は金銭感覚がシビアで値下げ要求などのコスト圧縮圧力が強く、“ウチの実績をアピールして他社での受注につながるでしょ? だから特別価格にしてよ”などと当然のような顔で言ってくる。さらに将来の継続的な発注をチラつかせて“今回は安くして”と言われ、ベンダの営業担当者やSEも目先の受注が欲しいから、要求を飲んでしまうんです。
しかし、何十億もの受注で浮かれたのもつかの間、終わってみればプロジェクトは億単位の赤字となり、社内で犯罪者のような扱いを受けるという例は、業界ではよくある話ですよ」(大手ベンダ社員)
野村とIBMの企業体質
今回、野村とIBMが真っ向から対立するに至った背景について、別の大手ITベンダ社員は言う。
「野村は金融機関のなかでも特に発注先への要求が厳しいことで知られ、たとえば現場レベルでもベンダ側のSEなんかを名指しして“誰々を担当から外して”などと平気で言ってくる。一方のIBMは外資系ということもあり、発注元相手でも“できない”と言い切ったり、追加費用がもらえなければ工数増やコスト増につながる要求を拒否したり、契約範囲外の要求なんかもはねのけたりと“ドライ”な面があり、そこが国産ベンダとは大きく違う。そんな両者の体質ゆえに、お互いに譲らなかったことから訴訟合戦という展開になったのではないか」
今回の判決は、こうした大手発注元とベンダの関係を変化させるのだろうか。
「もう10年以上も前からベンダ各社のなかでも“売上より採算・利益重視”なんて言われてますが、売上が立たなきゃキャッシュも入ってこないし、いろんな人的リソースも手放さなきゃならなくなるし、営業もノルマを達成できないわけで、特に何十億単位の発注をくれる大企業顧客にはひれ伏してしまう。今回は訴訟でIBMが勝ったからといっても、発注元とベンダの関係は何も変わらないんじゃないですかね」(同)
本事案を大企業間の法的紛争という観点からどうみるか。企業法務にも詳しい山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士に解説してもらった。
山岸弁護士の解説
この裁判、一審判決時からとても気になっていました。実は、システム開発やソフトウェア開発を業とするクライアントを持つ弁護士にとっては、開発系の裁判は長年、苦労してきています。
なぜなら、このような開発は、契約「時」には“だいたいこんな感じのものを作ろう”という合意しかなく、契約「後」に、要件定義といった“何をつくるか”を少しずつ明らかにしていく作業が行われるという性質があるからです。
これに対し、裁判の世界は、あくまでも契約「時」に遡り、当事者は契約「時」において、はたして“何を作る合意があったのか”“当事者は何をしたかったのか”を確定する作業であり、なかなか開発の現場の実態と合致しないところがあるからです。
こういった紛争が長く続いてきたため、現在は国家政策として経済産業省や(独)情報処理推進機構あたりが「ひな形契約」を作るなどして、なるべく法的紛争にならないような工夫がされたりしています。
しかし、上記のとおり、どんなに契約書をしっかり作っても、法務部や顧問弁護士がしっかりしている大手の会社同士の契約であっても今回のような法的紛争が避けられないのが、システム・ソフトウェア開発業界の特徴です。
そして、たいていの場合、カネを出す発注者は、なるべく自分の要望を強く押し出してきますし、ときに最初に希望していたモノと違うモノを欲したりもするので、仕事をもらうという弱い立場の開発側は、苦労することになるわけです(ここまで、システム・ソフトウェア開発業界については素人で、しかし、この業界の紛争については多数関わってきた一弁護士としての意見です。だから「業界がわかってないな、こいつ」とは思わないでね)。
ところで、今般の東京高裁判決を読み、まず驚いたのが、判決は「野村HDとIBMとの間では、本件システムを完成し稼働させることはビジネス上の目標であったとしても、契約上のIBMの義務とはされていなかった」と明言したところです。判決は「ビジネス上の目標とする合意があったとしても、それが契約上の義務として合意されたとは限らない」として、「IBMは本件システムの完成・稼働に至るまでの個別の契約に基づく業務はほとんど行っており、最終的な本件システム自体が完成・稼働しなくても、野村HDは未払いの個別の契約に基づく報酬を支払わなくてはならない」と判示しました。
おそらく裁判所は、キングファイル一冊分くらいの契約書の束を読み込み、担当者間の膨大なメールのやりとりを読み込み、会議の議事録を読み込み、「野村HDとIBMは、契約時には何をしようとしていたのか」を判断したと考えられます(民事の裁判官は、情や涙には流されません。膨大な量の資料を行間まで読み込むのが仕事です)。
そして、一審に敗訴したIBMは、「契約時の当事者の意図」を酌んでもらうべく上記の膨大な資料を裁判所に提出し、アピールしたのでしょう。IBM側の訴訟代理人弁護士の労力と能力に頭が下がります。
次に、判決では、報道であったように、野村HDの投資顧問部の担当者の言動について触れていますが、まぁこれは上記のとおり、システム・ソフトウェア開発に“あるある”なので、これだけをもって野村HDを逆転敗訴させたとは言えないでしょう。
今回の判決は、前述のとおり、当事者間は契約「時」に“何を作る合意があったのか”“当事者は何をしたかったのか”を確定する作業こそ裁判であるという本質に戻った、かくあるべきものだったと考えます。
報道は、高裁判決を受けた野村HD、IBMそれぞれのコメントを発表しています。どちらも「将来にむけて良好な関係になる」とのことです。やはり、大企業同士の大局を見据えた考えはとても良いですね。ぐっときました。
(文=編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表)