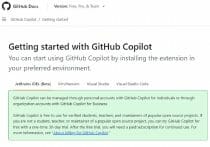生成AI普及で意外な影響…世界で原発の新設が活発化、TSMC一社依存

生成AIの急速な普及に伴い、世界で原子力発電所の建設が活発化している。これは、データセンター需要の拡大に伴い大量の電力が必要となるためだ。たとえば米OpenAIなどとのAI共同開発事業「Stargate Project(スターゲート・プロジェクト)を推進するソフトバンクグループ(SBG)は1月、AIインフラストラクチャを米国内で構築するため今後4年間でスターゲートが5000億ドルを投資すると表明し、米国内でデータセンターと発電所を設置していく計画を明らかにしている。また、中国は2024年末時点で運転中の原子炉が58基であり、建設中・建設認可済みの原子炉を合計すると計102基になる(中国国家核安全局の1月の発表より)。なぜ再生可能エネルギーや他の発電形態ではなく原発なのか。また、これ以外でも生成AIの普及によって影響がおよんでいる意外な領域というのは、あるのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。
「生成AIの開発には大量の電力が必要なので、これから新設することができ、かつ十分な量の電力を安く供給できるとなると、やはり原発ということになります。発電コストの面は重要であり、また原発1機あたりの発電量が他の発電形態に比べて遙かに大きいです」
こう解説するのは立命館大学情報理工学部教授の上原哲太郎氏だ。原発以外でも、生成AI普及によって意外にも影響が生じている分野というのは少なくないという。
「AIに必要な計算を高速で行う半導体であるGPUは今、世界的に争奪戦になって価格が高騰していますが、その影響でゲーミングPCの価格が上がっています。GPUはもともとゲーム画面の計算に使うもので、計算速度の割には安いのでAIに流用されてきたのですが、そのおかげで価格が上がってゲーム愛好家が困るという意外な影響が出ています。また、半導体まわりでいうと、GPUに使えるような高速な半導体を設計する企業としては米エヌビディアが最大シェアで、その次が米AMDですが、この2社とも自社では半導体を製造していません。両社の設計を受け取って実際に製造してるのは台湾のTSMC(台湾積体電路製造)です。
世界のGPUの製造が事実上、TSMC一社に依存している状況となっていますが、世界情勢的に台湾は中国との緊張関係が高まっているので、もし仮に台湾で何かが生じると世界中の半導体市場がパニックに陥りかねないという、大きなリスクを抱えています。仮に有事になってGPUの生産が滞ると、世界中の生成AIの開発がストップするなど、大きな支障が出る懸念があります。TSMCは台湾以外にも、日本だと熊本に工場を構えていますが、そこで手掛けるのは最先端半導体ではなく、信頼性を重視した旧世代のものばかりです。この他に最近米国アリゾナ州に最先端の半導体工場を建設しましたが、まだ稼働を始めたばかりで十分な量を供給できるわけでもありません。このようにTSMCはまだ海外で半導体をつくる能力を十分に確保していないので、台湾で何か起きると困ったことになるという可能性はあります。
そもそも、世界でTSMC一社しかつくれない超最先端の半導体というのがあり、パソコンやサーバ、スマートフォンのCPU(中央処理装置)のうち最高速のものはTSMCの技術に頼っています。AMDやインテルが設計する最先端のCPUは、今は主にTSMCが製造しています。インテルはこれまで自社で半導体を製造していましたが、最先端の半導体製造の製造能力がTSMCに遅れを取るようになってきて、ついに最近TSMCに自社で設計したCPUの生産を一部委託するようになりました。なので、AIに関わる半導体の製造は本当にTSMC一社体制、一強体制なのです。世界中のAI用半導体の製造を担ってしまっているので、TSMCに何かあると世界の半導体供給がストップしてしまうかもしれないという状況はリスクが大きいです」(上原氏)
AIを取るか、古いプログラムを取るか
他にも影響がおよぶ領域があるという。
「少し違う視点でいうと、AIのビジネスへの活用ということが注目される中で、クラウドサービスを使うことになるわけですが、クラウドに会社の情報を何でもかんでも送信して大丈夫なのかという点が問題視されています。ある企業の情報をクラウド上のAIが覚えてしまって、ライバル会社にうっかり教えてしまうケースが生じないのかという問題です。
それを防ぐためにCPUにAI専用の半導体NPU(ニューラルプロセッシングユニット)を付加して、クラウドに頼らず手元のパソコンでAIを動かすというかたちが推進されており、たとえばマイクロソフトはそれができるWindowsパソコンをCopilot+PCというブランドで提供しています。会社の機密情報を守るためにこうしたパソコンが必要だという話になると、パソコンの買われ方が変わってきます。今年はWindows10のサポート切れを控えているため一定のパソコン買い替え需要があるなかで、『NPU搭載のパソコンを買ったほうがいいよね』『Copilot+PCにしたほうがいいよね』というリプレイスの仕方をする会社が増えるかもしれません。
そのときに何が起こるのか。今までWindowsのPCで主流だったのはインテルやAMDのCPUですが、Copilot+PCではインテルのCPUとは互換性がない、英Armが設計したCPUのほうが優勢なんです。だからといってArmのCPUでもマイクロソフトのOffice等は対応済みなので問題なく動きますが、インテルのCPUで動いてた多くのプログラムは変換して動かさねばならないので、古いプログラムなどがうまく変換できず動かないという問題が広がるかもしれません。AIを取るか、古いプログラムを取るかみたいな問題になって、いろいろとドタバタした動きが今年後半以降に起きるかもしれません」
(文=Business Journal編集部、協力=上原哲太郎/立命館大学情報理工学部教授)