近大附属中高はネットで学習継続、花まるはZoom自学室…問われる学校の存在意義
新型コロナウイルス肺炎の拡大予防措置として、全国の小中高等学校などで一斉休校措置が取られて1カ月。ネット上ではさまざまな学習コンテンツが無料で公開され、ネット環境さえあれば自宅にいながら学べるということが証明された今、未来の教育の姿を模索する動きが始まっている。学校や塾など教育現場ではどんなことが起きていたのか。近畿大学附属高等学校・中学校と花まるグループのスクールFCの取り組みを取材した。そのなかで見えてきたこととは――。
ICT教育に力をいれてきた学校では、休校措置にもスムーズに対応できた
一斉休校措置が発表された翌週3月2日から、休校に踏み切った近大附属中高。その際、生徒に対して行ったのは、「通常通り、学校からの連絡システムに必ず目を通すこと」という1本のメールを送信するだけだった。休校中の学習は、双方向の連絡システムを活用して、e-ラーニング教材の視聴範囲やYoutubeのURLが提示され、オンライン上でレポートを提出したり、確認テストを行ったり、各教員が必要に応じて対応をしているという。
しかし、こういう事態に一番担保しなくてはいけないのは、生徒の精神的安定と心理的サポートだ。そこで、オンライン会議システムを使用してホームルームを行ったり、なかには、生徒たちの希望により、リアルタイムのオンライン授業を行った教員もいる。このように、休校中でもクラウド上で学校運営が続けられているのだ。
このようなスムーズな運営ができているのは、教員も生徒もICTの活用に慣れていたから。同校は、2013年から全校で一人一台のipadを導入して以来、すべての生徒、教職員が24時間365日双方向にやりとりできる通信システムを活用した学校運営を実施してきたICT教育のトップランナーだ。
そこで、同校の教育改革推進室長 乾 武司教諭にICT教育の可能性について話を聞いた。

ICTの活用で、学校の存在そのものの意義が問い直される
日常的に、オンラインでの双方向のやり取りに教員も生徒も慣れていたので、本校では急な休校装置にも、慌てずに対応ができました。今回明らかになったのは、ICTを使った学校運営をスムーズに行うためには、
(1)双方向のオンライン通信システムが確保されていること。
(2)24時間使える一人一台のデジタル端末があること。
(3)常日頃から教員生徒双方のICT活用スキルが磨かれていること。
この3つが欠かせないということです。いきなり学習ツールだけあてがわれても、十分な学習活動は行えないのではないでしょうか。今後もこういうことが起こりうる可能性はあるし、子どもたちの学ぶ場所を確保するためにも、学校は教育に対する認識を新たにしていく必要があると思います。
なぜなら、ICTの活用は学校の存在そのものの意義が問い直されることになるからです。この休校措置で、生徒たちは学校に来なくても勉強できるということに気づき始めていると思いますし、我々も生徒たちはいろいろなリスクを負って学校に通ってきているということに改めて気づきました。情報を伝達するだけなら、学校に来る必要はないのですから、学校での教育活動は、あえて学校に集まるだけの意味のあるものにしなくてはと感じています。
実際本校ではICTの導入を進めた結果、生徒主体の学び合いが活発に行われるようになっています。実は、導入当時は、学習目的で使用していたわけではなかったのですが、自由に使える端末があると生徒たちが勝手に自分で情報収集をして学びだしました。その様子をみていて、先生はなんのために存在するかを、否が応でも考えさせられたのです。
私は、学びの主体が生徒である以上、しんどい思いをするのは生徒であるべきだと考えるようになりました。そこで、単元を細分化し、担当セクションについて、生徒が事前に調べて資料をまとめて授業を行うというスタイルに変えました。教師は教えるのが好きなのでつい教えたくなりますが、生徒に委ねてみたら前よりずっと主体的に勉強するようなったのです。
~以上、乾先生のコメント~
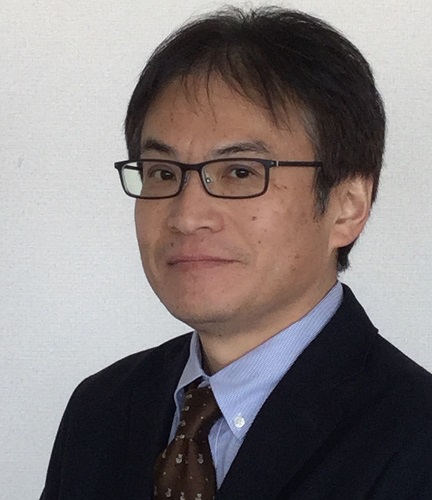
教育×ICTで、子どもたちの多様な才能が開花する可能性
ICT化によって、もたらされたもう一つの気づきは、生徒の隠れた才能が見えてきたこと。インプットだけでなくアウトプットが多様化することで、今まで引き出さなかった力を引き出せるようになったという。
「これまでの教育では、覚えて書く力に秀でている子どもだけが評価されてきましたが、今は動画で発表するなど表現も多様化していて、そこでは、総合芸術の力が求められます。また、教室では、今までは黙って授業を聞くことが要求されてきましたが、双方向の授業になれば、発信が得意な子が活躍するようになります」(乾先生)
学校でのICTの活用によって、児童・生徒の主体性や多様性が引き出されるという話は、前回の記事で渋谷区立西原小学校の手代木校長も指摘した視点だ。
Zoomを活用したオンライン自習室という取り組み
では、塾業界では、どのような動きが起きているのだろうか。学校と同様に大手を中心に休校措置を取るところが多かったが、なかにはオンライン会議システムを活用して対応したところもある。花まるグループの中学受験塾、スクールFC代表・松島伸浩さんに話を聞いた。
「政府の発表を受けて、3月2日から我々も2週間の休講を決めました。しかし、子どもたちが、家でストレスを抱えたり生活が乱れたりすることが予想できる中、課題を出すだけでいいのか、何かできることはないのかと考えて、急遽オンライン自学室を開講することにしました。」(松島さん)
活用したのはZoom。新型コロナウイルスで一挙に需要が高まっているといわれている会議システムだ。どのようにやっているのか、筆者もオンライン上で参加してみた。
指定されたURLから会議室に入ると、自宅のさまざまな場所で勉強をしている10名ほどの子どもたちとその様子を見守る講師の様子が画面に映し出されていた。全員マイクをミュートにしているので音はしないが、様子を見ていると皆思い思いの場所で静かに勉強をしているようだ。2名の講師がその様子を見守り、必要に応じて声をかけたり、生徒からの質問に対応する。質問があるときには、子どもはマイクをオンにしてホスト役の講師に声をかる。すると、ホスト役の講師が、Zoomのブレイクアウトセッション機能を使って、担当の先生と子どもを個別のセッションルームに移動させ、そこで1対1の個別指導が行われるという仕組みだ。
自分ひとりだと続かない勉強も、友達が勉強している様子が映っていると頑張ろうという気持ちにもなるのだろう。自学室は毎日午前10時から19時まで開けられているが、毎日200名ほどが利用している。規則正しい生活リズムを確保できると、保護者からも好評だ。

離れていてもつながっている空間の中で、自ら勉強する習慣が身につく
「もともと、『自学できる子を育てる』ということを指導理念の一つに掲げていて、普段から1年中自学室を開放しています。また、授業の合間にも自分で勉強する自学タイムを設けています。必要に応じて質問等に答えながら、自ら勉強する習慣を身に着けさせたいという思いから、やっていることですが、こういう学びを止めたくないと思いから、オンライン自学室という発想が生まれました」(松島さん)
4日間で生徒・保護者・社員向けのマニュアルをつくり、3月4日から始まった自学室。運営側も不慣れでバタバタしている中、10時の開講と同時に会議室に入り始めた子どもたちは、特別な指示も出さないうちに勝手に自習を始めたという。その様子を見ていて、「自ら進んで勉強する子を育てたいという我々の理念が子どもたちに届いていると感じて、嬉しかった」と松島さん。もともと自分で計画を立てて勉強するという習慣が身についていたからこそ、オンライン自学室という試みも、うまく機能したのだろうが、離れていてもつながっている感覚を持てるオンライン自習室というこの試みは、教育の新しい可能性を開く扉になるのかもしれない。

ICT化は、100年前から変わらない学校の姿を変える
2つの事例から、見えてきたことは、学びの主体者は子どもたちであり、大人が信じて任せれば、子どもたちは持っている力を発揮し始めるということ。そして、それを後押しするのが、ICTのさまざまな機能だということだ。
前述の乾先生は言う。
「日本の教育現場へのICT機器の導入を遅らせてきたのは、『学校の中でしか学べない』という思い込みが強かったことと、教える側と教わる側のヒエラルキーを崩さないという圧力が強かったからです。教育の世界では、先生以外からは教わる手段がなかった明治時代から変わらない情報伝達システムが今も行われています。しかし、今は誰からでも学べる時代です。日常的に教育現場でICTが活用されるようになると、いっきに教育改革が進むのでは」
今回の取材を通して、教育×ICTがもたらす可能性に改めて気づかされるのと同時に、これが今後学校のあり方や学び方を根底から変える起爆剤になるのかもしれないと感じた。
思ってもみない事態が起こったときに、自分で考えて行動できるかどうかは、日頃から主体的に取り組む経験があるかどうかにかかっているが、管理だけをしていたら、決して主体性は育まれない。国が打ち出した、一人一台の端末を持たせるという「GIGAスクール構想」が、日本の教育を変える起爆剤になりうるかどうかは、大人たちの「子どもは管理しないと何もできない」というブロックを外せるかどうかにかかっているのかもしれない。
(文=中曽根陽子/教育ジャーナリスト、マザークエスト代表)











