NTTはドコモを菅政権に差し出した…「料金引き下げ」「NTT法規制緩和」のバーター取引
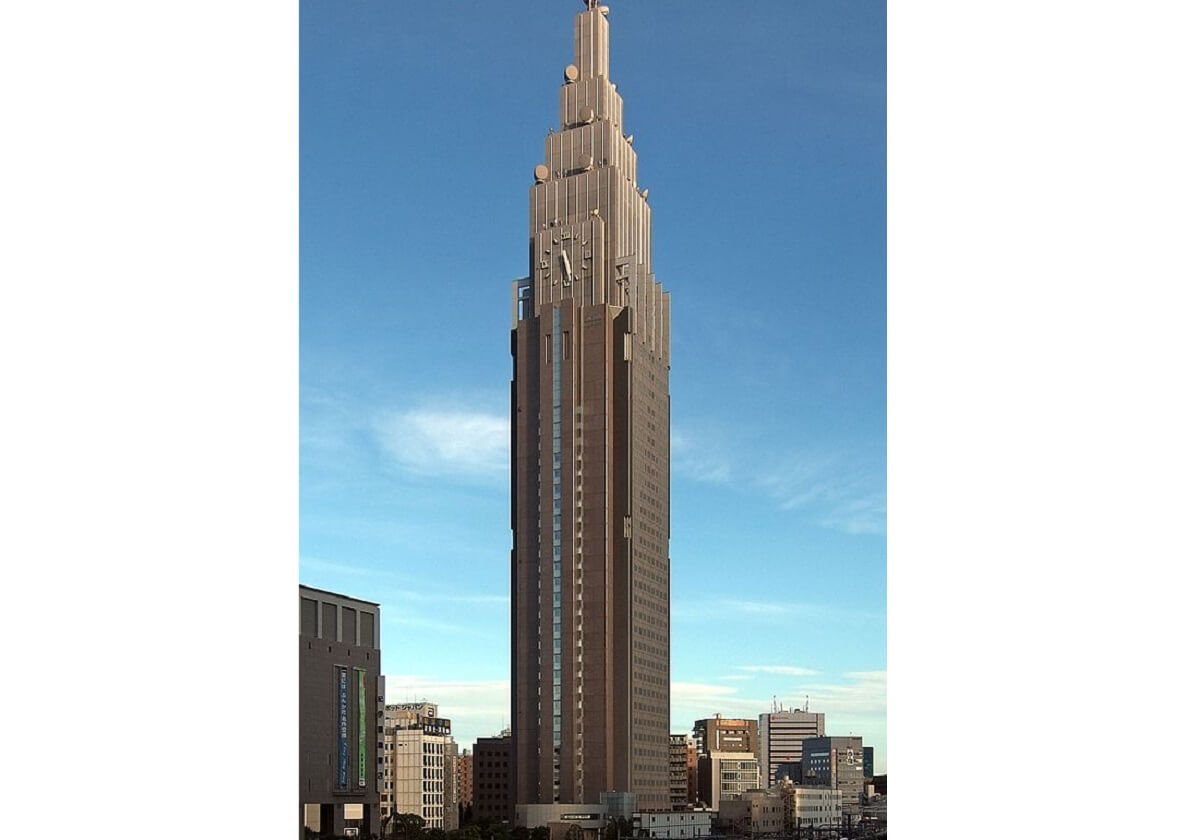
「NTTは規制緩和と引き替えにドコモを菅義偉首相に差し出した」――。
ある携帯電話大手関係者は、9月30日にNTTが発表したNTTドコモの完全子会社について、こう驚きを隠さなかった。
まずはNTTの発表の中身を確認していこう。同社はドコモ株を約7割所有しているが、一般株主が保有する残り約3割を約4兆円かけて買い取り、完全子会社化する。9月30日に記者会見したNTTの澤田純社長は、ドコモが契約数こそ国内トップだが収益性ではKDDIとソフトバンクに劣る第3位になっていると強調し、経営の意志決定の迅速化が今回の決断の目的だとした。ドコモはNTTグループ全体の約半分の利益を稼ぎ出す収益源であり、一般株主が持つ3割分の株の配当を取り込むことで収益性を一層高めるという。
これについて検証していく。ドコモの収益性の低さについてだが、2020年3月期のドコモの連結営業利益が8546億円なのに対し、KDDIは1兆252億円、ソフトバンクは9117億円となっており、売上高に占める営業利益の比率はそれぞれ18.3%、19.5%、18.7%で確かにドコモが第3位となっている。ドコモは「アプリなどを買わない地方の高齢者の契約者の比率が高く、一人当たりの収益性を押し下げていた」(業界アナリスト)ことが他の大手2社に後れをとる大きな原因となっていた。
さらに、株式公開による配当の取りこぼしだが、20年3月期の配当総額は3909億円で、この3割の1300億円程度が一般株主に「流出」していたことになるため、完全子会社化で確かにこの金額は取りこぼさなくてよくなることは、短期的にみれば間違いではない。
澤田社長の「強いNTT」への憧れが主因
一般論として子会社の業績が悪い場合、主要株主は経営陣を交代させるのが普通だ。完全子会社化して親会社と一体化するという例は、特にNTTとドコモのような巨大企業の場合はごくごくまれだろう。一般株主から株を買い戻すのにコストがかかる上、効果が上がるかわからないからだ。まして4兆円もの巨額資金をメガバンクから調達してまで、となればなおさらである。業界関係者の多くが「4兆円もあるなら、ソフトバンクグループのようにイケてるベンチャーでも買収したほうがいい」(証券アナリスト)と考えるのも無理はない。
取りこぼし分とされた1300億円が収益としてプラスとなっても、4兆円と利息分の支払いを考えれば30年程度かかってペイするわけだから、こちらも割に合わない。NTTは株主にどうこの巨大支出を説明するか、大いに疑問である。
投資効率を考えればまったく論外というしかない今回の完全子会社に、何がNTTを踏み切らせたのか。その原因の大きな一つに、NTTの澤田社長による「強いNTT」の復活願望があることは間違いない。
澤田氏は旧電電公社時代の1978年に入社し、かつて通信業界として「電電公社一強の時代」を知っている。澤田氏は9月30日の会見でも、NTTの足を引っ張ったのは1985年の民営化にともなうNTT法などによる規制であり、KDDIやソフトバンクの後塵を拝するきっかけになったと語っている。18年6月の社長就任時からクラウドやシステム開発などでグループ各社の力を結集する必要性を訴えており、今年3月のトヨタ自動車とのスマートシティの連携でも「GAFAに対抗する」と明言。日本の技術を集めて海外と競っていくことを重視しているという点ではナショナリストといっていいだろう。
菅政権とのバーター取引
澤田氏の悲願である規制緩和には、政府への働き掛けが欠かせない。菅義偉政権は携帯料金引き下げを至上命題としており、携帯大手3社への政治的圧力を強めていた。そこに今回のドコモ完全子会社化である。もちろん、これだけ大きな決断には時間と手間がかかるため、菅首相からの圧力が直接的な要因ではないだろうが、澤田社長からすれば「料金を引き下げるから規制を緩和してくれ」と要求するには十分すぎる材料だ。
ドコモが完全子会社化されれば、より高い配当を求める一般株主に配慮しなくてもよいため、菅首相が従来から主張している「4割程度の値下げ幅」が可能になる。具体的には、月4000~5000円程度の料金プランだ。ドコモがこのプランを打ち出したとすると、KDDIとソフトバンクも追随せざるを得ないため、菅政権の目玉政策は実現されることになる。
ただ、月額1000~2000円程度の格安スマホ業者もすでに多数あることに加え、総務省も昨年10月の電気通信事業法改正などさまざまな施策に取り組む中、9割ものユーザーが大手3社に偏っている現状は国内市場の保守性など多くの理由があるとみるべきだろう。それを政策的に無理矢理引き下げることは、市場における競争を重んじる資本主義社会の原理を侵すことにならないか懸念が残る。
独立性を失ったドコモの現場がサービスを良くしようという現場のモチベーションを失うのも避けられないだろう。さらに、当のNTTにしても、稼ぎ頭であるドコモの携帯料金の売上が一人当たり3分の1程度も下がれば、打撃となるのは間違いない。どの程度の規制緩和を望むのかは不透明だが、「4兆円払った高い買い物にしては見返りが少ない」(証券アナリスト)との指摘が出るのも納得だ。
GAFAがのし上がったのは、有望な他社を次々と飲み込んでいく多様性を持っていたからだ。NTTの今回の完全子会社化はそうした多様性とは真逆で、時代に逆行しているように思われる。
キャッシュレス決済サービスのドコモ口座での不正利用問題にしても、自社回線ユーザーにこだわったドコモが他社連携に後れを取り、あせってセキュリティーを緩めて顧客獲得に走った結果起きた。こうした自前主義、純血主義が日本企業が国際競争に敗れる大きな要因となったことを、澤田社長にはもう一度思い起こしてもらいたいものだ。
(文=松岡久蔵/ジャーナリスト)











