石油の時代は終焉するのか?米国シェールオイル生産が停滞、原油価格が不安定化の懸念
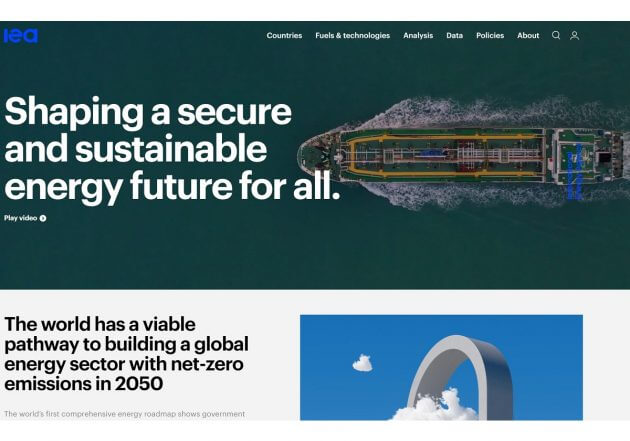
国際エネルギー機関(IEA)は5月18日、2050年までに世界の温暖化ガス排出量を実質ゼロにするための工程表を公表した。その主な内容は(1)化石燃料関連の新規投資の決定を今年中に停止する、(2)35年までにガソリン車の新車販売を停止する、(3)40年までに石炭・石油発電所を廃止する、(4)50年までにエネルギー供給に占める再生可能エネルギーの割合を約7割に引き上げる、などである。
極めて野心的な内容だが、IEAのビロル事務局長は「(実質排出ゼロ)は難しいが、達成可能だ」との声明を発表、各国政府が強力な対策を採るよう求めた。50年までに温暖化ガス排出量を実質ゼロにすることは、地球温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」が定める「産業革命からの気温上昇を1.5度以内に抑える」という目標と合致する。今年11月に英国で開かれる第26回国連気候変動枠組み条約締結国会議(COP26)を前に、IEAとしては具体的な道筋を示すことで「温暖化対策に後ろ向き」との批判をかわす狙いがあったのだろう。
IEAの工程表は世界に衝撃を与えたものの、IEAの根回し不足のせいか、産油国や民間石油会社からの反応は皆無といっても過言ではない。政府レベルで化石燃料の新規開発を抑制するような具体的な政策を導入している国はほとんどない。英蘭系石油大手ロイヤル・ダッチ・シェルの株主はIEAが工程表を公表した18日、年次株主総会で同社の「気候変動対策計画」を承認したが、25年まで新規の化石燃料開発を継続する内容となっている。
筆者は4月20日付コラムで「原油などの化石燃料は今後『座礁資産』となる可能性が高い」と指摘した。座礁資産とは、社会の環境が激変することにより、価値が大きく毀損する資産のことを指すが、温暖化ガス排出量の大幅削減を余儀なくされている環境下で化石燃料の資産価値は大きく下がる可能性が出てきている。
IEAのレポート、原油市場に混乱をもたらすとの危惧も
IEAの今回のレポートにより、化石燃料からの投資撤退を進めてきた世界の投資家たちは「自分たちの投資戦略が正しかったことが証明された。ほかの投資家も追随すべきである」と意を強くしていることだろうが、石油関連の専門家からは「今後の世界の原油市場に混乱をもたらす」と危惧する声が上がっている。
IEAの予測によれば、世界の原油需要は日量約1億バレル(19年)から50年までに同2400万バレルに減少する。原油需要の大幅縮小に伴い、原油生産者は低コストで採掘ができる少数の会社のみが生き残ることになるが、低コストで原油生産が可能な地域は中東に集中している。OPECの世界の原油生産に占める割合は現在37%だが、2050年には過去最高の52%に達するとされている。
そもそもIEAは、1973年の第1次石油危機を契機に米国のキッシンジャー国務長官(当時)の提唱により、石油危機を再発させないことを目的として74年に設立された国際機関である。石油危機が勃発する可能性が高い中東産原油の依存度を下げるために、非OPEC諸国の増産を支援するなど世界の原油供給の拡大を後押ししてきた。化石燃料をめぐる国際情勢が大きく変わったとはいえ、そのIEAが原油の中東依存度を高める内容のレポートを出したことは皮肉以外の何ものではない。
IEAは2010年代後半に「原油開発への投資の減少から20年代初めに深刻な供給不足が生じ、原油価格は急上昇するリスクがある」と警告していたが、この問題は杞憂に終わったのだろうか。
シェールオイルの生産が停滞
筆者が懸念しているのは、このところ米国のシェールオイルの生産が停滞していることである。20年3月時点の米国の原油生産量は日量約1300万バレルを誇っていたが、その後コロナ禍で約200万バレル減少し、そのままの状態が続いている。
米ダラス連邦準備銀行の調査によれば、シェールオイルの生産コストは高い地域でも平均で1バレル=30ドル台半ばであり、新規の油田開発が採算ラインに乗る原油価格が50ドル前後の地区が多い。現在の米WTI原油先物価格は1バレル=60ドル前半であることから、シェールオイルの生産が本格的に回復してもおかしくないが、そうならないのはシェール企業が投資を抑制しているからである。
調査会社ライスタッド・エネジーによれば、米国の独立系シェール企業の8割が、今年第1四半期の設備投資額を本業で稼いだ資金(営業キャッシュフロー)の範囲内に抑えている。過去のシェールブームでの投資負担が重く、コロナ禍でさらに赤字が増加したシェール企業は、財務内容の改善のために投資を抑制せざるを得ない。世界的な「脱炭素」機運の高まりも逆風となっており、今回のIEAのレポートはシェールオイルの生産に致命的な打撃を与える可能性がある。世界の原油供給の重要な役割を担うようになったシェールオイルに危険信号が灯れば、世界の原油市場が今後不安定化するのではないだろうか。
「今回のIEAのレポートでもっとも得をするのはOPECだ」との憶測が出ているが、OPECは20日、「IEAのレポートは石油価格の変動につながる恐れがある」と批判した。原油市場におけるOPECの寡占度が高まるものの、IEAのレポートのせいで原油価格が暴落することになれば、原油収入に依存している加盟国の政情が流動化する。
「石器時代を終わらせたのは青銅器や鉄器などの新しい技術だった。石油も同じ」
このように指摘したのは、第1次石油危機を招いたアラブ敵対国への禁輸措置を主導したサウジアラビアのヤマニ石油相(当時)である。この「予言」が一気に現実化しつつある現在だが、石油の時代が静かに幕を閉じるかどうかはわからない。
(文=藤和彦/経済産業研究所コンサルティングフェロー)










