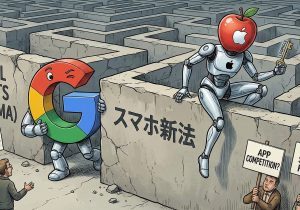これぞクラシック音楽のすごみ!動物の声を楽器で再現&壮大な物語を巧みに表現

「犬を飼いたいと思っているのだけど、今、犬の価格がものすごく高くて買えないのです」
これは最近、近所の友人家族から聞いた話です。調べてみると、コロナ禍をきっかけに犬や猫を飼う人が多くなったことが大きな原因のようです。
英国でのロックダウンのように、食品や必要最低限の日用品、そして医薬品を買うためにのみ、決められた時間に外出を許されていた国であっても、犬の散歩だけは許されていたそうです。それにより、犬の需要が急激に増えたという話は知っていましたが、日本でも自粛生活のなか自宅での時間が増えたことにより、“コロナ禍のペットブーム”が起こり、それは今でも続いているようです。
たとえば、犬の人気ランキング不動の第1位「トイ・プードル」。室内でも飼いやすい小さなサイズのぬいぐるみのような愛嬌のある犬です。新型コロナウイルス感染症の流行が始まった直後の2020年3月頃でも、人気犬ということで子犬には20~30万円の値がついていましたが、現在、一般的なペットショップのホームページを見ると、一番高いもので46万円もしています。人気第2位の「チワワ」も20万円くらいだったのが、人気あるホワイト色は42万円と、2倍以上に高騰しているのです。
しかし、このくらいの値段で驚いている場合ではありません。ある高級ペットショップでは、小さなサイズの「ティーカップ・プードル」が、なんと220万円で売れたとのことです。僕も6歳の「キャバリア」を飼っているのですが、買った当時のことを考えると値段も倍近く上がっていますし、今のように犬が品薄でもなかったので、現在の状況には驚くしかありません。
犬は、古代より人間にとって大切な動物でした。狩猟犬、牧羊犬、愛玩犬、盲導犬、警察犬、そして最近では、認知症の老人たちの治療法として注目されているセラピー犬など、たくさんの犬が人間に愛されてきました。そんなわけで、「犬」をテーマにしたクラシック音楽も数多くあります。
ショパンの『子犬のワルツ』誕生の裏側
代表的なのは、“ピアノの貴公子”フレデリック・ショパンのピアノ小品『子犬のワルツ』です。19世紀半ば頃に活躍したショパンは、社交界の大スター、ジョルジュ・サンドと同棲していました。そのサンドが飼っていた子犬が、自分の尻尾を追いかけてぐるぐる回っている姿を見ながら作曲した作品といわれています。曲の最初から、子犬が楽しそうに回っている姿を見事に表しており、犬につけられた鈴のような音も鳴り始める。そんな気楽で楽しい曲で、今もなお、大人気の作品です。
余談ですが、犬が自分の尻尾を追いかけるのは、多くの場合、ストレスを発散するためだそうです。なかにはエスカレートしてしまい、尻尾をかんで血が出ても止めない場合もあるそうで、かわいいとばかりは言っていられません。
前出のサンドは“世界最初のフェミニスト”とも呼ばれるような、特異な人物でした。当時のフランス・パリの社交界は、女性は美しく着飾り、男性貴族とのアバンチュールを楽しむ舞台でしたが、サンドはそんな社交界になんと男装して現れて驚かすような女性だったのです。
サンドには2人の子供がいたのですが、ショパンはその子供たちとの折り合いが悪かったことも一因となり、『子犬のワルツ』を作曲した翌年、サンドと9年間にわたる関係を解消してしまうことになります。もしかしたら、この曲を作曲した頃は、ショパンはサンドや子供たちとうまくいかなくなってきたストレスを感じ始めていて、自分に尻尾があったら、ぐるぐると回って追いかけたい心境だったのかもしれません。
動物の鳴き声が曲のなかで登場
犬の鳴き声を、曲にそのまま入れ込んだ作曲家もいます。それはイタリアのバロックの巨匠アントニオ・ヴィヴァルディで、『四季』のうち『春』の第2楽章です。もちろん、今のように録音機材があるわけではないので、あくまでもオーケストラを使います。ヴァイオリンが小さな音で、牧場の牧草が風に揺れる音を表現するのと同時に、ヴィオラが場違いなほど大きな音で、それこそ「ワンワン」と犬が吠える声を真似たような音符を演奏するのです。実際に、楽譜には「犬が吠える」と、ヴィヴァルディによって注釈が書き込まれているのです。
このヴィヴァルディは犬が大好きだったのか、『秋』の第3楽章でも、多くの猟犬が獲物を追い詰め興奮して吠えまくっている様子を、弦楽器に模倣させたりしています。
実は、クラシックの作曲家たちは、動物の声を楽器で模倣させることが多いのです。本連載前回記事でも取り上げたベートーヴェンの交響曲第6番『田園』の第2楽章の最後にも、3種類の野鳥が出てきます。サヨナキドリ(ナイチンゲール)、ウズラ、カッコウの鳴き声を、そのままベートーヴェンが楽譜に写し取ったように、フルート、オーボエ、クラリネットが演奏する場所があります。録音機材がなかった19世紀のことで、代わりに生き物の声を楽器で表現していたのです。
時代を超えた物語を巧みに音楽で表現
その後、1877年にエジソンが発明した蓄音機が改良されて、20世紀になるとレコードが出てきます。それに飛びついたのは、イタリアの作曲家、オットリーノ・レスピーギです。1924年に作曲した『ローマの松』では、オーケストラが演奏と同時に、あらかじめナイチンゲールの声を録音したレコードをならすように指定があります。その効果は抜群で、当時の聴衆もあっと驚いたに違いありませんし、今もなお、強いインパクトを持っています。
このレスピーギは、録音を使わずしても、楽器で動物の声を見事に再現する高い腕前を持ち合わせていたことがよくわかる作品もあります。それは、『ローマの祭』です。彼はよほどローマが好きだったのか、『ローマの噴水』という作品もあり、前出の『ローマの松』と合わせて“ローマ三部作”と呼ばれ、今もなお盛んに演奏されています。
そんな『ローマの祭』には、なんとライオンが登場します。同作は4部構成で、2曲目はキリスト教巡礼者による厳粛な宗教祭。3曲目は秋のブドウの収穫祭。そして4曲目は屋台の手回しオルガンや売り子の声、酔っ払いの下手な歌なども写実的に音楽に組み入れている乱痴気騒ぎのお祭りです。レスピーギの天才的な作曲技法が光る曲ですが、ライオンが登場するのは、その1曲目なのです。
1曲目の時代背景は古代ローマ、初期キリスト教徒を残忍な方法で虐待したことで有名な暴君ネロの時代です。当時のローマではキリスト教は邪教であり、キリスト教徒は処罰される存在でした。
紀元前より、古代ローマ皇帝は一般市民の不満を鎮め平和に治めるために、食料だけでなく娯楽まで提供していました。映画『テルマエ・ロマエ』(東宝)でも有名になったローマ風呂は、今でも遺跡として残っています。そんなななか、もっとも力を注いだのは、大人数の市民を円形の野外劇場に集めて行われる残酷な見世物だったのです。
そこでは、兵士をどちらかが死ぬまで戦わせたり、武器も持たない罪人とライオンを決闘させたり、市民たちが熱狂と悲鳴を同時に上げるような見世物が繰り広げられていました。
そのなかでも特に残酷なのは、何万人も市民が見つめている劇場のど真ん中に、無防備なキリスト教徒を集め、飢えたライオンを登場させ、恐怖に震えるキリスト教徒を襲わせて食い尽くさせる見世物でした。
レスピーギの『ローマの祭』では、ライオンが「ガオー」と威嚇する声、見物客が恐怖のあまりに上げる叫び声、そして襲いかかってくるライオンの興奮した恐ろしい吠え声、最後にはすべてを食べ尽くし満腹になったライオンが満足そうに上げる声を、オーケストラによって見事に再現しています。
そんな恐怖と残酷な音楽ですが、そのなかにも感動が含まれています。それは、キリスト教徒が歌う『グレゴリオ聖歌』です。ライオンを模倣する金管楽器がうなりを上げ、襲われる寸前でも、弦楽器によって歌い上げられる『グレゴリオ聖歌』は、動じることなく落ち着きに満ちた宗教的な信念を感じさせ、古代キリスト教徒たちが、最期までキリスト教を捨てない崇高さにあふれています。
そして、切れ目無しで2曲目に進んでいくと、後年、キリスト教がローマの国教になった時代に場面が変わります。そこでは、古代キリスト教徒がむごく殺されてもキリスト教を守り続け、神聖な街となったローマに、巡礼者たちが到着して感激する場面となるのです。
クラシック音楽には、時代を超えた物語を巧みに音楽で表現している曲がたくさんあります。これは、ほかのジャンルの音楽との違いでもあるでしょう。