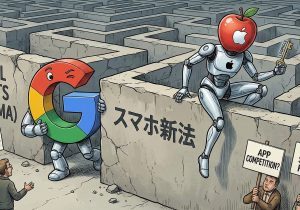無音で音楽の授業という奇妙な光景…コロナ禍での教育現場の混乱

学校での音楽の授業のために、子供に鍵盤ハーモニカやリコーダーを購入した親御さんは多いと思います。その際、「自分が小学生の頃、授業で苦労しながら演奏したなあ」と思い出された方もいるかもしれません。
大概は共同購入ですから、学校で子供は鍵盤ハーモニカを受け取り、音楽の授業の時に、ワクワクしながらケースを開けて取り出します。そこで先生から、まずは楽器の持ち方と指の動かし方を教わり、言われた通りに鍵盤を押さえていきます。教室内にみんなのカタカタと鍵盤を叩く音が響きわたって、しばらくして音楽の授業が終わるのです。
ここで、おかしいとお気づきになったと思います。音を出さずに、鍵盤だけ練習するというのは奇妙です。鍵盤ハーモニカは、その名の通りハーモニカのように息を吹き込み音を出して演奏します。そこで小学校としては、感染症対策として飛沫を飛ばさないために、楽器に息を吹き込むことを控えているのです。
これはNHK京都支局が、地元京都市の小学校を取材した際のニュースです。ほかにも、リコーダーも音を出さずに指の練習のみでした。取材を受けた小学校の教員は、「鍵盤ハーモニカは、楽器を持って指を動かす練習だけ。リコーダーも一緒です。子どもたちは実際にどんな音が出るか、わからないんですよね。でも、単元だからやるしかありません」と語っていました。音を出さない音楽の授業とは、計算をしない算数、漢字の練習をしない国語くらい変な話です。
このような制約は、音楽だけではありません。接触機会が多い体育はもちろん、理科でも、顕微鏡やアルコールランプなどを共有したり子供同士が近づく機会を避けるために実験を控えており、仕方なく子供たちは映像を見て学んでいるそうです。
それでも、前出の京都市の小学校では、マスクを着け小さな声でという制約はありながら、合唱をすることはできるそうですが、正直、僕は驚きを超えて心配になってきました。そこで、神奈川県川崎市の小学校に通っている僕の子供に聞いてみたところ、リコーダーも吹けるし、制約といえば、歌う際にマスクをしたままというくらいだそうで、安心しました。
つまり、地域や学校によって指針が違うわけで、教育現場も混乱していることがよくわかります。文部科学省のマニュアルの中に、「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」という項目があり、音楽に関しては「室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏」が、“特にリスクが高い”と書かれているのです。
文科省は、感染のレベルを3段階に分けています。レベル3は、「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高いことから、行わないようにします」と書かれていますが、レベル2では、「可能な限り感染症対策を行った上で、リスクの低い活動から徐々に実施することを検討します」と、少し判断に困るような表現で書かれています。やっとレベル1となっても、「換気、身体的距離の確保や手洗いなどの感染症対策を行った上で 実施することを検討します」と書かれており、結局どうしたらいいのか、僕が教員でも困ってしまうと思います。
しかも、文科省が現在公開しているマニュアル『学校における新型コロナウイルス感染症 に関する衛生管理マニュアル ~「学校の新しい生活様式」~ 最新版(2022年4月1日発行)』の音楽に関しては、2年前のもの(2020年9月2日発行)とほとんど変わっていません。新型コロナも変異を繰り返して、2年前とはまったく違う様相を見せていますし、医学的見地による感染症対策も、この2年間で進歩してきたはずです。
ちなみに現在、オーケストラでは、世界各地で繰り返された実証実験の結果を踏まえ、演奏に当たって飛沫を飛ばさない弦楽器はともかく、学校のリコーダーと同じく息を吹き込む管楽器であっても、飛沫は楽器内や奏者周辺にとどまることがわかっています。クラシック音楽の観客も声を上げるわけではなく、マスク着用で静かに聴いていただいているので、オーケストラ・コンサートでクラスターが発生したとは聞いたことがありません。
音楽教育の現場でも、冷静かつ合理的な検証を進め、子供たちには基本的な感染症対策を講じながら、のびのびと音楽を学んでほしいと願います。
指揮者の奇妙な練習風景
想像してみると、音を出さずに鍵盤ハーモニカをカタカタ叩いてみたり、リコーダーを吹く真似をしたり、そんな風景が繰り広げられている音楽の教室は、まるで冗談のようです。しかし、実は指揮者の僕も同じようなことをしていました。
指揮者が怖い顔をして情熱的に指揮棒を振ったり、笑顔で優しく指揮をしていたとしても、目の前にオーケストラがいなければ奇異な光景です。それでも、スコアを勉強しながら、出てくる音を想像しながら、自然に軽く指揮を振っていることはあります。特に、指揮をするのが難しい曲を勉強している時には、指揮の方法を考えながら、少し手を動かして練習することもあります。そんなときに家人がノックもなしに急に部屋に入ってきたときには、これほど恥ずかしいことはありません。
大学で指揮を勉強している時代には、ほかの学生が指揮をしているのを見ながら、自分も指揮の動作をしていました。ヨーロッパでは音楽大学を出たばかりの若者を集めて、夏に講習会が行われることがよくあり、もちろん指揮のコースもあります。20人くらいの生徒が、ほかの生徒の指揮を見ながら、同時に指揮の動作をしているのは不思議な光景です。若い指揮者の卵たちにとっては、とにかく指揮をしたくて仕方がないものの、オーケストラで振る機会がほとんどないので、我慢できなくなって指揮の動作をしてしまうのです。
僕が音大を出たばかりの頃、初めて行ったオーストリア・ウィーンの指揮講習会では、ほとんどがドイツ人とイタリア人の学生のなか、僕だけが日本人でした。ドイツ人学生は少し難しそうな顔をして軽く手を動かしている程度なのですが、太陽の国イタリアの学生はさすがです。まるで100人のオーケストラを目の前にしているかのように、ほかの生徒の指揮を見ながら、「自分のほうが上手く指揮できる」とでも言いたげな様子で、表現豊かに指揮の動作をしていました。
この時、僕も楽しくなって一緒に大きく指揮をしていたら、ほかの生徒をレッスンしていた先生が急に僕を指さして、「君、そこの指揮は違う!」と叱られてしまいました。こっちとしては、ただ気持ちよく指揮動作をしているだけでしたが、気を抜けないのでした。
ちなみに、その先生には、僕のレッスンの番でもガミガミと怒られました。それでも、優秀な生徒6名によるオーケストラ・コンサートの指揮者に選んでくれただけでなく、大トリの大役を与えていただきました。そこから、僕は指揮者としてスタートしたように思います。
(文=篠崎靖男/指揮者、桐朋学園大学音楽学部非常勤講師)