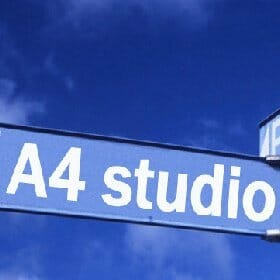研究室の教授に就活の状況見せたら退学を強要された…理系大学、アカハラ横行の理由

2021年11月下旬、あるTwitterユーザーの以下ツイートが一部で波紋を呼んだ。
「教授に選考状況を全て見せろと言われ、早期選考途中の3社を見せました。3社全てコンサル・シンクタンク系だったため、この研究室にお前は必要ないから内定出たら退学しろと言われました。就活終わったら研究に尽力すると伝えましたが、聞いてもらえませんでした…」
「正直そろそろ僕も限界を感じています。昨年は一個上の先輩1人、今年は一個下の後輩2人が研究を続けられない精神状態となってしまいました。教授は成果主義のためできない奴はいらないという考え方ですが、学生をここまで追い詰めるのは違うのではないかと思います…。」
このように理系の大学では、所属する研究室の教授から就職や研究をめぐって理不尽な対応を取られるアカデミックハラスメント、通称アカハラがあるという話は少なくない。また、所属する研究室によってその後の進路が影響を受けるといわれており、現に研究室によっては、大手企業とのコネクションを持つところもあるそうだ。
そこで今回は大学ジャーナリスト・石渡嶺司氏に理系大学生、大学院生に対するアカハラや、卒業後の就職状況について話を聞いた。
アカハラに関する法整備、対策は確立されていない
そもそもアカハラとはどのような定義で、現在どのような状況なのか。
「一般的には大学などの研究機関内で行われるセクハラ、パワハラ、モラハラのいずれか、もしくはそれらが重なるハラスメントを指します。現在、日本でアカハラの定義を定めた法的な根拠はありませんが、多くの大学ではハラスメント防止宣言、もしくはそれに準ずる対策をとっています。
今年1月の朝日新聞の記事では、アカハラに関する報道が2010年代前半は年2、3件であったものが、近年は年5件前後へと増加しているとのこと。もちろん報道された事件はあくまで表面化した氷山の一角にすぎず、実際数はもっと多いでしょう」(石渡氏)
では、なぜ大学の研究室でアカハラが起こりやすいのか。
「一般的に組織の一部署に同じ人間がずっと籍を置いていると、権限が集中しやすく、ハラスメントに発展しやすいというデメリットが出てきてしまいます。この点に関して、一般企業は大学に比べると人事異動が盛んに行われており、もちろん社風によって異なるでしょうが、上司に権限が集中する土壌の形成を定期的に排除することが可能です。
ですが、大学の場合、教員は最初に与えられた研究室で基本的に研究を続けていくことになります。他の大学へ異動することはありますが、同じ大学内で研究室を異動することは滅多にありません。ですからどうしても、教員側の権限が強くなりやすく、ハラスメントが生まれやすい空間になってしまうのです」(同)
そんなアカハラを防止できない背景には、大学の構造的な問題があるという。
「戦後の大学では、教員の自主、独立性を尊重する方針がとられていたため、個別の研究室に大学側が介入しづらいという事情がありました。大学は学長をトップとするピラミッド構造の組織にはなっているものの、研究室のなかのことは研究室内で対応してください、というスタンスが今なお根強いんです。
大学の相談窓口もアカハラに対しては十分に対応できるとは考えられません。先ほどの朝日新聞の記事によると、19校の大学のうち、5校が教員と相談員を兼任している事実が判明しました。これでは、相談を兼任している教員がアカハラを行った場合、相談窓口は正常に機能しません。
また専任の相談員がいる大学でも、女性が少ない、アカハラに対する専門的な知識がないなどの諸事情が判明しています。そして相談内容の複雑化により、被害者、加害者の区別がつきづらいという事実も明らかになりました。このように日本の大学では、研究室内の動きを監視、対策しづらいというガバナンス不全がよく見られているのです」(同)
大手企業の専門職枠も研究室に話が届きやすい?
またアカハラが発覚しにくい理由には、学生側のスケジュールが過密な点もあるという。
「学部生はもちろん特に院生の場合、自分の研究と同時に教員の実験や学会発表の手伝い、研究室の雑用をしなくてはいけません。大学院は修士課程2年、博士課程3年と定められていますが、そこでの生活は多忙を極めるため、ストレートに修了できず留年するという院生は少なくありません。仮にアカハラが起きたとしても加害者を糾弾する気力が起きにくいのだと考えられます。
教員からすると、自分も院生だったころに下積みとして同じことをやっていたので、ステップアップのために、今の院生にも当時と同じことを押し付けようとします。そこで、大学院での生活を覚えたり、研究のやり方を真似したりできるというのが彼らの言い分です。たしかに、一部利があることは認めざるを得ませんが、とはいえ院生は本来であれば独立した人材であるため、必要以上に研究室の仕事をやる義務はありません」(同)
では、理系学生の進路が研究室のコネクションで決まるということはあるのか。
「企業推薦は、大学のキャリアセンター経由での紹介があるものの、どうしても研究室つながりが多いですね。なぜなら、企業は研究室に直接伺ったほうが、求める人材にたどり着きやすいからです。
というのも、文系学生を採用する場合、専門性を問わず採用する、いわゆるポテンシャル採用というものが多いですが、理系学生を採用する場合、企業は自社の専門職枠とその学生の専攻を照らし合わせて採用することが少なくありません。たとえば、ある大手自動車メーカーの専門職の採用枠では、機械工学専門の学生を応募条件にしており、文系やその他の理系学生は応募できませんでした。つまり、企業は自社が求める専門職枠と親和性が高い理系学生を欲しているのです。
ですから結果的に学生の専攻、彼らの普段の生活をよく知っている研究室に推薦の話が来やすいのはある意味当然でしょう。余談ですが、あくまで学生の専攻が重要なので、偏差値が低い大学の学生でも専攻によっては内定をもらえるのは珍しくはないんですよ」(同)
では、アカハラを受けてしまった場合はどう対策すればよいのか。
「大学の相談窓口だけではなく、自分で弁護士に依頼したり、ハラスメント対策専門のNPOや相談機関に問い合わせたりするほうが、解決に向けての話は進みやすいかと思います。もちろん弁護士への依頼は費用がかかりますし、NPOや相談機関はマンパワーが足りていないところも多いです。ですが、学内で通報したとしても話を聞くだけで終わってしまうケースが多いので、さまざまなパターンを想定して対策する必要はあるでしょう」(同)
学生は所属する研究室の教員の趣向、裁量によって、アカハラ発生のリスクが付きまとう。場合によっては、就職斡旋も教員に委ねられる恐れがあるかもしれない。学生と研究室だけの問題とせず、外部から解決の糸口を探ることが重要になるだろう。
(取材・文=文月/A4studio)