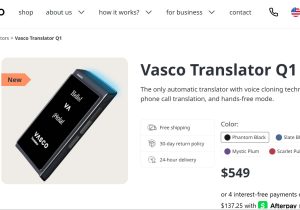ナイキ、オレゴンプロジェクトの闇…有望な女子強化選手、無理な減量強制で選手生命絶たれる

明日23日に開会式を迎える東京オリンピック(五輪)。新型コロナ禍にもかかわらず強行開催される背景には、莫大な資金や権力を握っているスポンサーや放送局、代理店といった存在があるはずだ。スポーツはアスリートだけでは成立しない。その理屈はわかるのだが、力を持ちすぎた企業がスポーツ界に暗部をつくり出してしまうケースは少なくない。
思い出されるのは、2019年10月に起きたナイキ・オレゴンプロジェクトのスキャンダル。このプロジェクトは、2001年にナイキが組織したアメリカの中長距離選手を強化するための精鋭チーム。ナイキにより資金、トレーニング、マネジメント面で多大なバックアップを受けられるとあって、中長距離選手にとってはまさに憧れのチームで、日本の大迫傑がアジア人で初めて所属したことでも知られる。
しかし、同プロジェクトのヘッドコーチ、アルベルト・サラザールが選手へのドーピングに関与していたとされて4年間のコーチ資格はく奪が決定。それに伴いプロジェクトの解散が発表された。そして、そのニュースに追い打ちをかけるかたちで、所属していたアメリカ女子長距離のホープ、メアリー・ケインもサラザールを告発。無理な減量を強いられ、月経が停止、エストロゲン不足で5度の骨折をして選手生命が絶たれるなど、女子選手への指導法への問題も浮き彫りとなった。
陸上界に激震が走った事件。だが、誰もが知るスポーツブランド、ナイキによるプロジェクトのスキャンダルにしては、認知度はそれほど高くない。「ナイキがビジネス面で大きな影響力が持っていたりと、複合的な要素があって継続的なニュースにならなかった」と、その理由を話すのはスポーツライターの小林信也氏だ。
ナイキは広告戦略でメジャーになったブランド?
「来年行われる世界陸上は、ナイキ本社のあるオレゴン州。この問題が大事となれば大会への影響は深刻だ。ナイキはもちろん、大会スポンサー企業などにとっても、それは非常に都合が悪い。ナイキの上層部がこの問題について事前にどのくらい把握していたかはわからないが、サラザールとその周辺の人物の責任にして企業の指示や関与を否定する必要がナイキにはあったのでしょう」(小林氏)
この後に、因果関係は不明ながらもナイキの当時CEOだったマーク・パーカー氏が退任しているが、ナイキは組織的にドーピングに関与していたことを否定。そして、この件に関して続報はほとんどなく、ナイキのブランドイメージは守られた。それどころか、厚底シューズが話題になり、「やっぱりナイキはすごい」という再認識が世間にもたらされた。
「そもそもスポーツブランドとしては他の人気ブランドより後発のナイキは、マイケル・ジョーダンとのスポンサー契約に代表される広告的戦略もあってここまで大きくなったブランド。だからイメージへの危機管理能力が高いのでしょう。近年、ナイキはCMに人種差別問題や社会問題をメッセージに込めることで話題を集めている。それ自体は支持も集めていますが、一方で社会的メッセージまで広告に使っている違和感も覚えますね」(同)
メアリー・ケインの告発はナイキを変えたのか
そもそも、ある意味でサラザールもナイキの勝利至上主義の被害者的な一面もある、と小林氏は話す。
「スポーツブランドとしては、強い選手に自社製品を使ってもらうのが一番広告効果がある。だったら自分たちで育ててしまおう、というのがオレゴンプロジェクトでした。しかし、中長距離、特にマラソンの分野では、世界歴代トップ100を記録した選手の約9割がケニア人かエチオピア人。トップ25まですべてこの2カ国の選手で、アメリカ人やその他の国の選手が勝つのは難しい。そのなかで、サラザールは企業をあげてのプロジェクトのコーチに任された。勝たせなきゃいけない、結果を残さなければクビになるという重圧のなかで、ドーピングに手を出してしまったとも考えられる。となれば、問題の根底は、ナイキをはじめとした大企業の、勝つことで商売にする勝利至上主義にあるともいえるでしょう」
強行開催によりIOCの貴族体質に変化の兆候
このようなメーカーなどの広告主義の犠牲者は、アスリートやコーチといった現場の人間だけではなく、スポーツ界全体に対しても決してプラスにならない。それはビジネスが優先されるここ数十年の、特にコマーシャリズムに翻弄される今回の五輪の姿を見れば明らかだ。
「それまでの五輪の開催都市は、多額の税金を投入したことで破綻に追い込まれるケースが続出していた。それが1984年のロサンゼルス大会で、組織委員会とIOC(国際オリンピック委員会)がスポンサーの協賛金や放映権等で大幅な黒字を出して独立採算のビジネスモデルをつくった。五輪の商業化は選手のプロ化を促し、日本でもプロとして満足に生活できる競技は野球と相撲とボクシングなど一部だったのが、それ以外の利権競技者でも五輪で活躍することで多額の収入を得られるようになった。コマーシャリズムが強くなりすぎてスポーツ本来の純粋さが失われてしまった。それが今の五輪の姿です」
しかし、小林氏いわく、アスリートや開催国の国民を無視して無理やりに開催される今回の東京五輪も悪いことばかりではないという。
「五輪がコロナ禍のおかげで変わり始めている。こんな状況でやるからこそ、今までやりたい放題だったIOCやその周辺の貴族体質がどんどんと削られている。感染拡大の懸念はありますが、五輪にとって、スポーツ界にとっては、非常に前向きな変化だと思います」
もはや賽は投げられてしまった。大ブーイングの中での開催となるが、“誰も得をしない五輪”で終わるのではなく、少しでも“商業ファースト”が排され、後世のアスリートや指導者が競技に集中できるような大会の礎になってくれればと願いたい。
(文=武松佑季/ライター)