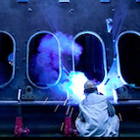日立造船、造船撤退から10年、漂着した「儲かる環境ビジネス」で世界トップも視野に
日本の造船業は高度経済成長の波に乗って急成長し、70年代前半にピークを迎えたが、その波に乗って同社も成長を続けた。だが79年の石油ショック、85年のプラザ合意以降の円高、90年代以降の韓国・中国勢の追い上げなどで日本の造船業は国際競争力を急速に低下させていった。それに伴い日立造船の経営も悪化。造船事業を独力で継続するのは困難と判断した同社は02年、旧NKK(現JFEホールディングス)の造船事業部門と自社の同部門を統合、ユニバーサル造船を設立するかたちで造船事業を分離し、「陸に上がった造船会社」となった。
造船事業から撤退した日立造船に、その代替となる有力事業は何もなかった。生き残るためには、造船事業の周辺事業的に行っていたゴミ処理施設、船舶エンジン、トンネル掘削機、海洋防災設備などの事業強化を図るしかなかった。ポスト造船の有望事業を求め、ヒラメ養殖など約100件の新事業にも手を出したが、ことごとく失敗した。
それから10年。試行錯誤の先にたどり着いたのがゴミ処理施設事業だった。廃棄物リサイクルなど環境意識の高まりや、それに対応した廃棄物処理法の度重なる改正が同事業を成長させていた。
2003年以降、造船事業全盛時代に蓄積した資産の切り売りで通期の最終赤字を辛うじて回避しつつ生き残り策を模索、環境ビジネスに活路を見いだし、ゴミ処理施設事業を成長戦略の要に位置付けられるようになったのは「スイスのイノバを10年末に買収、子会社化したのがきっかけだった」(証券アナリスト)。
イノバの前身のフォンロールは、日立造船ゴミ処理施設事業のいわば育ての親。日立造船は1960年に同社とのライセンス契約により欧州式ゴミ焼却発電施設技術を導入、それを元に65年、国内初のゴミ焼却発電施設建設に成功した経緯がある。以降、フォンロール時代を含め、イノバと日立造船はライセンサーとライセンシーの関係にあった。
ところがイノバの親会社が倒産し、イノバが売りに出されたことから日立造船は、自社ゴミ処理施設事業を飛躍させるチャンスと判断し買収したのだった。これによりイノバが欧州で保持していたゴミ焼却発電施設市場のシェア20%を獲得したほか、同社の営業拠点網を通じて北米、インドなど世界中で同事業を展開できる体制が整ったからだ。
●「儲かる環境ビジネス」の成長戦略
だが問題もあった。それは収益性だった。買収により設立された日立造船イノバの13年3月期の売上高は400億円近くと推計されているが、営業利益は「たった数億円しかない」(日立造船関係者)。実はイノバはゴミ焼却発電施設の設計から建設までを一手に手掛ける欧州随一のEPCコンストラクターだが、日立造船のように施設建設後の保守・運用サービスは行っていない。つまり「建てるまでのビジネス」の会社だった。