そして村上春樹を超越した『騎士団長殺し』が目の前に現れた。それだけで十分である。
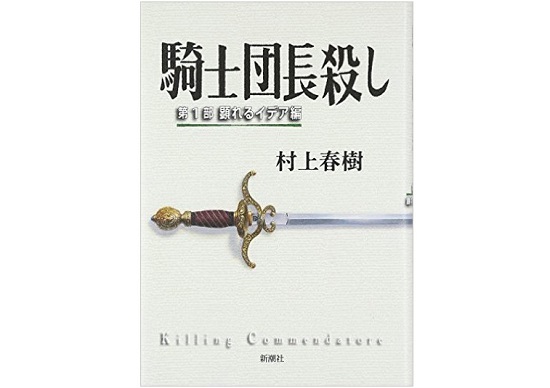 『騎士団長殺し』(村上春樹/新潮社)
『騎士団長殺し』(村上春樹/新潮社)昨年もそうだったが、ノーベル賞の季節になると、まるで季語のように村上春樹の名がメディアに浮上する。日本に全人口の1%ほどはいると思われる文学愛好家にとっては、そんなことはどうでもいいことになっていた。村上の作品ばかりを繰り返し読む、「ハルキスト」と呼ばれる人々。とりあえずは新作が出たら読んでみるという人々。嫌いだから批判するために読むという人々。村上の作品は、だいたい評価が真っ二つに分かれる。読んでみて嫌いになったから読まないという人々もいるだろう。だが、村上春樹の動向にまったく関心を持たないという人を、文学愛好家のなかに見つけ出すのは難しい。
村上春樹が世界的な作家であることは間違いない。日本の文学が英訳されることは珍しくなくなった。だが、ヨーロッパの主要言語から、カタルーニャ語、ガリシア語、ウクライナ語、リトアニア語、ヘブライ語にまで訳されているのは村上くらいだ。もちろん、中国語や韓国語にも訳されている。
読者の関心は、このところ、ノーベル賞を取るかどうかではなく、村上が小説を書いてくれるのかどうかに向けられていた。
2009-10年の『1Q84』(新潮社)という大作から時間がたちすぎているだけでなく、13年の『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(文藝春秋)というちょっとした作品は、読者を不安に陥れた。それは村上の文学技法だけが際だつ作品だった。水が干上がった泉の、むき出しの地肌を見せつけられたような気になったのだ。
このところ、レイモンド・チャンドラーの『高い窓』や『プレイバック』、サリンジャーの『フラニーとゾーイー』などの翻訳を村上は着実に発表している。文学愛好家としては、最高の作家が最高の作品を訳してくれるという、幸せな時代に感謝する気持ちになる一方で、作家としての村上の泉は枯れてしまったのではないかという不安が、頭をもたげたのである。
あるいはノーベル賞で騒がれることに嫌気がさして、村上の小説の登場人物がよくするように、最低限の荷物だけ持って旅に出てしまったのではないか。読者など見捨てて。
「私」と村上春樹
だが『騎士団長殺し』(新潮社)は発表された。最低限の荷物だけ持って旅に出たのは、この物語の語り手であり、主人公の「私」であった。
この「私」はいくつか、村上春樹本人と共通点を持つ。早朝に起床する習慣を持つこと、自分をハンサムだとは思っていないこと、音楽への趣味の幅広さ、画家と作家という違いはあるが、芸術家であるということ。
そして自分の作品に対する接し方も似ている。「私」は、こう語っている。






