中国、ハイテク産業と金融システムが瓦解の兆候…事実上の「ドル本位制」が行き詰まり
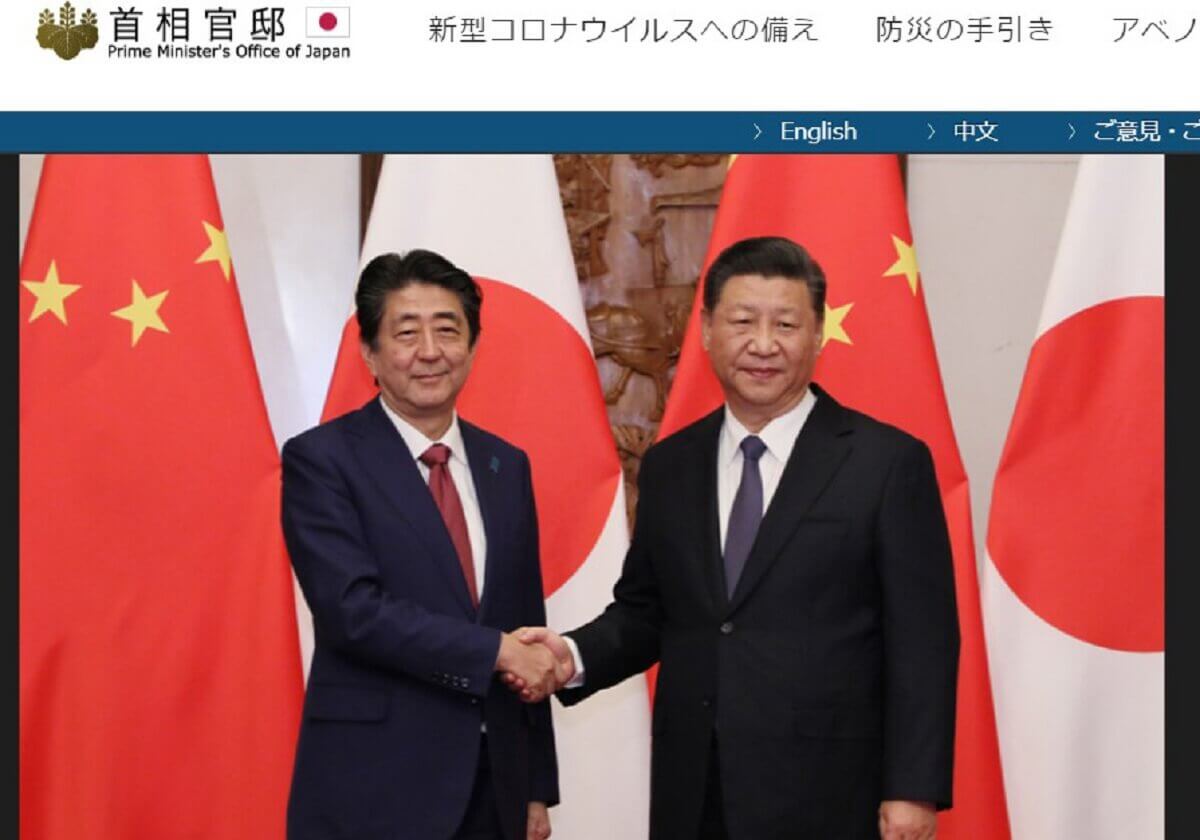
コロナ禍のなか世界に先駆けて経済回復の軌道に乗ったとされる中国だが、9月24日、国内第2位の不動産開発企業である恒大集団の株式が急落した。「恒大集団が8月24日に広東省政府に救済を求める書簡を送付した」ことをブルームバーグが報じたからである。
ブルームバーグの報道や中国のネット上で流れている情報によれば、恒大集団の有利子負債残高は2020年6月末時点で1200億ドルを超えており、同社が本社を置く広東省の政府に対し、深圳証券取引所への上場を来年1月31日までに認めることを求めている。上場が認められなければ、同社の大株主となっている戦略的投資家から最大200億ドルの資金を返還するよう求められるからである。このような事態になれば、同社は破綻し、取引のある約130の金融機関に悪影響が及び、50兆ドルにまで拡大した中国の金融システム全体を揺るがすシステミックリスクにつながりかねないと警告を発している。
恒大集団はこの書簡の内容を否定しているが、9月7日からすべての不動産物件を30%値引きして販売する方針を示すなど、資金繰りがいっそう苦しくなっていることは明らかである。しかし恒大集団だけが特別ではない。中国の大手不動産開発企業の多くは、今年6月末時点で短期債務を辛うじてカバーする手元資金しか残っていないことがわかっている(9月4日付ブルームバーグ)。
人民元の発行量抑制
不動産開発企業の流動性が急激に逼迫している要因は、コロナ禍でも中国の金融当局が引き締め政策を行っていることにあるが、田村秀男・産経新聞特別記者は「人民銀行が事実上の『ドル本位制』を採用していることに原因がある」と指摘する。
中国の法定通貨である人民元は、一定比率以上のドルの裏付けがあることで通貨の信用を保っており、人民銀行のドル準備が枯渇すれば、人民元は単なる紙切れとみなされてしまうリスクが生じる。このため人民銀行は貿易や海外投資などで得られた外貨(ドル)を一元的に管理し、外貨の水準に応じて人民元の発行量を決定している。しかし米国との貿易摩擦などの影響で、このところ外貨の水準が以前ほどには伸びなくなっていることから、人民銀行は人民元の発行量を抑えこむことを余儀なくされているのである。
金融機関からの借り入れが困難になった企業が「救い」を求めたのは社債市場である。中国の社債市場の規模は4.1兆ドルにまで膨れあがったが、今年上半期のデフォルトの総額は前年比46%増の100億ドル超と過去最高となっている。
資金繰りに苦しむ中国企業は海外からの資金調達にも熱心だったが、中国企業のドル建て社債のデフォルトの総額が9月下旬時点で120億ドルに達し、昨年1年間の3倍となっている(9月23日付サウスチャイナモーニングポスト)。今年末に償還期限を迎える中国企業のドル建て社債の規模は1018億ドルに達し、2021年は10%増え、2022年はさらに19%増えるという。
「中国製造2025」は風前の灯火
フランスの投資銀行であるナティクシスによれば、今後ドル建て社債のデフォルトが起きやすい業界は、不動産開発企業に加え、半導体などハイテク企業だという。
米中対立の激化により、グローバル・サプライチェーンが見直され、中国の半導体企業の収益が減少するとともに、米国政府による中国半導体企業に対する禁輸措置も悪影響を及ぼしている。米商務省は9月下旬、中国の半導体受託生産企業SMICに米国企業などが特定製品を輸出する場合、製品が軍事目的に転用されるリスクを理由に、事前に同省の許可を得ることを求める措置を打ち出した(9月27日付ブルームバーグ)。輸出許可制になればSMICから供給を受ける華為技術(ファーウェイ)にも大きな打撃になる。
9月に入り、7日と12日に相次いでロケット打ち上げに失敗しているが、米国政府が半導体チップの輸出を規制したことがその背景にあるとの指摘がある。中国政府は半導体の国産化を急いでいるが、2017年11月に武漢市内の経済開発区で建設が開始された半導体製造工場が、今年9月に資金不足を理由に事実上ストップしてしまった。「プロジェクトに投じられた200億ドルはどこに消えてしまったのか」として中国メディアは「中国の半導体産業で史上最大のペテン」と批判している。
中国初となる国産旅客機「C919」の2021年の就航も難しくなっている。C919の飛行制御システムの開発は米国企業が担当しているが、米国政府は軍事転用の可能性を理由に技術提供に慎重な姿勢を示しているからである。製造強国を目指す中国の国家戦略「中国製造2025」は、今や「風前の灯火」と言っても過言ではなく、ハイテク企業の経営破綻は時間の問題なのかもしれない。
中国政府は「米国債を大量に売却する」との脅しを盛んに仕掛けているが、金融面で追い込まれているのは中国のほうである。中国が香港に導入した国家安全法制を理由に今年7月に成立した米国の対中制裁法により、中国国有の4大銀行が保有する1兆1000億ドル相当のドル資金が危険にさらされている(6月30日付ブルームバーグ)。この法律は金融機関に制裁対象となる当局者への口座提供を禁じるものであり、制裁違反と認定された銀行は米国の金融システムへのアクセスが断ち切られることとなるが、当局者の多くが中国の国有銀行を利用しているとされている。そうなれば、事実上のドル本位制を採用している中国の金融システム全体が瓦解してしまうだろう。
このように、米国との対立が激化すればするほど、中国経済が崩壊していくリスクが高まるのではないだろうか。
(文=藤和彦/経済産業研究所上席研究員)











