伊藤忠、日本の脱炭素のカギ握る…画期的なビジネス開始、排出枠取引市場の育成の起爆剤に
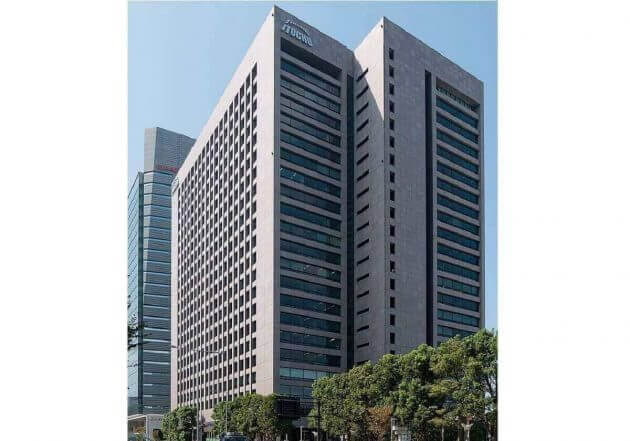
現在、世界的に脱炭素への取り組みが加速している。そのなかで、大手総合商社である伊藤忠商事があたらしい蓄電システムの販売を発表した。そのフローは、まず蓄電システムが、家庭が太陽光から得た電力を自家消費することの価値を計算する。その上で、ポイントと交換で伊藤忠は家庭から排出枠を調達し、それを企業に販売する。
ビジネスモデルのポイントは、家庭が自家消費する再生可能エネルギー由来電力に“環境価値”を見いだすことだ。それは2つの可能性を持つ。まず、ポイントは人々のより良い意思決定を支えるだろう。2点目に、伊藤忠の蓄電システム事業は、国内排出枠取引市場の育成に寄与する可能性がある。なお、環境価値とは再生可能エネルギーが持つ、二酸化炭素を排出しないプラス面を指す。
中長期的な視点で考えると、伊藤忠の取り組みは脱炭素に関する家庭と企業の取り組みを促進する要因の一つになるだろう。そうした展開が現実のものとなることは、伊藤忠の事業運営が、家計(家庭、消費者)にも、企業にも、そして、社会全体にも意義ある“三方よし”の価値観を体現することといえる。
脱炭素に向けて家庭の役割に着目する伊藤忠
近年、世界各国が脱炭素を重視した政策を進め、企業などに事業活動から排出される二酸化炭素を削減するよう求めている。それによって各国は環境関連の投資や技術開発、雇用を創出して経済成長を目指したい。
政府は2050年にカーボンニュートラル(二酸化炭素の排出を実質ゼロにすること)を実現すると発表した。どちらかといえば大手企業の取組みを念頭に置いているようだ。経済産業省が公表した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を確認すると、各産業での取り組み方針が記載されている。その意味は、各業界を代表するリーダー格の企業、あるいは業界団体を中心に、カーボンニュートラルに関する取り組み推進を求めるということだ。一例として、住宅産業ではZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)など省エネと再生可能エネルギーの活用を重視した住宅供給を増やすことが記された。また、蓄電池の活用を進めることも明記されている。
その一方で、個々の家庭、あるいは個人レベルで、どのように脱炭素への取り組みを進めるか、政府資料には詳細な取り組み方針が明記されてはいない。その点に伊藤忠は着目した。具体的に伊藤忠は、家庭に設置された太陽光発電システムと自社の蓄電システムをつなぎ、得られた電力を自家消費することの価値を算定する。伊藤忠の蓄電システム事業は、政府の取り組みをより掘り下げたものといえる。
重要なのは、伊藤忠が家庭の太陽光電力の自家消費分に価値をつけ、さらにはそれを取引する発想を事業化したことだ。伊藤忠のビジネスモデルでは、太陽光発電システムを導入してきた家庭が自主的に脱炭素への取り組みを進めることを目指している。それは、政府のスタンスとは異なるとの印象を持つ。政府は、メインの取り組み主体を企業に定め、必要に応じてカーボンフリー電源の導入などを義務付ける。以下で伊藤忠の蓄電システムのビジネスモデルの特徴を、2つの点から考察したい。
家庭の自家消費へのポイント付与の意義
1つ目が、ポイントの付与だ。これまでの脱炭素に関する日本の取り組みでは、再生可能エネルギーを用いて発電を行った家庭などが、企業に余剰電力を売却することに、環境価値を認めてきた。家庭(家計)は、再生可能エネルギー由来の供給者と位置付けられてきたといえる。
脱炭素には、再生可能エネルギーを用いた発電とその消費の増加が必要だ。伊藤忠はその原点に立ち返り、家庭の電力自家消費が脱炭素に貢献していると考えて環境価値をポイント化する。家庭は得られたポイントを使って買い物などに使うことができる。
政府の脱炭素への取り組み方針は、規制など相応の強制を伴う。それに対して、伊藤忠のビジネスモデルは人々のやる気、欲求(環境の保全に貢献したいという心理)を重視したものといえる。イソップ童話の『北風と太陽』にたとえれば、政府の発想は北風的、伊藤忠の発想は太陽に近い。
その違いは大きい。どちらのほうが効果があるかを考えると、後者だ。人は強制されると反発する。脱炭素を進める場合に、「こうやりなさい」と頭ごなしに、上から目線で取り組みを求めることが適切とは限らない。それよりも、人々に選択の自由を与えつつ、より効用(満足度)が高まる仕組みを考えたほうが無理なく、脱炭素への取り組みを進めることができるだろう。人々の注意を喚起し、社会の規範に照らしてより良い意思決定に導くことを行動経済学では「ナッジ」と呼ぶ。
固定価格買取制度(FIT)の下で、家庭は売電を重視した。その半面、太陽光に由来する家庭の電力自家消費への関心は高まりづらかったといえる。人工知能(AI)を用いて充放電を最適化する蓄電システムの開発によって自家消費に環境価値を認めることは、ありそうでなかった発想だ。蓄電池関連の技術に関しては、日本企業が競争力の発揮を目指して研究開発を進めている。伊藤忠の蓄電システムの導入が増え、新しい技術がそのシステムに実装されれば、既存の住宅での脱炭素化は加速する可能性がある。それは、日本が循環型経済を目指すために重要だ。
排出枠市場の拡大の可能性
2つ目として、伊藤忠の蓄電システム事業が排出枠取引市場の育成に寄与する展開が考えられる。排出枠取引とは、企業などが排出できる温室効果ガスの量(排出枠)を定め、超過した企業が、下回っている企業から排出枠を買うことなどを指す。
伊藤忠はポイントと交換することによって蓄電システムを導入した家庭から排出枠を獲得する。その上で同社は獲得した枠を企業に販売する。やや長めの目線で考えると、伊藤忠の蓄電システムを利用する家庭が増加すれば、伊藤忠と企業間の排出枠取引も増大する可能性がある。そのために、伊藤忠はシステムの有用性を消費者に訴え、蓄電システムの導入を増やさなければならない。導入コスト低下のために政策面からの補助も重要だろう。
それに加えて伊藤忠に期待したいのが、より多くの企業との連携だ。日本ではブロックチェーン(分散型元帳)を用いてインターネット上で、家庭が削減した排出量の取引に取り組む企業がある。伊藤忠の持つ家庭の発電データなどがそうしたネットワークと結合することは、取引拡大を支えるだろう。それは、日本の排出枠取引市場に深みをもたらす要因になり得る。
そうした展開が現実のものとなれば、排出枠取引は増え、社会全体で脱炭素への意識は一段と高まるだろう。取引市場の育成が進む結果として、海外の企業などが日本から排出権を購入するケースが増加することも考えられる。伊藤忠にはマーケット・デザインの主体的な役割が期待されているといってもよいだろう。
見方を変えれば、伊藤忠の蓄電システム事業は“三方よし(売り手によし、買い手によし、世間によし)”を体現する取り組みといえる。一つの展開として、各社の取引プラットフォーム上でポイントの互換性が進むなどして参加者が増えれば、より多くの家庭が排出枠取引に参加して脱炭素への取り組みが加速することが考えられる。そうなれば、伊藤忠などが取り組む排出枠の取引は社会的共通資本(持続可能なゆたかな社会を支える仕組み)としての役割を担うだろう。そうした展開を念頭に、伊藤忠が、排出枠取引に参画する企業との連携を強化し、取引のルールなどを統一化することを期待したい。
(文=真壁昭夫/法政大学大学院教授)











