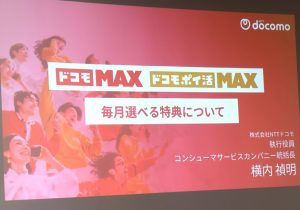熱狂的な親子のファンを持つ塾「探究学舎」が、『ドラゴン桜』より“スゴイ”理由

「探究学舎」は、受験も勉強も教えない塾。「学びは本来、楽しいもの」として、小学生向けを中心に「驚きと感動」を提供し、熱狂的な親子のファンを持つ。宝槻泰伸氏が2011年に東京・三鷹市に開校し、その後コロナ禍でのオンライン授業が評判となった。
文部科学省の新・指導要領で2022年春から導入される探究学習は、主体的な学びを促進するものだが、「探究学舎」はその流れを先取りしたものだ。
「探究学舎」は、同じ学びでも漫画『ドラゴン桜』(三田紀房/講談社、2021年にTBS系でドラマ化)とは何が違うのだろうか。「探究学舎」の考え方は、子どもだけでなく、大人にとっても思考を深める上で大いに役立つ。また、授業の内容や組み立て方、授業を進める先生たちのファシリテーション技術など、ビジネスパーソンが仕事に活用できる点がいくつもある。
探究心に火をつける、「探究学舎」の授業
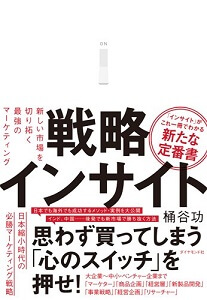
探究学習は2022年春から高校で導入されるが、小中学校でも特例校で導入されることになった。探究学習は、自分で課題を見つけ、情報収集し、分析し、表現する学習方法。今までの知識偏重型の教育を脱し、課題解決の力を育(はぐく)もうとするものだ。その背景には、高校生の勉強意欲が高まらないという問題がある。
「探究学舎」は、その学ぶ意欲を高める。受験も勉強も教えないが、その代わりに子どもたちが「好きなこと」「やりたいこと」を見つけることができるように、「もっと知りたい!」「やってみたい!」という興味の種をまき、ひとりひとりの探究心に火をつける、そんな興味開発型の学び舎だ。
その原点は、宝槻氏の幼少期にある。型破りな父親の教育方針が、「探究心に火がつけば子どもは自ら学び始める」というもので、その実体験がベースになっている。
「探究学舎」のすごいところは、『ドラゴン桜』の「東大合格」のためのテクニック習得以上に、一生ものになる「学ぶ楽しさ」や「考える喜び」が体験できるところ。宝槻氏は高校中退後、大検を取得し、京都大学に進学しているが、大学に合格すること以前に、学ぶ楽しさや喜びを体験することを大切にしている。
筆者にも、小・中学生の二人の子どもがいるが、この「学ぶ・考える喜び」が何より大切だと思っている。受験をする場合でも、この「楽しさや嬉しさ」が得られれば成功。たとえ合格しても、学んだり考えたりするのが嫌いになってしまったら、元も子もない。今の時代もそうだが、これからの時代はますます、一生学び続ける必要がある。学歴を得たら終わりという時代はとっくに終わっている。卒業してからも、新しいことに好奇心をもって「探究」し続ける姿勢が欠かせない。
「探究学舎」の授業に親子ともに熱狂するのは、なぜか
「探究学舎」は、何がそんなにおもしろいのか。どうして子どもたちが夢中になるのか。授業を具体的に見てみよう。
まず、授業の分野を見ると、宇宙・生命・元素・医療・数学・経済・歴史・芸術・ITなど実にさまざま。人気の科目は「生命進化編」「戦国英雄編」「宇宙編」「元素編」など、入門者向けの授業だ。
例えば、「生命進化編」では、どんな授業が繰り広げられるのか。カンブリア紀には、どんな生き物が現れて、どう進化し、あるいは絶滅して、今につながるのか? いろいろな古代生物がカードになっていて、時代順に並べたり、グルーピングしたり、カードゲームのように楽しい。まるで、ポケモンカードのようではないか。数人ずつのグループに分かれて話し合うから、誰もが参加できる。不思議な形の古代生物のフィギュアがあるので、さわって遊ぶこともできる。また、生物の大量絶滅がどうして起きたのか、みんなで考えて発表する。「気温が下がった」「食べ物がなくなった」「酸素がなくなった」など、自分の考えを言いたい子どもたちの手がいっせいに挙がる。
ここで大事なのは、正しい答えを求めているわけではないこと。全然違っていても、「なるほど、そういう見方もあるね」「その考え、おもしろいね」と受け止めて、考えること自体を推奨する。だから、自分なりに考えて発表する楽しさがある。「あっ、思いついた!」と、ひらめいたときのぞくぞくするような嬉しさも実感できる。グループ間で得点を競ったり、親のグループも参加して、いつのまにか子どもグループ以上に熱中していたりする。
内容自体は、かなり専門的でマニアックなものだが、掘り下げた内容のほうが子どもたちはハマる。そして、「古代生物」を起点にして興味が「生物の細胞」に広がったり、「人類の起源や進化」へと広がったりしていく。
オンラインの授業でも、全員で発表し合うだけでなく、小グループのホームルームに分かれて濃い時間を楽しめるようになっている。また、オンラインだと体感が少なくなるので、例えば戦国英雄編では、つまようじを木材代わりにしてお城をつくったり、お気に入りの武将の鎧や兜を紙やダンボールでつくって着てみたり、工作やお絵描きなど五感を使った学びが得られる。
クイズ大会もある。カフート(kahoot!)というノルウェーの教育スタートアップ企業が世界で注目されているが、そのサービスをいち早く取り入れているので、オンラインで簡単に4択のクイズをつくることができるのだ。
大人のビジネスの世界でも、SDGsなどはゲームをしながら学べる教材がいくつも開発されている。カードゲームだったり、ボードゲームだったりを楽しく遊びながら、ワークショップ形式で学んでいく。大人であっても、興味をもって楽しく接したほうが、学びや気付きは多くなる。
仕事に活かせる、多くの気付き
筆者はマーケティングのコンサルティングをしているが、ある意味、おもしろがって熱中すればするほど、よいアイデアが生まれる。「これは、難問中の難問だ」「いや、そもそも問題は何なのか」など、考えることに喜びを感じ、「探究する」ことに楽しさを感じている。どれだけ仕事にワクワク感や楽しさを感じられるかが、アウトプットの質に直結する。だから、おもしろがれる点を見つけるのが大事。「探究学舎」の子どもたちではないが、1つの興味点を突破口にして、興味を広げていく。例えば、フリマアプリの場合、「最もメジャーなM社のアプリではなく、R社のアプリを使っている人って、なぜなんだろう?」いう疑問を起点にして、謎解きを広げていく。
この考える楽しさやひらめいたときの喜びがあるから、学びが深まり進化もしていける。おもしろいと思うから、スキルも上がっていく。
また、コンサルティングをする中で、プロジェクトチームのメンバーとワークショップを行い、そのファシリテーター(進行役)をすることも多い。ワークショップは問題解決を導き出す有力な手段になるため、日本企業の中でも広がりつつあるが、その成否を決するのが、ファシリテーター。今後、ワークショップや会議を効果的に運営するファシリテーション・スキルが、ますます求められるようになってくるだろう。
「探究学舎」の先生たちは、授業をしている「先生」というより、子どもたちを夢中にさせる「ファシリテーター」に近い。いかに子どもたちに楽しく考えさせるか、ある意味「エンターテイナー」でもある。子どもたちからどんな答えが返ってきても、「おもしろいね!」と受け止め、どんどんアイデアを広げていく。沈滞ムードになったときは、自ら道化を演じてでも、場を盛り上げる。つまり、楽しく考える環境・状況を作り出している。これは、まさに、ファシリテーターの神髄である。
まさか、子ども向けの教室で、これだけビジネスに活かせる気付きが得られるとは。学びの教材は、さまざまなところにあるものだと、改めて気付かされた。
(文=桶谷功/株式会社インサイト代表取締役)